『中央公論』2023年6月号
「問われる日本型雇用と労働観−テレワークは広がるのか」
JILPTのコロナ調査から
今から3年前の2020年前半期には、新型コロナウイルス感染症対策として、政府の緊急事態宣言を受けて多くの職場でテレワークが実施され、通勤電車はガラガラの状態であった。その後何回も感染の波が日本を襲い、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が繰り返し発出されたが、テレワークの普及率は小さく波打ちながら、ある程度の水準で落ち着いているようである。労働政策研究・研修機構(JILPT)は20年から20年初めにかけて、企業と個人を対象としたコロナの影響に関するパネル調査をそれぞれ実施したが、企業ベース(図1)で見ても個人ベースで見ても、コロナ以前よりは高い水準でテレワークが定着していることが分かる。
ただし、個人調査(図2)に示されているように、完全テレワークは2割程度にとどま
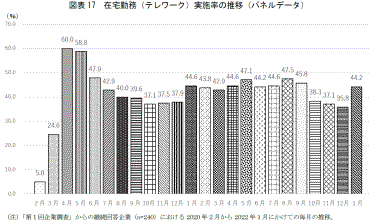
っており、出勤する日と在宅勤務の日を組み合わせた部分的テレワークという形で定着しつつあるようだ。ということは、時々出勤しなければならないので、地方に在住して東京の会社にテレワークする
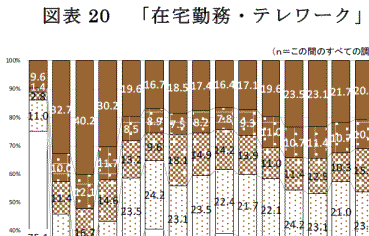
という一時注目されたパターンが普及する可能性は低い。つまり、本特集の問題意識である「テレワークで地方創生は進むか?」という点では、答えはNoなのが現状だ。
それどころか、ピーク時から見ればかなりの揺り戻しが生じている。その理由について、JILPTが20年末に行った企業へのヒアリング調査では興味深い指摘がなされていた。それは、緊急事態宣言下のテレワークは「半ば強制的に、会社の号令に基づいて進んだ」もので、「テレワークというより新型コロナウイルス感染拡大防止のためのひきこもりに近い状態」であり、「事実上の自宅待機」であったというものだ。
これは、社外から社用メールを送受信できたり、勤怠管理や決裁等の手続きをオンラインシステム上で完結できたりするといったハード面の環境整備があまり進んでいなかったことも原因である。しかしそれだけでなく、労働時間の適正な把握や勤怠管理(働きぶりの「見える化」)をテレワークの課題として挙げる声が多かったことは、仕事の進め方などのソフト面におけるテレワークとの相性が問題とされていることを物語っている。
ごく最近でも、Job総研の「2023年リモートマネジメント実態調査」(同年1月)によれば、マネジメントする側の69.3%がテレワークでのマネジメントに課題を感じていた一方、全体の65.4%がテレワークで「サボり経験あり」と回答し、マネジメントする側は86.7%がそれを黙認しているとのことであり、問題がソフト面にあることが裏付けられている。この問題を追究していくと、職務(ジョブ)がよくいえば柔軟、悪くいえば不明確な日本型雇用システムとテレワークとの相性という論点に行き着くのだが、その前にまずは文明史的観点からテレワークの在り方の推移を概観しておこう。
テレワークの進化3段階とコロナ禍
コロナ禍直前の2019年11月に、国際労働機関(ILO)が刊行した『21世紀のテレワーク:進化的パースペクティブ』(Telework in the 21st century: An evolutionary perspective)という報告書は、その導入部でテレワークの進化を3段階で説明している。
第1世代はホームオフィスの時代で、1980〜90年代前半である。自宅で電話やファクスを利用して、在宅勤務をしていた時代である。当時は通勤しなくていいという点に着目して、テレコミューティングという言い方が一般的であった。当時のテレワークを前提に、エレクトロニック・コテージ(情報通信器機が備わった住宅)が普及するという将来像を描いた本が、今や古典となっているアルビン・トフラーの『第三の波』である。
第2世代はモバイルオフィスの時代で、1990年代半ば〜2000年代である。自宅で電話やファクスを使っていた時代から一段進化し、ラップトップパソコンや携帯電話を利用して、自宅以外でもテレワークができるようになった。
そこからさらに進化して、10年代以降が第3世代のバーチャルオフィスの時代になる。何が変わったかというと、電子機器がラップトップパソコンや携帯電話から、スマートフォンやタブレットに進化したのだ。大した変化ではないようにも見えるが、これによって情報処理と通信が完全に一体化し、情報はクラウド上で常時アクセス可能になったので、「いつでもどこでも」情報にアクセスし、通信し、仕事をすることができる時代になったのである。
この「いつでもどこでも働く(working anytime anywhere)」というのが、第3世代のバーチャルオフィスの時代を象徴するフレーズである。17年にILO と 欧州生活労働条件改善財団が共同研究成果を報告書にまとめているが、その報告書のタイトルが、『Working anytime anywhere』であった。今や、いつでもどこでもスマートフォンなどからクラウドにアクセスして仕事ができるようになったというのが、コロナ禍直前の時代認識であった。
ところが、20年から世界中に広がったコロナ禍によって、日本だけでなく世界中どこでも、今までホームオフィスも、ましてモバイルオフィスも経験していなかったような多くの人たちが、いきなりロックダウンだ、ステイホームだと言われ、急に家で仕事をするよう迫られる事態になってしまった。いわば第1世代のままでテレワークが急激に拡大したことになる。その実態を欧州生活労働条件改善財団による20年の報告書は、在宅勤務の実施者が、都会在住の高学歴で高所得のサービス分野のホワイトカラー労働者に偏っており、労働者間の階層格差がはっきりと表れていると指摘している。この傾向は日本でも見られ、JILPTの高見具広は「在宅勤務は誰に定着しているのか」(JILPTリサーチアイ2020年9月16日)において、情報通信業で定着率が高く、建設業、サービス職、技能・労務職で定着率が低いこと、また、性別、年齢、学歴、雇用形態、勤め先企業規模、勤続年数、居住地域によっても適用率差があることを示している。
日本におけるテレワーク政策
日本でテレワークが政策課題として取り上げられたのは1990年代半ば、当時の労働省と郵政省がテレワーク推進会議を開催したのが始まりである。その後2004年に厚生労働省労働基準局から在宅勤務ガイドラインが発出され、一定要件下で事業場外労働のみなし労働時間制を適用できるようになった。これに対して経済財政諮問会議の労働市場改革専門調査会(八代尚宏会長)が緩和を求め、08年の改定ガイドラインではその制度のより細かい解釈が示された。
ところが16年からの働き方改革においては、長時間労働の是正が大きな柱とされたため、これを受けた18年の事業場外勤務ガイドラインでは、むしろ厳格な労働時間管理に傾斜した記述が目立つようになった。そのうち特に時間外・休日・深夜労働の原則禁止や許可制を示唆した部分は、規制改革推進会議による19年の第5次答申で「通常の事業場での働き方に比べて制約が大きいという認識を与えかねない」との批判を受け、その見直しが予定されていた。
ちょうどそこにコロナ禍が直撃し、20年8月に厚生労働省で「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」が設置され、その報告書を基に21年に新たなテレワークガイドラインが策定された。この検討会には筆者も参加して意見を述べたので、報告書にも盛り込まれているが、いくつか論点を示しておきたい。
・人事評価
まず日本ではこの間、テレワークに関しては人事評価をどうするかということばかりが関心事項になっていたが、これは諸外国ではほとんど見られない現象であった。人事評価というのは表面上の問題であり、根源的な問題はむしろ業務のやり方、進め方にある。例えば欧米のオフィスであれば、ITが入る以前から基本的に文書ベースで仕事をしている。その文書ベースの仕事の進め方が電子化されるだけであり、テレワークになって距離が離れても、基本的にその延長線上で行われる。これに対して、日本のオフィスでは文書ベースというよりもオーラル(口頭)コミュニケーション、場合によればノンバーバル(非言語)コミュニケーションが重要で、それが電子化されてもやはり「ちょっと来て、説明しろ」ということになるし、それをテレワークでやるのはなかなか難しい。その難しさの一つの表れが人事評価の問題である。したがって根が深い話であり、人事評価の方法だけ変えれば済むものではない。では仕事の進め方をがらりと変えて、基本的に文書ベースで全部やるべきだという話になるのか。日本の組織の在り方とも密接に絡む問題なのでこれがまた難しい。
テレワークでは新人育成ができないという悲鳴も、この人事評価の話とつながっている。日本では即戦力として新卒労働者を採用するわけではなく、スキルのない状態で採用して上司や先輩が鍛えていくというやり方である。一人前の労働者と異なりある程度仕事をまかせながら適時監督するというわけにはいかず、作業がおぼつかないのを手取り足取り指導しなければならない。そうすると、文書ベースだけではなかなかうまくいかず、どうしても濃厚なオーラル/ノンバーバルコミュニケーションが必要になり、テレワークとの相性が悪くなる。
・労働時間制度
21年のガイドラインは18年のガイドラインに比べて労働時間制度の自由度を若干高めており、通常の労働時間制度をとる場合でも始業・終業時刻を労働者ごとに自由に認めることはできるのだとか、フレックスタイム制や事業場外労働のみなし労働時間制はテレワークになじむ等と書かれている。事業場外労働のみなし労働時間制については、1988年の通達でポケベルで指示を受けている場合は労働時間が算定できるので適用できないという厳格な解釈が示されており、携帯電話やスマートフォンとなればなおさら無理ではないかと見られていた。そのため2021年のガイドラインは、わざわざ「情報通信機器を労働者が所持していることのみをもって、制度が適用されないことはない」と述べている。この点については細かな法的議論が繰り広げられているが、そこは省略して、それに関わるやや思想的な考察を述べておきたい。
長時間労働の抑制と労働者の私的自由の矛盾
今回のコロナ禍で、非常に多くの人が思いもかけず在宅勤務をすることになった。その結果、厳格な労働時間管理は長時間労働の抑制という観点からは望ましいが、一方でそれが労働者の私生活に対する介入にもなりうるということを、かなり多くの方々が経験したのではなかろうか。新聞報道でも、常時ウェブカメラで在席を確認されるとか、離席する場合はちゃんとチャットで投稿しなければならず窮屈だという苦情が紹介された。かえって息が詰まる、せっかく家にいるのに何でそこまで縛られるのか、というわけである。
それを念頭に置いて、21年のガイドラインにおける、テレワークに対する事業場外労働のみなし労働時間制の適用要件を読み直してみると、即応しなくていいとか、離席してもいいと書かれている。これは、裏を返すと、上司から何か言われても、すぐに反応しなくてもよく、しばらく席を離れて自分のことをやってもいいということであって、それは実は労働者にとってのメリットでもある。
これまでのテレワークは、少数の先端的な人々の働き方というイメージが一般的であったが、今回のコロナ禍で、ごく普通の仕事をしている人たちが在宅勤務をすることになった。日頃は大部屋で上司から見られながら仕事をしている人が在宅勤務になったため、上司も以前の感覚のまま見えていないと心配だからと、「ちゃんと顔を出して俺に見せろ」と言いたくなってしまう。
このように、今回のコロナ禍に伴った在宅勤務は、長時間労働の抑制だけが労働者のメリットなのではなく、労働者の私的自由も大事であり、とりわけ在宅勤務ではそれこそを重視すべきではないかということが、改めて意識化された経験だったと考えられる。実は、上記04年と08年のガイドラインには、「在宅勤務については、事業主が労働者の私生活にむやみに介入すべきではない自宅で勤務が行われ、労働者の勤務時間帯と日常生活時間帯が混在せざるを得ない働き方であることから、一定の場合には、労働時間を算定し難い働き方として、事業場外労働のみなし労働時間制を適用することができる」という記述があった。つまり、単に会社の外にいて行動を把握しにくいから労働時間の算定が問題となっているのではないのだ。
みなし労働時間制はもともと、外回りのセールスマンがどこに行っているか分からないから、一定の時間働いたとみなすしかない、という発想で1987年に作られた。ところが、今ではみんなスマホを持っているので、外回りをしている労働者がいつどこにいるかというのは、会社側には掌を指すように分かる。35年前にポケベルを持っているだけでもだめだったのなら、今のセールスマンでみなし労働時間制が適用できる人などほとんどいないはずである。しかし、そのように単に労働時間を算定しにくいということではなく、自宅にいる労働者の一挙手一投足を監視するようなことは望ましくない、つまり技術的には労働者を監視して正確な労働時間を算定することはできるけれども、あえてしないという価値判断もありうるだろう。
もちろん、在宅で目が行き届かないからといって、野放図な長時間労働を認めていいわけではない。長時間労働の抑制と労働者の私的自由の確保という二つの利益のバランスをどうとるかが問題なのである。少なくとも、通常の労働時間制度を適用するために、ちょっと買い物に行くからこれから1時間年休を取りますというような、中抜け時間を時間単位年休扱いにするなどの過度に厳格な労働時間制度はおかしな話なのである。この点は2021年ガイドラインで改善された。
「いつでもどこでも働く」社会はユートピアかディストピアか?
以上は在宅勤務(ILOの3段階説ではホームオフィス)を想定した議論であった。では、技術的にはそれを遥かに超えてモバイルオフィスやバーチャルオフィスが可能になりつつある今日、「いつでもどこでも働く」ことに対してはどう考えるべきだろうか。在宅でなくても、そこは労働者の私生活の場であるから、むやみに介入すべきではないということになるのだろうか。
実際にコロナ禍をきっかけに「ワーケーション」というやや特殊な形態で、そうした働き方の機会が一般労働者層にも開かれつつあるようだ。観光地やリゾート地で、休暇を取りながらテレワークするというスタイルは、国土交通省やいくつかの自治体が、地域振興を意図して推進しようとしている。しかしここまでくると、労働時間規制との矛盾がさらに大きくなってくる。そもそもワーケーションとはワークとバケーションを組み合わせた造語だが、バケーション(休暇)とは非労働日(時間)という意味なのだから、言葉自体が矛盾をはらんでいる。
リゾート地で休暇を取っている以上、労働者の私生活の場であり、会社が一挙手一投足を監視するべきではない。それは、「働き過ぎていないだろうな、ちゃんと休んでいるだろうな」という遵法のための監視であっても同じであるはずだ。上司に見張られることなく、温泉に浸かったり山野を歩き回ったりしながら、自分の都合でやりたいときに仕事をする。何と素晴らしいユートピアの実現であろうか。しかしこれを悪意をもって描写すれば、非労働日のはずの休暇が労働で充たされ、「いつでもどこでも」労働を強いられる究極のディストピアとなる。それがユートピアなのかディストピアなのかは、個人の人間観と労働観の関数で導き出されるものであり、一義的な回答は不可能であろう。
ただ、現行労働法制と折り合いをつけるためにはやっておくべきことがある。それは、少なくとも現時点では、労働基準法上の労働者に該当するのかの判断基準には空間的・時間的拘束性という項目があり、空間的・時間的拘束性が希薄になればなるほど労働者としての保護を受けられなくなる可能性(危険性)が高まるということからくる。別に保護など要らない、フリーランスで結構という考え方もあるが、空間的・時間的自由と引き換えに、例えば賃金支払いや解雇規制など、明らかに労働者であることに基づく保護が失われるとすれば、躊躇する向きも多いはずである。
地方創生のためにテレワークを推進したいのであれば、こうした問題を解決しなければならない。そのためには、例えばワーケーション型の裁量労働制、新たな労働時間の適用除外制度といった、何らかの法制的な工夫が必要になるのではなかろうか。そして将来的には、「いつでもどこでも働く」ことが一般化する中で、「労働者保護とは労働者の何をどのように保護することなのか?」という哲学的な問い直しが不可避となるであろう。
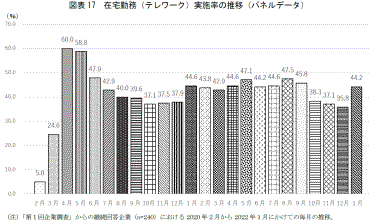 っており、出勤する日と在宅勤務の日を組み合わせた部分的テレワークという形で定着しつつあるようだ。ということは、時々出勤しなければならないので、地方に在住して東京の会社にテレワークする
っており、出勤する日と在宅勤務の日を組み合わせた部分的テレワークという形で定着しつつあるようだ。ということは、時々出勤しなければならないので、地方に在住して東京の会社にテレワークする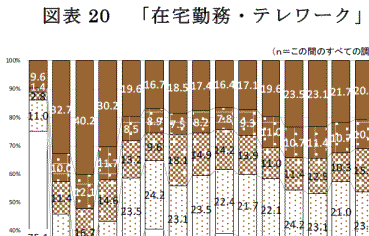 という一時注目されたパターンが普及する可能性は低い。つまり、本特集の問題意識である「テレワークで地方創生は進むか?」という点では、答えはNoなのが現状だ。
という一時注目されたパターンが普及する可能性は低い。つまり、本特集の問題意識である「テレワークで地方創生は進むか?」という点では、答えはNoなのが現状だ。
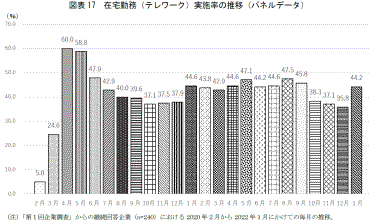 っており、出勤する日と在宅勤務の日を組み合わせた部分的テレワークという形で定着しつつあるようだ。ということは、時々出勤しなければならないので、地方に在住して東京の会社にテレワークする
っており、出勤する日と在宅勤務の日を組み合わせた部分的テレワークという形で定着しつつあるようだ。ということは、時々出勤しなければならないので、地方に在住して東京の会社にテレワークする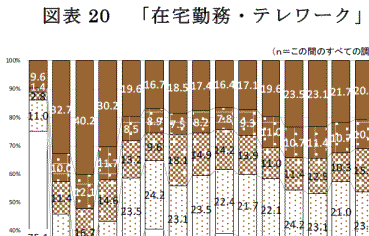 という一時注目されたパターンが普及する可能性は低い。つまり、本特集の問題意識である「テレワークで地方創生は進むか?」という点では、答えはNoなのが現状だ。
という一時注目されたパターンが普及する可能性は低い。つまり、本特集の問題意識である「テレワークで地方創生は進むか?」という点では、答えはNoなのが現状だ。