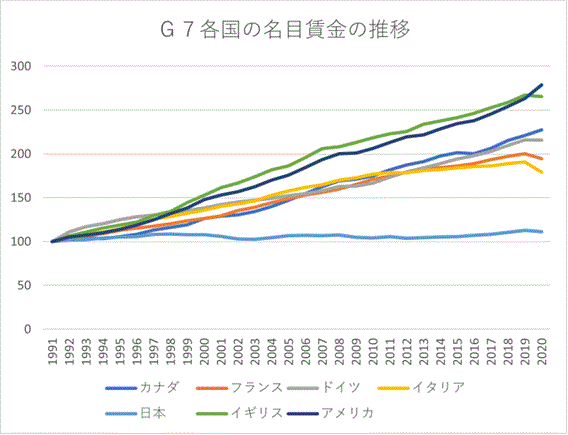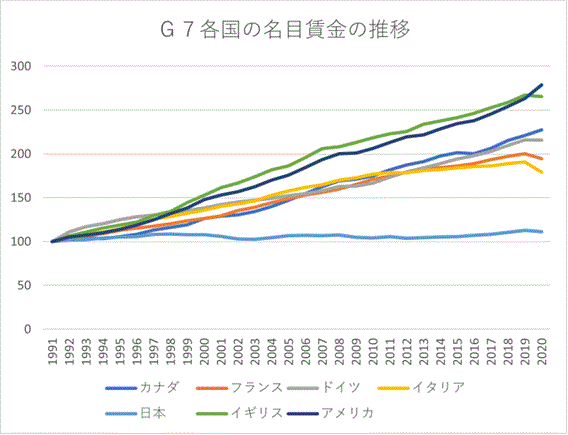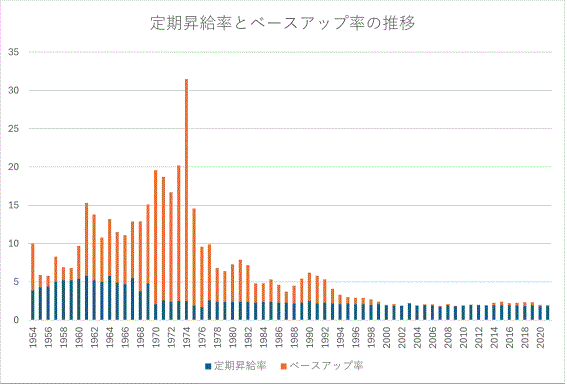『Work & Life 世界の労働』2025年第1号
「日本の賃金はなぜ上がらないのか」
濱口桂一郎
官製春闘とも言われる政府の掛け声の中で、2023,24年と、ようやく過去2年間にかなりの賃上げが実現したが、それまでの約30年間にわたって、日本の賃金はほとんど上がらなかった。日本の賃金が上がらないということは、労働研究者の関心を惹き、2017年には玄田有史編『人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか』(慶應義塾大学出版会)などという本まで出たくらいだ。この間、他の先進諸国の賃金が上がっているのに日本だけ賃金が全然上がっていないことを示す図1のようなグラフがよく出回った。これは『令和4年版労働経済白書』に載っているグラフだが、読者もどこかで目にしたことがあるだろう。これを見ると、確かに他の先進諸国が多かれ少なかれ着実に賃金が上がっているのに、日本だけはほとんど上がらず低迷していることが一目瞭然である。
図1 G7各国の名目賃金の推移
ところが一方、この30年間、読者諸氏の賃金は本当にこんな風に低迷してきているだろうか。そういう人もいるだろうが、一般サラリーマンの多くは、必ずしもそうではなかったはずだ。30年前の賃金と今の賃金がこのグラフのようにほとんど変わらないという人は少数派で、多くの人は「いやこのグラフの諸外国並みに上がってきているよ」と答えるのではなかろうか。
実際、この30年間の春闘結果は、政府の発表でも日経連/経団連の発表でも連合の発表でも、ほぼ毎年2%程度ずつ賃金が上がってきていることになっている。毎年2%ずつ賃金が上がると、10年で2割増し、20年で5割増し、30年で8割増しになり、このグラフのイタリア程度にはなっているはずだ。労働者(正社員)個人の賃金はそれなりに上がってきているのに、日本全体の賃金の動向を見るとそうなっていない。このミクロとマクロの違いは何によって生み出されているのだろうか。その答えを出すのは、昔ながらの労使関係論を知っている人にはたやすいはずである。
その答えは、毎年2%の賃金引上げというのは「定期昇給込み」の数字だからである。この30年間という時代は、賃金の上げ方という観点からすれば、「ベアゼロと定昇堅持の時代」であった。一人ひとりの労働者(正社員)からすれば、ベースアップはなくても毎年自分の賃金は上がっていくのだから、まあこれくらいで仕方がないな、と思えたのかも知れない。ところが、その定期昇給というのは、労働者個人にとっては確かに自分の賃金額の引上げではあるのだが、それを全部足し上げたら、労働者全員の賃金は全然上がっていないのである。このメカニズムについては、今から70年前の1954年に、日経連の地方組織であった関東経営者協会が見事に語っていた。これは戦後日本労使関係史上極めて有名な文書である。
・・・ベース・アップとは文字通りに考えれば労務費総額を全労働者数で除したる商が賃金ベースであるからこれを引き上げることであるということができる。従ってベース・アップの内容である配分は問題にならないかにみえるが、しかし多くの場合はベース・アップの内容は支払基準即ち支払の条件及び額の膨張を伴わないと実施しえないので、賃金体系変更の一つであり且つ労務費が増大するものと規定しうる。
これに対して定期昇給の場合は賃金体系を固定したまま労働者の新陳代謝、労働の量質の向上に伴う労働者個々人の査定替えでありベースとは全く無関係である。しかも賃金体系を固定化してあるため長期的には労務費の増大をきたさないものとみられている。従って定期昇給がベース・アップとは場を異にするにも拘らず、それを否定する形において登場してきたということは企業の実態から労務費を増大せしめるが如きベース・アップはできないという事情にあること、又国際収支の悪化している国民経済の危機の現状からも輸出阻害要因となる製品コスト引上げを齎らす賃金増額が不可能な点からも定期昇給がせいぜい限度であるということである。・・・
定期昇給原資即ち査定替え実施に伴う所要財源は、あらゆる条件が正常である場合には、労働者の新陳代謝に伴う賃金の差額がこれに充てられ、人件費は増大もせず減少もしない。このことはしばしばエスカレーターの比喩をもって説明されているが、この場合はエスカレーターの自動運転を企業内労働者の新陳代謝に又エスカレーターの傾斜を基準線にたとえたのであって、個々の労働者はエスカレーターの各段階、即ち基準線の一定の所に位置し、年々職務遂行能力の上昇によって、段階を昇って行くが、最上段の労働者が企業外へ離職して行き、新たにその代りに最下段に新しい労働者が入り、エスカレーター全体いわば人件費総額は内転して常に一定であることを示している。
労働組合の激しいベースアップ攻勢に苦しんでいた当時の経営者側が、何とかしようとひねり出したこの絶妙のアイディアは、しかしながらそれから40年間実現することはなかった。労働組合側は当然の権利としての定期昇給に加えて毎年高率のベースアップを要求し、実現させてきたからである。ベースアップとは、内転するエスカレーター自体をクレーン車でもってぐいっと上に引き上げるものである。これにより、日本の労働者の賃金は個人的に定期昇給するだけではなく、それ以上に毎年ベースアップにより全体として上昇していき、それらを全部足し上げたマクロ経済的な真水の賃上げ部分として、日本人の賃金水準自体を右肩上がりに引き上げてきた。それを、関経協/日経連の「昇給・ベースアップ実施状況調査」でみると、図2のようになる。
図2 定期昇給率とベースアップ率の推移
ところが1990年代以降、「ベアゼロと定昇堅持の時代」に突入すると、このエスカレーターは空間上の同じ位置でただぐるぐると回るだけになってしまった。エスカレーターに乗っている個々の労働者(正社員)の目には、自分の賃金が毎年上がっているように見えても、 全体では全然上がっていないという、手品の仕掛けはまさにここにあった。
この事態をいささか風刺的に表現してみるとするならば、「上げなくても上がるから上げないので上がらない賃金」ということになるであろう。
「上げなくても」:ベースアップという形で無理やりにでも賃金総額を引き上げるということをしなくても、
「上がるから」:定期昇給という形で毎年正社員一人ひとりの賃金は上がっていくものだから、
「上げないので」:わざわざ苦労してベースアップして賃金を引き上げるということをしなくなってしまったので、
「上がらない」:結果として日本人全体の賃金水準は全然上がらないままになってしまった、
というわけである。
逆に、日本以外の諸国がなぜこの三〇年間着実に賃金が上がってきたかといえば、無理やりにでも賃金を引き上げてきたからだ。ジョブ型社会では賃金は職務にくっついていて、人にくっついていない。従って、職務を変えない限り、原則として賃金は上がらない。日本のような定期昇給という仕組みはない。ほうっておいても賃金が上がる日本とは対照的に、ほうっておいたらいつまで経っても賃金は上がらないのがジョブ型社会である。そこで、職務に貼りつけられた値札をみんなで一斉に書き換える運動をせざるを得なくなる。それがジョブ型社会の団体交渉であり、その結果の改定価格表が労働協約ということになる。この事態をやはりいささか風刺的に表現してみると、「上げなければ上がらないから上げるので上がる賃金」ということになろうか。
「上げなければ」:団体交渉による値札の書き換えをしなければ、
「上がらないから」:職務に貼りつけられた値札の額はいつまで経っても上がらないから、
「上げるので」:みんなで団結して団体交渉をして無理やりにでも値札を書き換えるので、
「上がる」:結果として一国全体の賃金水準が上がっていった、
というわけである。
さて、「ベアゼロと定昇堅持の時代」の後半期になって、日本の賃金には公的な引上げメカニズムが組み込まれた。2007年の第1次安倍内閣時代から、政権交代やさまざまな外的なショックにもかかわらず継続されてきた地域最低賃金の高率の引上げ政策である。全国加重平均で見ると、2006年の673円から18年後の2024年に1055円へ57%の上昇、最高の東京都では2006年の719円から1163円へ62%の上昇である。しかし政府はさらなる引上げを目指しており、石破茂首相は就任記者会見で2020年代に全国加重平均1500円を目指すと述べた。
最低賃金については近年世界的に関心が高まっており、EU(欧州連合)でも2022年10月19日に「欧州連合における十分な最低賃金に関する欧州議会と理事会の指令」(最低賃金指令)が成立し、去る2024年11月15日から国内法化されている。同指令は法定最低賃金の決定基準のうち、その十分性の基準として賃金の総中央値の60%、賃金の総平均値の50%といった具体的な数値が含まれている(指令第5条第4項)。筆者は、岸田内閣時の2023年9月4日に、労働組合ナショナルセンターの連合に呼ばれて、この最低賃金指令についてお話をした。連合幹部の問題意識は法定最低賃金を決定する際の基準にあったようだが、筆者が力説したのは別のことであった。
このEU指令には、法定最低賃金の基準についての細かな規定の前に、第4条として「賃金決定に関する団体交渉の促進」という規定が置かれている。筆者が連合にしっかり認識してほしかったのは、むしろこちらである。同条は、とりわけ産業別又は産業横断レベルにおいて賃金決定に関する団体交渉を促進することを求めた上で、その第2項で「団体交渉の適用率が80%未満である各加盟国は、労使団体に協議した後に法により又は労使団体との合意により、団体交渉の条件を容易にする枠組みを導入するものとする。これら加盟国はまた団体交渉を促進する行動計画を策定するものとする。・・・行動計画は、労使団体の自治を最大限に尊重しつつ、団体交渉の適用率を段階的に引き上げる明確な日程表と具体的な措置を規定するものとする。・・・」と、団体交渉の適用拡大に向けた行動計画の策定を求めている。
最低賃金指令の中になぜこんな規定が入り込んできたのかというと、スウェーデンやデンマークといった北欧諸国がEUレベルで最低賃金指令を設けることに猛反発したからである。猛反発したのは北欧諸国の労働組合である。北欧諸国には法定最低賃金などというものはない。組織率80%を超える労働組合が自らの力で賃金を支えているからだ。彼らにとっては、国家権力の力を借りなければ賃金を支えられないなどというのは労働組合としては恥ずかしいことなのである。
その気概を示したのが、イーロン・マスク率いるテスラ社のスウェーデン工場で2023年11月、金属労組IFメタルが労働協約締結を拒否する同社に対して行ったストライキに、港湾労働者や郵便労働者などが同情スト(テスラ車だけ荷下ろし拒否、テスラ車のナンバープレートだけ配達拒否など)で協力したことである。この争議はまだ続いているが、公共性とは国家権力への依存ではなく、産業横断的な連帯にあるという北欧労働者の心意気が示された事件である。
もちろんこんなことができるのは組織率の高い北欧諸国くらいであって、近年組織率が急減してきたドイツも、2014年の協約自治強化法によって、それまでなかった法定最低賃金の導入に踏み切っている。EUで最低賃金指令が作られたのもヨーロッパ全体で労働組合の力が弱まってきているからだろう。しかし、それは本来あるべき姿ではなく、賃金は労使間の団体交渉で決められるべきものだという理念を、わざわざ最低賃金指令の冒頭に書き込むことによって、その本来あるべき力量を維持している北欧諸国の労働組合の反発をなだめようとした、というのが、この規定が盛り込まれた経緯なのである。
産業横断的な連帯どころか、企業を超えた産業別の連帯すら極めて希薄な日本では、直ちにその真似をできるはずもないが、とはいえ政府主導の法定最低賃金引上げを囃し立てるだけではなく、労働協約によって賃金を支えていくという考え方に立って、たとえば産業別・職業別の特定最低賃金をもっと容易に導入できるような制度改正を提起していくことも考えていいのではなかろうか。賃金は本来労使関係論の中核事項なのである。