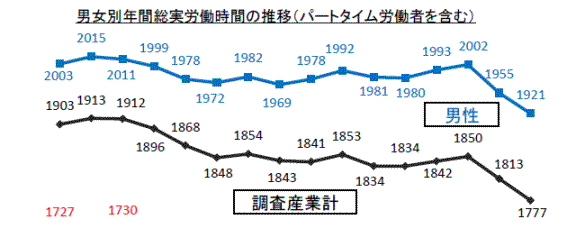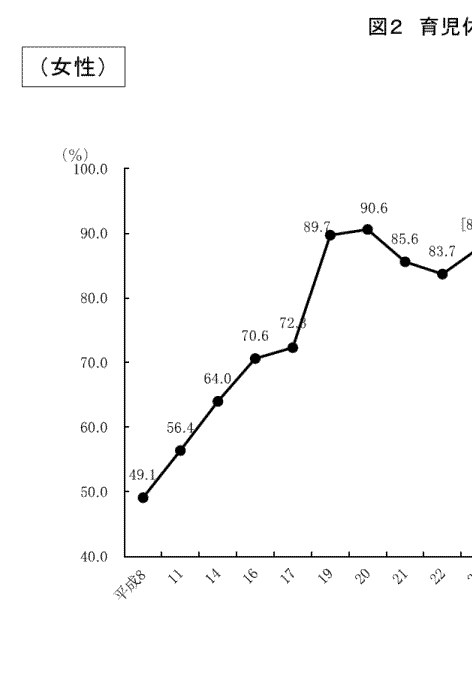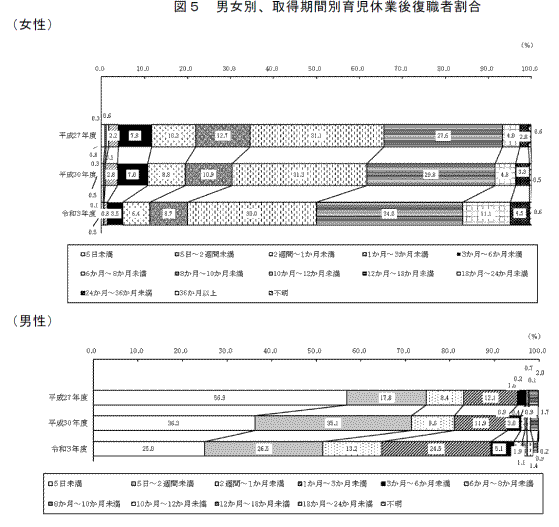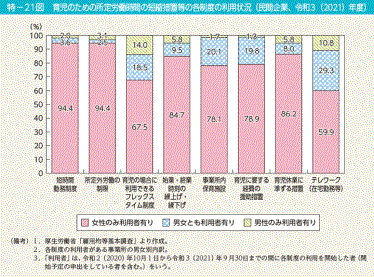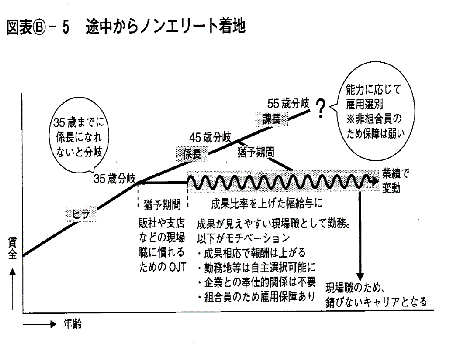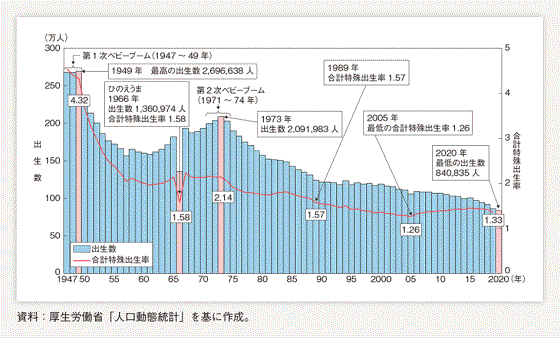特集I:第28回厚生政策セミナー「時間と少子化」
【報告4】
子育て世代の労働時間と労働法政策
濱口 桂一郎*1)
・司会: それでは続きまして、『子育て世代の労働時間と労働法政策』と題しまして、独立行政法人労働政策研究・研修機構労働政策研究所長 濱口桂一郎様よりご発表をいただきます。濱口様、よろしくお願い致します。
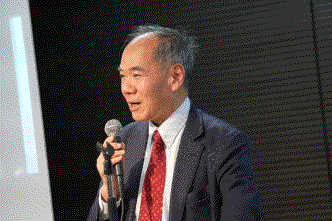
・濱口氏: はい、ご紹介いただきました労働政策研究・研修機構(JILPT)の濱口でございます。JILPTというのは、社人研と同じく厚生労働省関係の研究機関なのですが、社人研が厚生系であるのに対して、私のところは労働系ということになります。大石さんは労働経済学者でもありますので、そういう意味ではその話の続きということになりますが、私からはこのタイトルにあるように労働法政策・法制度のあり方に注目します。ただし法制度を解説することはいくらでもできるのですが、それを説明しただけではなぜ現実がこうなっているかということは全然わかりません。法制度はこういうふうになっているのだけれども実態はこうなっているのはなぜか、というところが実は大きな問題であります。時間が乏しいのできちんとした説明はできないかと思いますが、雇用システムという問題があるということを踏まえながらお話をできればと思っております。
まず日本の労働時間に関わる法律はどうなっているか。終戦直後に労働基準法という法律ができまして、一日8時間、週48時間という法定労働時間になりました。普通労働時間の上限と言われていますが、実は上限ではないんです。なぜ上限ではないかというと、法律ができたとき、成人男性については、残業代を払えば無制限の時間外・休日労働ができたからです。そして、ごく最近までそうだったんですね。ただ女性についてはそうではありませんでした。かつては女性については一日2時間、週6時間、そして年間150時間という上限がありました。だから例えば5時に仕事が終わったら7時までは残っていいけれども、8時に残っていたらそれだけでアウトなのです。そういう時代があったんです。いつまであったかというと、実は1997年の均等法改正までなんですね。え、と思うかもしれません。ある意味すごい男女差別とも言えるかもしれませんが、どちらが差別されているのかよくわかりません。少なくともこういう制度の背景にあったのは、パンを稼ぐのは成人男性で、だから無制限に働いていいんだ。だけど女性はケアラーであるから家庭が大事で、だからいつまでも会社に留めちゃいかんのだと。こういう考え方だったんでしょうね。この考え方は20世紀を通じて社会的にはずっと維持されていました。
その証拠に、1980年代に時短というのが流行語になったんですが、その頃の時短とはなにかというと、長時間労働が悪いから短くしましょうなんて話ではないんです。貿易摩擦で、欧米から日本はウサギ小屋で働きすぎだからけしからんと言われ、働くのはどこが悪いんだと内心思いながら、まあ言われているからしょうがないと言ってやったんです。何をやったかというと、法定労働時間を48時間から40時間に短縮しました。ただその時に時間外労働には手をつけませんでした。時間外労働というのは、日本の雇用を安定化させるために非常に重要なものだから、そんなものを制限してはいけないのだというのが基本的な考え方で、ほんの数年前までこの考え方はずっと維持されていました。
一方、これは世界的に共通なのですが、20世紀の後半に男女平等の考え方がだんだん広まってきました。日本も、国連の女性差別撤廃条約を批准しなければいけないということで、男女雇用機会均等法ができました。これで何が起こったかというと、男性も女性並みに時間外労働に上限を設けようなんて、そんなことはごく一部の人間を除けば誰も言わない。女性も男性と同じように無制限に働けるようにしようということになりました。ずっとそういうふうになってきたんですね。ようやく2018年に、これはまだほんの数年前ですが、働き方改革で月間80時間から100時間という時間外・休日労働の上限規制がされました。これは確かに意味のある規制ですが、この基準というのは実は労災の認定基準です。ここまで働いて死んだら労災だよという基準です。
そのおかげで確かに年間総実労働時間数は、この2019年から少し下がりつつあるんですが、基本的にあまり変わっていません。右側のグラフは週60時間以上働いている人の割合なんですが、これが実に男性の場合十数パーセントもあるんですね。60時間ということは週あたり20時間余計に働いているわけです。月当たりにすると80時間以上ですから、実はこれは労災認定基準超えになっている。もし倒れたら労災が認定されるような人たちが、これだけ日本にいるという話なんですね。これが労働時間の現状です。
次に育児休業法制という、いわゆるワークライフバランスの関係について見ていきます。日本で育児休業法ができたのは今から30年以上前の1989年です。これはいわゆる1.57ショックという、合計特殊出生率の低下に対して、なんとかしろという政治的要請を受けて育児休業法という立派な法律ができました。法律を読むと立派なんですよ。男女双方に一年間の育児休業の権利があるんです。さらにこの後お話をしますが、実は六法全書に載っている今の育児介護休業法をみると、先ほど大石さんが言われたように、短時間勤務など、世界的に見てもこんな立派な法律はないぐらい充実しております。が、実態から言うとほとんど女性のための制度なんです。
厚生労働省は、いやそんなことはない、我々の鉦や太鼓のおかげで男性の育児休業取得率がものすごく伸びてもう17%になっている、素晴らしいでしょうと言うわけですね。これだけ聞くと素晴らしいように聞こえるんですが、はっきり言ってこれは大本営発表です。左側のグラフは、育児休業を何%取っているのかというデータです。しかし、何%取っているといっても、どれくらいの期間取っているのというと、女性はだいたい1年前後が一番多いです。これに対して男性は下のグラフの白い部分で、実は一番多いのは5日未満なんですよ。さすがに一番最近の令和3年度では5日未満よりも5日から10日の方が若干多くなったんですが、両方合わせるともう半分以上ですね。私はこれを育児休業と呼びたくないです、あえて言えば育児休暇です。何が違うかと思うかもしれませんが、「あ、なんか濱口君、ちょっと休んでるな」と思ったらまた復帰してきたというようなものですから。介護の話とは違うんですね。育児というのは、親が子どもの世話をするためのペアレンタルリーブですから、5日や10日で何がペアレンタルだという感じなのですが。しかしそれで17%だと厚生労働省は言っております。
それから、現在の育児介護休業法には実に様々な制度があります。深夜業の免除請求権、一定の時間外労働の免除請求権、短時間勤務の措置義務、所定外労働の免除請求権、子の看護休暇の請求権、その他フレックスタイム、時差出勤、託児所の設置運営等々。さらに今審議会で議論していて、おそらく来年の国会に出される法案では、テレワークというのも選択的な措置義務に入ってくると思われます。
問題はこれらも基本的には女性のための制度になってしまっているということです。グラフのグレーの部分は女性のみが使っている制度です。フレックスタイムやテレワークなど一部の制度を除くと、ほとんど女性専用の制度になっているということがわかります。これが実態なんですね。
ここまでは制度の説明です。だけどなぜこんなに立派な制度がこういう実態になるのかというと、戦後に形成された日本型雇用システムが非常に大きな影響を与えているだろうと思っています。これを説明しはじめると1時間でも2時間でもかかるんですが、今日のお話と最も関係のあることを言うと、戦前の日本の方がむしろ欧米社会に近かったということです。戦後日本は、エリートとノンエリートを入り口で区別しないで、ラットレースよろしくバリバリ無制限に働かせて、それで勝ち残った人、よく頑張った人が上に上がっていく、こういう社会を作ってきました。それが良いか、悪いかという話はとりあえずしません。戦後日本人は、それは大変良い社会だ、入口であいつはエリート、ノンエリートというふうに区別される階級社会ではなくて、みんなが社長になれる可能性がある。係員島耕作たちが、みんな社長島耕作を夢見て一生懸命頑張る、素晴らしい社会じゃないかというふうに思ってきたわけです。それは確かにある面でそうなんですが、裏返して言うと、頑張ることができる者だけの平等なんですね。ガンバリズムの平等主義というのは、頑張れる人だけが平等になるということです。
かつて均等法以前の日本社会は、男性と女性は別のカテゴリーに属してきました。男はサラリーマンで女はOLと言って、カテゴリカルに違っていたわけです。OLというのは基本的に結婚退職前提で、補助的な業務に従事し、結婚したら辞める。そうすると夫は奥さん、子どもたちのためにワークに専念する、奥さんはライフに専念する。これぞ日本的な素晴らしいワークライフバランスじゃないかというふうに思っていた。当時そんな言葉はないですが、たぶん当時の人たちはそういうふうに思っていたのだろうと思います。ところがそこに均等法がやってきて、女性も男性並みにきちんと処遇しろ、処遇する以上は女性も男性並みに働けと。男性並みというのは、エリート候補生だけどもエリートになれる保証は何もない若者たちが、とにかく無制限にあれもやれこれもやれと言われて、はいわかりました頑張りますと言って、時々失敗をするけれども頑張って一生懸命やっていく。その中に若い女性も一緒に入れましょうと、こんなやり方をしたわけです。そんなやり方には、未婚の女性はなんとかついていけるかもしれませんが、子どもを抱えてしまった女性がこれについていけるかというと、そんなはずありません。なぜなら、かつてのサラリーマンは自宅に銃後の妻がいましたが、子どもを抱えた女性たちが、銃後の妻も一緒にやりながら、一生懸命前線で戦う、そんなバカなことができるはずがありません。
もちろん先ほども言ったように育児介護休業法というのは大変立派な法律です。短時間勤務をはじめとして様々な両立支援のための制度が用意されています。ところが、短時間勤務は権利ではあるのですが、短時間勤務の時だけ短時間勤務なんです。同語反復じゃないかと思うかも知れませんが、短時間勤務は当然期限があるんですね。短時間勤務が終わったらどうなるか?パートタイムが終わったらフルタイムに戻るというのが、たぶん世界の常識だと思うんですが、日本のサラリーマン社会はそうではありません。ある方は私にこう言いました。「濱口さん、パートタイムが終わったらフルタイムに戻ると思っていたらそうじゃなかったんです。オーバータイムが待っていました」。幼児を抱えてオーバータイムというのはなかなかきつい。だけど若い男性たちが頑張っているその横で若い女性たちも同じように頑張る。そんな状況を目の当たりにしていて結婚できるか、子どもはできるか、こういう話であります。一方で先ほどのように、働き方改革で月80から100時間という上限規制ができましたけれども、これは過労死認定基準です。命のワークライフバランスであって生活のワークライフバランスではないのです。
このワークライフバランスという言葉ももう一遍考えてみたいと思います。実は、日本は育児介護休業法に書いてある、いわゆるワークライフバランス法制というのは本当に充実しています。立派なんですよ。だけどそこに書いていないことが大事なんです。何かっていうと、そもそも育児介護休業法というのは例外なんです。では、育児介護休業法という例外が前提にしているのは何かというと、それは労働基準法の労働時間規制のはずなんです。これがもしきちっとしていれば、一日8時間、週40時間というのが本当に上限であるならば、例えば子どもに朝ごはんを作ってから会社に向かう。家に帰ってから子どもに夕食を作ってあげるということがなんとかギリギリできるでしょう。労働時間は柔軟性が大事だと言うんですが、実はその前の段階があります。労働時間はむしろ硬直的である方がワークライフバランスを守るんです。
ただそれだけでは足りません。これが先ほど大石さんが言われた、子どもを育てるというのはそんなに規則的なものじゃないということです。1日8時間、週40時間という規制だけでやっていたらそれでは及ばないことがあるでしょう。例えば朝は子どもを保育所に預けに行くために同僚よりも遅く出勤できることが必要でしょうし、夕方は子どもを引き取りに行くために早く退勤できることが必要でしょう。あるいは子どもが病気になれば病院に一緒に連れていくとか、子どもを育てているといろんなことがあるので、こういった柔軟性は必要です。
日本はこの10年、20年ぐらいフレキシビリティ、柔軟性という言葉が若干混乱してきたのではないかと感じています。今でも覚えていますが、今から十数年前に、ちょうど裁量労働制とかホワイトカラーエグゼンプションの議論があった時に、当時政府の規制改革会議は何と言ったかというと、このホワイトカラーエグゼンプションを導入することによって仕事と子育てが両立できるようになる、少子化対策になるのだというふうに言っていました。これは全くの嘘ではないです。確かに労働時間は柔軟であることがワークライフバランスにプラスになることがあります。しかし、そもそもの根っこで、無制限に働くことがデフォルトルールになっている中で、そこだけ柔軟性ということを言ってしまうと、時間に糸目なくいくらでも働く方向にのみ、フレキシビリティというのは働いてしまう。そこのところの議論というのがどうも日本ではすっぽり抜けているなという感じがしました。
ではなぜそうなるかというと、ここが最初に申し上げた、日本の法制度を社会的に支えていると同時にそれを制約している雇用システムのあり方だろうというふうに思います。この育児介護休業法にあるような、第二次的なワークライフバランスはEUに遜色ないぐらい充実しているのに、育休世代は非常に疲弊していく。なぜか?その基盤となるべき第一次ワークライフバランスが空洞化しているからだろうと思うわけです。短時間勤務中はいいけれども、それが終わると労働時間無制限の男性正社員ルールというのがかぶさってくる。ですから女性の問題と思われていることは、実は男性の問題なのです。そして、女性の働き方をどんなに弄っても男性正社員の無制限な働き方が変わらない限り、女性活躍というのは絵に描いた餅になってしまうだろうと思います。
この問題が難しいのは、これは社会的にマイナスなだけではなく、むしろ戦後日本社会にとってはバリバリ頑張れば頑張るほどいくらでも出世することが可能だという、「青空の見える人事」という言葉も昔あったんですが、いわばメリットのあるものとして展開してきたがゆえに、なかなかそこから脱却することが難しいということがあるんですね。今から数年前に限定正社員という言葉が流行ったことがありますが、その時も、それいいねというよりも、なんだその変なものはという批判の方が強かった。限定正社員ってなんだと。俺たちのことを限定しようというのかと。無限定であることがデフォルトであるということが心に染み付いているがゆえに、それを限定するというのは、お前はエリートにならない一格落ちの人間にするんだぞ、みたいな感じになってしまう。ガンバリズムの平等主義からいかに脱却するかというのが、労働時間に関わる少子化問題というものの大きな鍵になるんじゃないかなと思います。
ここまでが本論ですが、先ほど岩澤さんがミクロな時間とともにマクロなライフスパンの時間の話をされたので、その関係で人生コースという観点からの話もしてみたいと思います。海老原嗣生さんという雇用ジャーナリストがいますが、彼が日本の雇用のいろんな問題を解決するための処方箋として、途中からノンエリートという道を作ったらどうかということを、『雇用の常識」という本の中で提示しています。若いうちの、日本社会における入り口は変えない。入り口から変えるとなったら教育制度から何から全部変えないといけない、そんなことはできない。だから会社に入ってから10年ちょっとは今までと同じようにバリバリやる。だけどずっとそういうわけにはいかないので、だいたい35歳ぐらいで、社長島耕作を目指すラットレースから降りる。これでいいじゃないかというふうに彼は言うわけです。
だけどこの議論は男性の若者や、男性の中高年を前提とした議論なんですね。確かに男性の若者、男性の中高年を前提とした議論であれば、これはなかなかリアルな解であることは間違いないのですが、ここに女性という変数を入れて三元連立方程式として解こうとすると、一体何をもたらすかというと、女性に高齢出産を要求するという解になります。35歳まで女性も男性並みに無限定正社員としてバリバリ働けと。だけどずっとそうではなくて、その後はそこから降りて行っていいですよと。そこで海老原さんはこの『女子のキャリア」という10年ちょっと前に出た本のなかで、医学的にどこまで本当かよくわからないですけど、医学的なデータをいろいろ駆使して、高齢出産はなにも悪いことではない、30代あるいは40代になってもいくらでも子どもを産んでいいじゃないかということを縷々この本で書いているんです。
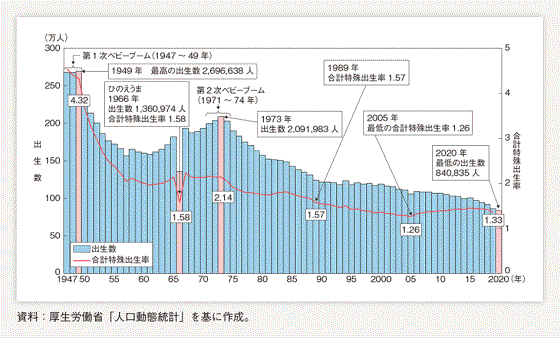
これに対して私は本当にそうなのかなというふうに思っています。今から7、8年前の2015年に『働く女子の運命」という本を出しましたが、その中で、本当にそれでいいんだろうか? 35歳で分岐してその後高齢出産という、一見合理的に見える解で本当に社会は回っていくんだろうか?と問題提起をしました。雇用システムのあり方として、若いうちは男女ともにバリバリ働いて、あるところに行ったらそこから降りる人はみんな降りてねというやり方で、そのツケは女性が高齢出産することでなんとか行くでしょう、高齢出産にはなにも悪いことはないよと言うんだけども。だけど人間だって生き物です。生き物であるということをそんなに無視していいのだろうか。そうやって雇用システムのあり方と妥協をさせながら女性を高齢出産に導いていって、そのツケを不妊治療でもって賄うような社会のあり方が本当にいいのかということについては、もうちょっと考えた方がいいんじゃないですか?ということをこの本の最後のところで投げかけました。これは投げかけたということです。つまり私にも答えはないんです。これはすごく難しい問題で、きれいな答えがあればいいんですが、きれいな答えはないです。日本の雇用のあり方に問題があるというふうに分析することは可能です。ただだからといって、日本の雇用はおかしいから全部入り口からひっくり返してしまえと、一介の評論家だったらできるかもしれませんが、ある程度政策に責任がある人間はそんなこと怖くて言えるはずがありません。つまりこれは非常に難しい問題で、真面目に考えれば考えるほどきちんとした解がないということになってしまう。とりわけマクロな人生コースという観点からの時間と少子化という観点からすると、ここに実は一番大きな問題をはらんでいるのではないかと思います。私からの話は以上です、ありがとうございました。
*1) 独立行政法人労働政策研究・研修機構
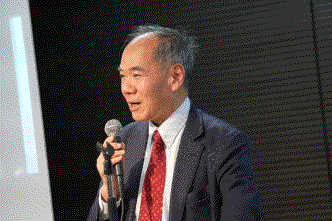 ・濱口氏: はい、ご紹介いただきました労働政策研究・研修機構(JILPT)の濱口でございます。JILPTというのは、社人研と同じく厚生労働省関係の研究機関なのですが、社人研が厚生系であるのに対して、私のところは労働系ということになります。大石さんは労働経済学者でもありますので、そういう意味ではその話の続きということになりますが、私からはこのタイトルにあるように労働法政策・法制度のあり方に注目します。ただし法制度を解説することはいくらでもできるのですが、それを説明しただけではなぜ現実がこうなっているかということは全然わかりません。法制度はこういうふうになっているのだけれども実態はこうなっているのはなぜか、というところが実は大きな問題であります。時間が乏しいのできちんとした説明はできないかと思いますが、雇用システムという問題があるということを踏まえながらお話をできればと思っております。
・濱口氏: はい、ご紹介いただきました労働政策研究・研修機構(JILPT)の濱口でございます。JILPTというのは、社人研と同じく厚生労働省関係の研究機関なのですが、社人研が厚生系であるのに対して、私のところは労働系ということになります。大石さんは労働経済学者でもありますので、そういう意味ではその話の続きということになりますが、私からはこのタイトルにあるように労働法政策・法制度のあり方に注目します。ただし法制度を解説することはいくらでもできるのですが、それを説明しただけではなぜ現実がこうなっているかということは全然わかりません。法制度はこういうふうになっているのだけれども実態はこうなっているのはなぜか、というところが実は大きな問題であります。時間が乏しいのできちんとした説明はできないかと思いますが、雇用システムという問題があるということを踏まえながらお話をできればと思っております。