�w�G���J���@�x2022�N�~��(279��)
�u�J���@�̗��@�w�v��66��
�u�i�����w�Z�j���t�̘J���@����v
�@
�͂��߂�
�@
�@���߂ɒf�蕶��L���Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂��A���{���ɂ͋��t�Ƃ����E��ɒ��ڂ������ʂ̘J���@����͂قƂ�Ǒ��݂��܂���B���̂悤�Ȃ��̂����݂���Ƃ����v�����݂́A�������ܒn�قⓌ�����ق̍ٔ����̔]���ɂ��Z���ɕY���Ă���悤�ł����A����͂����Ȃ����@��̍������L���Ă��܂���B�������Љ�w�I�ɂ́A���t�͈�t�ƕ���ň�ʓI�Ɂu�搶�v�ƌĂ�鑸�h���ׂ����x���E�Ƃ݂Ȃ���A�ꍇ�ɂ���Ắu���E�v�ƌĂ�邱�Ƃ�����܂����A����ɑΉ�����悤�Ȏ���@��̓��ʈ����͑��݂��Ȃ��̂ł��B
�@�ɂ��ւ�炸�A���t�͓��ʂȐE��ł��邩��J���@��̓��ʂȈ��������݂���Ƃ����v�����݂�����@�Ɋ�Â��Ĕ����������ׂ��ٔ��������ɂ��o�����Ă����̂ɂ͗��R������܂��B���݂��Ȃ��w�Z���t�̑命�����߂�����w�Z�̋��t�͒n���������Ƃ����g����L���Ă���A���̒n����������������w�Z���t�Ƃ�������̖@�I�n�ʂ�L���鋳�t�ɂ��Ă̂݁A�n���������@���o�R�����J���@�̓��ʈ��������݂��Ă��邩��ł��B���̓��ʈ����́A������g����L���Ȃ������w�Z�⍑���w�Z�̋��t�ɂ͑S���K�p����Ȃ����̂ł���ȏ�A����͂����Ȃ�Ӗ��ł��E��Ƃ��Ă̋��t�ɒ��ڂ������̂ł͂��肦�܂��A�����̑��݂�]���ŏ������Ă��܂����Ƃɂ���āA�n���������Ƃ����g���ɒ��ڂ������ʈ����|�����@�|���A�����������t�Ƃ����E��ɒ��ڂ����J���@�ł��邩�̂悤�Ɍ�F���Ă��܂��҂��₦�Ȃ��̂ł��傤�B
�@�{�e�ł́A����������F�ݏo�����ƂȂ��Ă��鋋���@�|�����_�ɂ����鐳�����̂́u�����̋`�����珔�w�Z���̋���E���̋��^���Ɋւ�����ʑ[�u�@�v�|���߂���@����̐��ڂ��A����ɐ旧�����ɑk���ĊT�ς��Ă��������Ǝv���܂��B�b����₱�����̂́A�����@��1971�N5���ɐ��肳�ꂽ�Ƃ��ɂ́u�����y�ь����̋`�����珔�w�Z���̋���E���̋��^���Ɋւ�����ʑ[�u�@�v�ł���A(�J����@���܂������K�p����Ȃ�)�����w�Z�̋��t�ɌW��K�肪���C���ŁA(�J����@�������K�p�����)�����w�Z�̋��t�͂��ꂪ���p�����ɉ߂��Ȃ������̂ɁA2004�N�x���獑����w�@�l�����Ė��Ԑl�ƂȂ����O�҂��K�p�Ώۂ���O�ꂽ���߁A��҂������K�p�ΏۂƂȂ������Ƃł��B���̂��Ƃ��A�����@���߂������Ȃ˂���ݏo���Ă��܂��B
�@
�P�@�J����@�������̌o��
�@
�@�J����@��1947�N3���ɐ������܂������A��O�̍H��@���ƈقȂ�A�������킸�A�S�Ă̋Ǝ�A�S�Ă̐E��A�S�Ă̋K�͂̎��ƂɓK�p������ʓI�J���������@�Ƃ��Đ��ݏo����܂����B���������̐���ߒ��ɂ����ẮA�����Ȃ���٘_����N����Ă����悤�ł��B
�@�����̌����ȘJ���ǘJ���ی�ۂ��J��Ԃ��쐬�����@�Ăɂ́A���t�Ƃ����E��ɒ��ڂ������ʈ����̋K��͈�؊܂܂�Ă͂��܂���ł������A1946�N9��11���t�ŕ�����b���[�����ے���������ȘJ���ǒ����ɏo���ꂽ�u�J����@���Ăɂ��āv�́A���̂悤�ɓK�p���O�����߂Ă��܂���*1�B
�@�{��3���M�Ȃɉ��ĘJ����@���Ăɂ��ĊW�e�Ȃ̑ō���J�Â̍ہA�{�ȌW������\�o��v���܂����ӌ������L�̒ʂ蕶�����ȂĂ��͂��v���܂��B
�L
�@�J����@���Ē����̂₤�ɏC��������Ђ��܂��B
��A�掵���\�u����A�������͒����̎��Ɓv�̉��Ɏ��̂₤�ɉ��ւ�B
�@�u�i���E���������j�v
���R�@����A�������͒����̎��Ƃɏ]������҂̒����E���͘J���������̑��ɂ��Ď��I�ɖ{�@�Ɉ˂�J���Ƒ��Ⴗ��_�����邩�炱���̎��Ƃɏ]�����鋳�E���͊����Ɠ��l�ɖ{�@�̎�|�ɏ����ĕʓr�ی�A�ۏ�̑[�u���l������������ł���B
�@�u���I�ɖ{�@�Ɉ˂�J���Ƒ��Ⴗ��v�Ƃ����咣�̒��g���s���ł����i���E���ł����Ȃ���A����A�����A�����ɏ]�����Ă����I�ɑ��Ⴗ�邱�Ƃ͂Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA���Ȃ��Ƃ��E��ɒ��ڂ��Ă���̂ł͂Ȃ������ł��B�j�A���Ȃ����ǂ��鋳�E���ɑ��Ă͘J���@�̉�����������Ă������Ƃ����͂悭�`����Ă��܂��B�������Ȃ��炱�̂悤�Ȉӌ����e����邱�Ƃ͂Ȃ��A���E�����܂ދ���A�������͒����̎��Ƃ͘J����@���t���ɓK�p�����Ǝ�Ƃ��č����܂ő����Ă��܂��B
�@�J����@�̓K�p�͈͂��ς�����̂́A���������Ǝ��E��Ƃ͕ʂ̎����ŁA��������̉ߌ��ȘJ���^���ɋƂ��ς₵���}�b�J�[�T�[�����̂�����u�}�b�J�[�T�[���ȁv�Ɋ�Â�1948�N11���̍��ƌ������@�����ɂ��A�J���g���@�ƘJ���W�����@�ɉ����ĘJ����@�܂őS�ʓK�p���O�ƂȂ��Ă��܂������Ƃɂ��܂��B�������ɂ�����W�c�I�J�g�W�V�X�e����ύX����Ƃ����ړI���炷��ƁA���̘J����@�S�ʓK�p���O�͂ǂ��܂Ő����������������^�킵�����̂ł����A70�N�ȏ�ɂ킽���Ĉێ����ꑱ���Ă��܂��B
�@�������A1950�N12���ɐ��������n���������@�ł́A������ÂɂȂ��ċK��̎d�������Ȃ���A�J���g���@�ƘJ���W�����@�͑S�ʓK�p���O�ł����A�J����@�ɂ��Ă͌����K�p�A�����I�ɕs�K�p�Ƃ����`�ɂȂ�܂����B�����ŁA����E�����E�����ȊO�̌��ƐE���i�����a�@�Ȃǁj�ɂ��ẮA�J�g�Γ�����̌����i��2���j�y�яA�ƋK���̋K��i��89-93���j���������ׂēK�p�����̂ɑ��āA���`�̔ƐE���i�J����@����8���16���́u�O�e���ɊY�����Ȃ��������v�j�y�ы���E�����E�����ɏ]������E���ɂ��ẮA��̓�ɉ����āA�J����ē@�ւ̐E����l���ψ���͂��̈ψ��i�l���ψ���̂Ȃ��n�������c�̂ł͒n�������c�̂̒��j���s���Ƃ����K��i�n���������@��58���3���j�������A�J����@�̘J�Е⏞�̐R���Ɋւ���K��y�юi�@�x�@�����̋K�肪�K�p���O�Ƃ���܂����B�l���ψ���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����Ŏ������ē���Ƃ����J����ēV�X�e���Ƃ��Ă͂����ɂ���Ȑ��x�ł����A����������܂łȂ�̕ω����Ȃ��ێ�����Ă��܂��B
�@���Ȃ݂ɁA1946�N9���ɐ��肳�ꂽ�J���W�����@�̗��@�ߒ��ɂ����Ă��A���N5���̘J���@���R�c��\���o�Ė@�Ă��쐬����A���������ɒ�o���钼�O�̊t�c�ŁA�c���k���Y�����̋����咣�ɂ��A�������y�ю����w�Z�̍Z���y�ы����̑��c�s�ׂ��֎~�����Ƃ����C������������Ƃ����A�N�V�f���g������܂������AGHQ���u���������c�s�ׂ����Ă��A�����ɍ��Ƃ������͂Ȃ��v�Ƃ��āA�����P����Ƃ����h�^�o�^�����������Ă��܂��B����W�҂ɍ������u���t�͘J���҂ɔv�_����������ے肳�ꂽ�킯�ł����A���̌�����݂Ɏ���܂Ŏ����w�Z�����̑��c�����ے肳�ꂽ���Ƃ͈�x������܂���B
�@�Ȃ��A����ƈ�ÂƂ���2����ɂ��ẮA�J�������@���i�J����@�j�ɂ����Ă͌��ƂƂ��Ĉ����Ă���̂ɁA�J�g�W�@���i�����@�Ƌ����J�@�j�ɂ����Ă͔ƈ��������Ƃ����s���������݂��Ă������Ƃ��A���t�ɌW��J���@����̘c�݂������炵���傫�Ȍ����ł��B����́A���Ԃɂ������w�Z�⎄���a�@�����݂��A�������w�Z�⍑�����a�@�Ƃ܂����������T�[�r�X����Ă���_�ɒ��ڂ��A���Ԏ��Ə������݂����Ȃ��������Ƌ�ʂ��Č��Ƃƈ����J����@�̕��������I�ł���A�c�̌�����F�߂�E��𐭎��I�o�܂���f�ГI��3����5���ƂƂ��Đ�o�����J�g�W�@���̕������_�I�ɂ͂��������̂ł����A���炭�����a�@�⍑���w�Z�͔ƂƂ��Đl���@�̏��ǂƂ���Ă������߁A�l���@���ǂ��܂Ō�����L���邩�ɂ��ĔF���̘c�݂������Ă��܂����悤�Ɏv���܂��B����ł��A��Â̐��E�͈�t�̃v���t�F�b�V���i���Y���ɂ��Ǝ��̐E�Ɛ��E���\�z����A���ꂪ��w�̈�ǂ𒆐S�Ƃ��銯�����ђʂ�����O�I�ȃW���u�^��Ԃ��`�����Ă������߂ɁA�l���@����t�̐E�ƓI��含���]�X����]�n�ȂǂȂ������̂ɑ��A����̐��E�́i��w�����̐��E�͕ʂƂ��āj�����ł͂Ȃ��������߁A���ƌ������@�����ǂ��邾���̐l���@���������������w�Z�̋��t�̐E��Ƃ��Ă̐�含�ɂ��Ă܂Ř_���邱�Ƃ��ł��邩�̂悤�Ȍ�������ݏo����Ă��܂����̂ł��傤�B���̓_���A��ɏq�ׂ鋋���@�̃{�^���̊|���Ⴂ�̂��������̌����ƌ����܂��B
�@�v����ɁA�I�풼��ɍ\�z����A������]�Ȑ܂ŏC�����ꂽ���{���̊�{�I�J���@���ɂ����ẮA���ƌ������Ȃ����n���������Ƃ����g���ɒ��ڂ����K�p���O�͑��݂��܂����A���t�Ƃ����E��ɒ��ڂ������ʈ����͂قƂ�Ǒ��݂��Ȃ��`�ŏo�������̂ł��B�������Ƃ����g����L���Ȃ������w�Z�̋��t�́A���75�N�Ԃɂ킽���Ĉ�x�����t�Ƃ����E��ł��邪�̘̂J���@��̓��ʈ����������Ƃ͂���܂���B���ꂪ�A���{�ɂ����鋳�t�̘J���@����̑匴���ł��B�����Y�ꂽ�c�_�͑S�Ęc���̂ƂȂ炴��܂���B
�@
�Q�@���E���̋��^���߂���o��*2
�@
�@��O�ɂ͍���������߁A���C����߁A�����w�Z�E����ߓ��ɂ���Ċ����y�ёҋ������Ƃ��ꂽ���t�̋��^���@�肳��Ă��܂������A�I�풼�ケ��炪�p�~����A1946�N�̊�����߂��o�āA1948�N3���̐��{�E���̕���Ɋւ���@���ɂ��b�����x������邱�ƂɂȂ�܂����B����́A�Ζ����ԍ��ɉ������Ƃ����ΘJ�̑Ή��Ƃ��Ă̕�̊T�O���m���������̂Ƃ����Ă���A1�T�Ԃ̍S�����Ԃ̒i�K�ɂ���ċ��^�̊����ؑ֗��ɍ���݂��܂������A�����͂��̋Ζ��̓��ꐫ����ꉞ48���Ԉȏ�Ζ�����҂Ƃ��āA�ō�������17���ɐ�ւ����܂����B
�@����ɓ��N5���́u���{�E���̐V���^���{�Ɋւ���@���v�ɂ��A�E���̋��ƍ���ɂ�邢����E�������x���m����*3�A�����ɂ��Ă͈�ʐE������1������������邱�ƂƂȂ�܂������A���̉ߒ��ŁA�V�{��ؑR�c������ȉ�́u����E���ɂ͒��ߋΖ��蓖���x�����Ȃ��v�Ƃ��Ă��܂����B���ɘJ����@���{�s����A����E���ɂ��K�p����Ă���̂ɁA����Ƃ͖�������@������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�����Ȃ́A1949�N2������3���ɂ����āA���̂悤�ȒʒB���A�J����@�̋K��Ɩ�������w�������Ă����܂��B�����Ƃ��A���̎����͏�q�̂悤�Ɍ������ւ̘J����@�̓K�p�ɂ��ėh�ꓮ���Ă��������Ȃ̂ŁA�ŏI�I�Ȍ����_�͂悭�����Ȃ���������Ƃ������Ƃ��ł��܂��B
�������̋Ζ����Ԃɂ��āi���a24�N2��5�����w��46���j
�@���ʐ��{�E���̋Ζ����Ԃ́A���a��\�l�N�������ߑ�ꍆ�ɂ���Ē�߂�ꂽ�̂ŁA�����̋Ζ����Ԃɂ��Ă��A���̎�|�Ɋ�Â��Ă�������{���ׂ��ł��邪�A����̓��ꐫ�ɂ������̋Ζ��ɂ��Ă͈ꗥ�ɓ��ߑ�ꍀ�̋Ζ����ԂɍS������Ƃ��́A�������ċ���̔\���ቺ����������ꍇ�������ƍl������̂ŁA���ɋ����̋Ζ����Ԃɂ��ĕ����ȍ����𐧒肵������A��ʐE���̋Ζ����Ԃ������Ɏ��{�����鎖��ɏƂ炵�A���̉^�p�ɓ������Ă͂����܂ŋ���I���ʂ��グ�A�����̑f���ቺ���������Ȃ��悤���⊶�Ȃ���������ꂽ���B
�@�Ȃ��^�p�ɓ����ẮA���L�̓_���\�������ӂ̏㏈��������悤�O�̂��ߐ\���Y����B
�L
��A�Ζ����Ԉ�T�l�\�����Ԃ̊��U�ɂ���
�@�w�Z�S�̂��ꗥ�ɒ�߂邱�Ƃ�v�����A�����l�ɂ��Ă�����ߓ��邱�ƁB
��A�Ζ��̑ԗl�ɂ���
�@�Ζ��͕K�v�ɉ����K�������w�Z������łȂ��A�w�Z�O�ōs�����邱�ƁB���������������@���\���̋K��ɂ�錤�C�̏ꍇ�͓��R�Ζ��ƌ���ׂ��ł��邱�ƁB�ċG�x�ɓ��̐E���̋Ζ��ɂ��ẮA�����̋���\�������ス���ނ邽�߁A�x�ɂ������A�u�K�y�эZ�O�w�����ɗ��p������悤�w�Z�̒��͓��ɔz�����ׂ��ł��邱�ƁB
�O�A���ߋΖ��ɂ���
(1)�@�Ζ��̑ԗl����X�Ŋw�Z�O�ŋΖ�����ꍇ���͊w�Z�̒����ē��邱�Ƃ͎��ۏ㍢��ł���̂Ō����Ƃ��Ē��ߋΖ��͖����Ȃ����ƁB
(2)�@�������ɂ����Ď��������Ԉȏ�Ζ�����K�v������ꍇ�ɂ͂��̋Ζ��𖽂��邱�Ƃ͂ł��邪���̋Ζ��͌����Ƃ��Ĉ�T�l�\�����Ԃ̋Ζ��Ɋ܂܂����̂Ƃ��ċΖ�����@����������̂Ƃ��邱�ƁB
�l�A�����̋Ζ��̊Ǘ��ɂ���
�@�����̋Ζ��ɂ��Ă��̊Ǘ��͈�ʐ��{�E���̋Ζ����Ԃ������Ɏ��{�����Ă��鎖��Ɋӂ݁A�o�Ε낻�̑��w�O�Ζ��ɑ��鏳�F���ɂ��Ă͓K�X�̕��@�ɂ�萮�������̋Ζ��̎��тm�ɂ��Ă������ƁB
�������̒��ߋΖ��ɂ��āi���a24�N3��19�����w��168���j
�@�����̋Ζ����Ԃɂ��ẮA�ܓ������ȍ�����\�ꍆ�������Ă�����߁A�����t���w��l�\�Z���������Ē��ߋΖ��͌����Ƃ��Ė����Ȃ��|���܂߂Ēʒm���܂������A��O�Ƃ��Ă��̓��Ɋ���U��ꂽ���K�̋Ζ����Ԃ������č��L�̋Ζ����s���K�v������ꍇ�ɂ́A����ߋΖ��Ƃ��Ė����A���{�E���̐V���^���{�Ɋւ���@�����\����̋K��Ɋ�Â��A���ߋΖ��蓖���x�����č����x������܂���^�p�v�̂����܂݂̏�A������ׂ������v�炢���肢�܂��B
�L
��A�h��
��A����
�O�A���w��������
�l�A�g�̌���(�ψ��Ɍ���)
�܁A�w�ʘ_���R��
�@�^�p�v��(��)
�@���̒ʒB���悭�ǂނƁA���w����������w�ʘ_���R���ȂǂƂ������̂����邱�Ƃ��炵�Ă��A��w��������Ƃ��ĔO���ɒu���ď�����Ă���悤�Ȉ�ۂ�����܂��B����Ȃ�A���ݐ��Ɩ��^�ٗʘJ�������K�p����Ă��邱�Ƃ܂���A�u�ꗥ�ɥ���Ζ����ԂɍS������Ƃ��́A�������ċ���̔\���ቺ����������ꍇ�������v�Ƃ����̂�������ʂ�����܂��B����������́A��ɋ����@�̓K�p�ΏۂƂȂ�u�`�����珔�w�Z���v�Ƃ͕ʂ̐��E�̘b�ł��B������ɂ��Ă��A�u���̋Ζ��͌����Ƃ��Ĉ�T�l�\�����Ԃ̋Ζ��Ɋ܂܂����̂Ƃ��ċΖ�����@����������̂Ƃ���v�ȂǂƁA�@���̍������Ȃ��܂���ɘJ�����ԋK���̒e�͉���ʒB���x���Ő}���Ă������ƂɂȂ�A����@����J����@�Ƃ̃o�b�e�B���O�������Ă���͓̂��R�ł����B
�@
�R�@�������Αi��
�@
�@��q�̂悤�ɁA1950�N�n���������@�ɂ��A�n����������������w�Z���t�ɂ͘J����@�������K�p����邱�ƂƂɌ��������ɂ�������炸�A�����Ȃ͖��R�Ə�L�ʒB�ɂ��^�p�𑱂��Ă������߁A�e�n�̋��E���g���͏������Αi�ׂ��N���A1960�N��㔼�ɓ���Ɗe�n�̒n�فA���ق��璴�ߋΖ��蓖���x�����ׂ��Ƃ��锻�����������܂����B
�@���̂����A�ō��ق̔����Ɏ������̂͐É������g�����i���a47�N12��26���ŎO�������W��26��10��2096�Łj�ŁA�������̂͋����@�̐�����ł����A���Ǒ��̏㍐�����p���A�قڑS�ʓI�Ɍ������̑i����F�߂Ă��܂��B���̔������́A�����@�ȑO�̖@�ɑ��锻�f�ł���Ƃ͂����A���{���̘J���@�̓K�p�̊�{�����ɂ��ēI�m�ȔF���������Ă���A�Ԉ�����F�����咣���Ă��鋳��ψ���(������)���������Ȃ߂���e�ƂȂ��Ă��܂��B�����āA���̓_�ɂ��Ă͋����@����Ȍ�Ƃ����ǂ��Ȃ��ς����̂ł͂Ȃ��i�Ƃ������Ƃ��ꕔ�ٔ�������͖Y����Ă���悤�ł����j�ȏ�A���߂Ă�������ƓǂݕԂ����K�v������悤�Ɏv���܂��B
����_�|�́A�܂��A���E���̋Ζ��͑��̐E��̂悤�ɘJ�����Ԃ����Ă�����͂��邱�Ƃ�����ł���Ƃ������ꐫ��L����Ƃ��납��A���E���ɑ��ẮA��ʐE���Ɠ��l�ȈӖ��ɂ����鎞�ԊO�Ζ��蓖���x�����Ȃ��Ƃ��鐧�x���m������Č��݂Ɏ��Ă���̂ł���A���̂��Ƃ́A���_���Ó��ł��邱�Ƃ𗠕t������̂ł���A�Ƃ����B
�@�������A���E���Ƃ����ǂ�����ʂ̐E����O�`�������̂ł͂Ȃ����A���E���������ɂ������ԊO�Ζ��̎��Ԃ�����ɂ����Ė��m�ɂ��邱�Ƃ���ɕs�\�ł���킯�ł��Ȃ��B�`�������ɕ��S�@����A�s�������w�Z�E�����^���S�@����͋��E���ɑ��鎞�ԊO�Ζ��蓖�ɂ��Ă͋K�肵�Ă��Ȃ�����ǂ��A�E�e�@���́A�����̋`�����珔�w�Z�̌o��A���邢�͎s�������̏��w�Z���̐E���̋��^�̕��S�҂ɂ��Ē�߂Ă���ɂ����Ȃ����̂ł��邵�A���^�x�[�X�ؑւ��̍ۂɋ����ɑ��ėD���[�u���Ƃ�ꂽ�����͂���Ƃ��Ă��A���Y�[�u�̎�|�����_�̂悤�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ��@�ߏ㖾�m�ɂ���Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł��āA�O�q�̂悤�ɁA��㍐�l������w�Z�̋��E���ɑ��Ă��J����@�O������K�p���邱�ƂƂ���Ă��邱�Ƃ���l����A�E�̂悤�ȓ_����A��㍐�l��ɑ��Ă͎��ԊO�Ζ��蓖���x�����Ȃ��Ƃ��鐧�x���m������Ă����Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
����Ƃ���ŁA�J����@�O�������A��O�I�ɋ��e���ꂽ���ԊO�J���ɑ��Ċ��������̎x�����`���Â��Ă���̂́A����ɂ�āA�J�����Ԑ��̌����̈ێ���}��ƂƂ��ɁA�ߏd�ȘJ���ɑ���J���҂ւ̕⏞���s�Ȃ����Ƃ�����̂ł���Ɖ����ׂ��Ƃ���A�O�q�̂悤�ɁA�{���e���ԊO�Ζ������ꂽ�����A��㍐�l��ɂ��E�@�����K�p����Ă����̂ł��邩��A��������K��ł��鋋�^������̉��߂ɂ����ẮA���̒�߂鎞�ԊO�Ζ��蓖�̎x�����A�J����@�O�����ɂ�銄�������̎x���Ɠ��l�̖������ʂ������̂ł��邱�Ƃ��l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B���Ƃ��A�Ζ����ԏ�ᔪ��́A��㍐�l�狳�E���ɑ��Ď��ԊO�Ζ��𖽂�����ꍇ����Ɍ��肵�Ă���A���ꂪ�A�E�J����@�O�����̕ی삵�悤�Ƃ���J���҂̗��v�ȏ�̌��v��̗v���Ɋ�Â����̂ł���Ƃ���Ȃ�A��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����ǂ��A����́A���E���̐E���̐�����A���ԊO�Ζ��ɑ���ēɍ�������̂ŁA�����Ƃ��Ď��ԊO�Ζ��͖����Ȃ����ƂƂ��A��������������ё��̒n�������c�̂Ƃ̊W�ɂ����āA���̋��E���Ƃ̊Ԃ̑ҋ���̋ύt���l�����A���A���̍����ɗ݂��y�ڂ����Ƃ̂Ȃ��悤�ɂƂ̔z������A���̂悤�Ȑ�����݂��Ă�����̂Ɖ������̂ł��āA�����ɂ́A��̓I�̏ꍇ�ɁA��i�̈�@�Ȗ��߂Ɏ�����S������āA�Ζ����ԏ��A���K���̒�߂鐳�K�̋Ζ����ԈȊO�̎��Ԃɂ킽�āA�{���̐E���͈̔͂ɑ����邱�Ƃ���ɂ��ċΖ������X�̋��E���ɑ���J����@�ɂ��ی�����Ă܂ł��ێ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǂ̌��v��̗v��������Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̂悤�ȓ_���l����A�É����̌����w�Z�ɂ����āA�Z���̎��ԊO�Ζ����߂Ɋ�Â��A���E�������K�̋Ζ����ԈȊO�̎��Ԃɂ킽�Ė{���̐E���͈̔͂ɑ����邱�Ƃ���ɂ��ċΖ��������ꍇ�ɂ́A�Z���ɉE���߂̌������Ȃ����Ƃ��Ă��A���ꂪ���E���ɑ��Ď�����̍S���͂������̂ł��邩����A�㍐�l�Ƃ��ẮA�E���߂̍s���@��̌��͂̂�����͕ʂƂ��āA�������r���咣���ĉE���ԊO�Ζ��ɑ��鏊��̎��ԊO�Ζ��蓖�̎x�������ނ��Ƃ͋�����Ȃ����̂Ɖ�����̂������ł���B
�@�����āA�{���ɂ�����e�w�Z�s���A�E����c���ɎQ�����邱�Ƃ���㍐�l�狳�E���̐E���͈̔͂ɑ�������̂ł���A�܂��A��㍐�l��ɑ���e�����w�Z���̖{�����ԊO�Ζ����߂̍S���͂ɂ��A�E���߂����ꂽ�����q�ϓI�ɖ@�K�ɔ��������ɖ����Ȃ��̂ł���Ƃ܂ł͂������Ȃ��ȏ�A��㍐�l��͏�i�̐E����̖��߂Ƃ��Ă���ɕ��]������Ȃ��悤�ȗ���ɒu����Ă�����̂Ɖ����ׂ������R�ł���Ƃ����������̔F�蔻�f�́A�����Ƃ��Ď�m���邱�Ƃ��ł���B
�@���Ă݂�ƁA�Z���̈�@�Ȏ��ԊO�Ζ����߂ɂ�Ė{�����ԊO�Ζ���������㍐�l�狳�E���ɂ��Ă����ԊO�Ζ��蓖�������͔F�߂���ׂ��ł���Ƃ������R�̔��f�́A���ǐ����ł���B
�@�Ȃ��A�������̍Ō�ɂ́A���Ǒ��́u�{���Ŗ��Ƃ����悤�Ȏ��ԊO�Ζ��ɑ��ẮA���ԊO�Ζ��蓖���x����Ȃ��A���邢�́A����𐿋����Ȃ��Ƃ������K�́A����ɂ����Ƃ��Ă����̌��͂�L���Ȃ��Ƃ����������́A���@�����̉��߂�������̂ł���v�Ƃ����₯�����C���̎咣�ɑ��Ă��A�u�J�������̊���߂�J����@�̋K�肪���s�@�K�ł��邱�Ƃ́A���@��O���̋K��ɂ�Ė��炩�ł��v��A�u����ɔ����銵�K�͌��͂�L���Ȃ��Ƃ��錴�R�̔��f�́A�����ł���v�Ƃ����Ȃ߂Ă��܂��B
�@
�S�@1968�N�������������@������
�@
�@��L�É������g�����̑��R��1966�N1��29���É��n���ł���A���R��1970�N11��27�����������ł������A����ɐ旧���āA�l���@��1964�N8���̋��^�����̕����ɂ����āA�u���s���x�̂��Ƃɗ�������A���K�̎��ԊO�Ζ��ɑ��ẮA����ɉ����钴�ߋΖ��蓖���x������[�u���u������ׂ��͓��R�ł��邪�A�����A���̖��́A�����̋Ζ����Ԃɂ��Ă̌��s���x���K���ł��邩�ǂ����̍��{�ɂ��Ȃ��鎖���ł��邱�ƂɌڂ݁A�W�����x�����̗v�ۂɂ��ẮA���̓_�����l�����A����ɐT�d�Ɍ�������K�v������v�Əq�ׂĂ��܂����B
�@���̖��ɂ��āA�����}��������͋����̘J����@�K�p���O�̕����ʼn����Ƃ̕��j��ł��o���܂������A1968�N�V�t���X���玩���}�E�����Ȃ��J���ȁE�l���@�ƐՂ��A�����̂ݘJ����@�K�p���珜�O���邱�Ƃ͖@���㍢��ł���Ƃ̌��_���o����A���̌��ʁA������J����@37���Ɋւ��Ă̂ݓK�p���O������j���ł߂�Ɏ���܂���*4�B�������ċ������������@�����Ă����N3���ɍ���ɒ�o����܂����B���̓��e�͌�ɋ����@�Ƃ��Đ���������̂ƂقƂ�Ǖς��܂��A�������������@���4���̋��E���ʎ蓖���K�肷��(��25����4)�ƂƂ��ɁA���@��25����7�Ƃ��Č����̋`�����珔�w�Z���̋����Ɋւ���Ǒւ��K���u���Ƃ������̂ł����B�������A������ɂ��u�����̊ԁv�Ƃ���4�������t���Ă��܂����B�����炭�A�����������t�͐��E�ł��邩�玄���w�Z���t���܂߂ēK�p���O���ׂ��Ƃ��������I�Ȉ��͂̉��ŁA�b��I�ȑ[�u���ƌ����Ă̖@�č쐬�ł��������炾�Ǝv���܂��B
�@����ł͎Q�l�l�Ƃ��ĐΈ�Ƌv����R����Ă�A���@�ŘJ����@�̎蒼�����s���Ƃ�������R�̐R�c���o��ׂ��Əq�ׁA������ē��N5���ɒ���R�̗Վ�����J����܂������A���_�͏o���A���ǐR�c�����p�ĂƂȂ�܂����B
�@
�T�@1969�N�̎����}��
�@
�@1969�N8���ɂ͎����}��������E�������x�������u���E���̋��^���Ɋւ�����ʑ[�u�@�āv������܂������A����͋����̐��E�Ƃ��Ă̒n�ʂ��m������Ƃ��������I�ȉۑ���������A���ʂ̎{��Ƃ��ē��ʑ[�u�@�𐧒肷��Ƃ������̂ł����B
����}�Ƃ��ẮA���E���̐��E�Ƃ��Ă̒n�ʂ��m�����邽�߁A��{�I�Ȑ��x�̎�������������̂ł��邪�A��������A���ʂ̎{��Ƃ��āA���̂��сA��������y�ѕ������x������ł͎��Ɏ����v�j�̔@�����Ă��B���
�@�����y�ь����̋`�����珔�w�Z���̋���E���̋��^���Ɋւ�����ʑ[�u�@�ėv�j
��A���E���ʒ����蓖�̎x��
(1)�@�������͌����̋`�����珔�w�Z���̋���E���̐��E�Ƃ��Ă̐E���̓��ꐫ�ƍ��x�̐ӔC�ɂ��݁A���ʕK�v�ȑ[�u�Ƃ��āA����ɋ��E���ʒ����蓖���x�����邱��(�Z���E�������܂ށB)
(2)�@���E���ʒ����蓖�́A��i�����w�Z�̋���E���̏ꍇ�́A�����B�ȉ������B�j�̌��z���тɂ���ɑ��钲���蓖�y�юb��蓖�̌��z�̍��v�z�̘Z���Ƃ��邱�ƁB
��A���ߋΖ��蓖�̐����y�т���Ɋ֘A����[�u
(1)�@���E���ʒ����蓖�̎x���ɔ����A�����̋`�����珔�w�Z���̋���E���ɂ��ẮA��ʐE�̐E���̋��^�Ɋւ���@���ɓ����݂��A���ߋΖ��蓖�y�ыx�����̎x���̋K��̓K�p�����O���邱�ƁB
(2)�@���E���ʒ����蓖�̎x���ɔ����A�����̋`�����珔�w�Z���̋���E���ɂ��ẮA�J����@�y�ёD���@���̎��ԊO�J���ɑ��銄���������͎��ԊO�蓖�̋K��̓K�p�����O���邱�ƁB
(3)�@�����̋`�����珔�w�Z���̋���E���ɂ��āA�J����@���̎��ԊO�J���ɂ��Ă̋���̋K��(��O�\�Z��)�̓K�p�����O���邱�ƁB
(4)�@�����̋`�����珔�w�Z���̋���E���ɂ��āA�����̂��ߕK�v������Ƃ��́A���ԊO�Ζ��𖽂��邱�Ƃ��ł���|�𖾂炩�ɂ��邱�Ɓi�J����@��O�\�O���O���̋K���ǂݑւ��ēK�p���邱�ƁB�j�B
�O�A������E�Ƃ��Ă̒n�ʂ̊m��
�@�����y�ь����̋`�����珔�w�Z���̋���E���ɂ��A���̋�����E�Ƃ��Ă̒n�ʂ��m�����邽�߁A��{�I�Ȑ��x���߂������ɂ����Ď��������ׂ��ł��邱�ƂL���A�O�L��y�ѓ�̑[�u�́A���̖ڕW�B���̂��߂̒i�K�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��邱�ƁB
�@����͂������ɋ����@�̋K�肻�̂��̂ł����A���ꂪ�u���ʂ̎{��v�ł���A�����ɂ�蓥�ݍ��u��{�I�Ȑ��x�v�̎����������Ă��邱�Ƃ����炩�ɂ���Ă���_���d�v�ł��B����͓����A�����g�̋��t�J���Ҙ_�ɑ��鋳�t���E�_�Ƃ��������I�Η��}���̒��Ō���Ă������̂ł����B
�@�Ȃ��A1967�N����Љ�}����o���Ă������q����E���玙�x�ɖ@�Ăƈ��������ɎЉ�}�������}�Ăɐڋ߂��A�����^��}������Ăɂ��c�����@�Ƃ��Ē�o���悤�Ƃ����������������悤�ł����A�����g�̔��ɑ����Ď��s�ɏI������Ƃ����o�܂��������悤�ł�*5�B����������]�Ȑ܂̖��ɗ^��}������Ăɂ��A1975�N6���ɋ`�����珔�w�Z���̏��q����E���y�ш�Î{�݁A�Љ���{�ݓ��̊Ō�w�A�ەꓙ�̈玙�x�ƂɊւ���@���Ƃ��Đ������Ă��܂��B
�@
�U�@�l���@�ӌ�
�@
�@�����������ŁA�l���@��1971�N2���A�u�`�����珔�w�Z���̋��@���ɑ��鋳�E�����z�̎x�����Ɋւ���@���̐���ɂ��Ă̈ӌ��̐\�o�v���s���܂����B����ƁA�Ƃ�킯���̐����������A�ߔN�̉����R�����ł����̂܂ܓ��P����Ă��鋳���̐E���̓��ꐫ��_���Ă��錠�Ђ��鐭�������Ƃ��Ďg��ꑱ���Ă��邱�Ƃ��l����ƁA���́i�}�C�i�X�ʂ��܂߂��j�d�v���͋ɂ߂đ傫�Ȃ��̂�����܂��B
�@�܂��A�l���@�̖��ŏo���ꂽ�u�`�����珔�w�Z���̋��@���ɑ��鋳�E�����z�̎x�����Ɋւ���@���̐���ɂ��Ă̈ӌ��̐\�o�Ɋւ�������v�̖`���̕�����ǂ�ł݂܂��傤�B����́A����܂ŋ���E�ł͓��R�̔@������Ă��Ă��Ȃ���A�����̗��@�̍����Ƃ��ėp����ꂽ���Ƃ̂Ȃ��v�z���A�����������R�̗��H�ł��邩�̔@������Ă��܂��B
��������̋Ζ����Ԃɂ��ẮA���炪���ɋ����̎������A�n�����Ɋ�Â��Ζ��Ɋ��҂���ʂ��傫�����Ƌy�щċx�݂̂悤�ɒ����̊w�Z�x�Ɗ��Ԃ����邱�Ɠ����l������ƁA���̋Ζ��̂��ׂĂɂ킽���Ĉ�ʂ̍s�������ɏ]������E���Ɠ��l�Ȏ��ԊǗ����s�����Ƃ͕K�������K���łȂ��A�Ƃ�킯���ߋΖ��蓖���x�͋����ɂ͂Ȃ��܂Ȃ����̂ƔF�߂���B����āA�Ζ����Ԃ̊Ǘ��ɂ��ĉ^�p��K�Ȕz����������ƂƂ��ɁA�����̒��ߋΖ��Ƃ���ɑ��鋋�^���Ɋւ��錻�s���x�����߁A�����̐E���ƋΖ��̑ԗl�̓��ꐫ�ɉ��������̂Ƃ���K�v������B
�@���̗����́A�S�����藧���Ȃ��Ƃ����킯�̂��̂ł͂���܂���B�����͂܂����݂��Ȃ����x�ł������A��ɐ��Ɩ��^�ٗʘJ�����Ƃ������x������A���t�̂�����w�������ɂ��Ă͂��̓K�p�ΏۂƂȂ������Ƃ��l����A���x�̍��͂���Ƃ͂����A���Z�ȉ��̋��t�ɂ��Ă������ꏭ�Ȃ���ٗʘJ���I�ȑ��ʂ͂���A��ʘJ���҂Ɠ����悤�ȘJ�����ԊǗ������邱�Ƃ͕K�������K���łȂ��A���ԊO�E�x���J���̊��������̓K�p�����O����Ƃ������z�͏\���ɂ��肦���Ƃ����Ă����������m��܂���B
�@�������Ȃ���A���ɂ��̗�����F�߂��Ƃ��Ă��A����͂����܂ł����t�Ƃ����E��̓��ꐫ�Ɋ�Â����̂ł����āA���ƌ������ł��낤���n���������ł��낤�����ԘJ���҂ł��낤���S�������悤�ɓK�p�����ׂ��ł���A�����̐g���̈Ⴂ�ɂ���ĈقȂ点�邱�Ƃ������������킯�̂��̂ł͂���܂���B�l���@�������w�Z�̋��t�ɂ��Ăǂ̂悤�ɍl���Ă����̂��͕s���ł����A����̏��ǂł͂Ȃ�����Ƃ����āA���ɑ��݂���l�X������悤�ȋc�_�C�œW�J���Ă������Ƃ́A���ꂪ�����̐����̒��Ŕ����Ă������炾�Ƃ���������͗����ł���Ƃ͂����A�����㐢�Ɏc�����ʂɂȂ����Ƃ����ׂ��ł��傤�B
�@�������A���̐l���@�ӌ��͎��͑�ϔ���ȗ����ʒu�ɂ���܂��B�Ƃ����̂��A�����������x�㍑�̋@�ւƂ��Ă̐l���@��������L���Ă���͍̂��ƌ������Ɋւ��Ă����ł���A�n���������ɂ��Ă͒��ڂ̌�����L���Ă��Ȃ��̂ŁA���̈ӌ��\�o�͍��ƌ��������鋳�t�ɂ��Ă̂���Ă��邩��ł��B���ہA���̈ӌ��\�o�ɓY�t����Ă���̂́u�����̋`�����珔�w�Z���̋��@���ɑ��鋳�E�����z�̎x�����Ɋւ�����ʑ[�u�v�j�v�ł����āA�n����������������w�Z�̋��t�͂��̑ΏۊO�Ȃ̂ł��B
�@���ꂪ����ł��鏊�Ȃ͂�������ł��傤�B2004�N�x���獑����w�@�l�����Ė��ԘJ���҂ƂȂ��������w�Z�̋��t�����́A���Đl���@�����ނ�̂��Ƃ�O���ɒu���āu�����̐E���ƋΖ��̑ԗl�̓��ꐫ�ɉ��������̂Ƃ���K�v������v�Ƃ��u���ߋΖ��蓖���x�͋����ɂ͂Ȃ��܂Ȃ����̂ƔF�߂���v�ƌ����Ă���Ă����̂ɁA���̐��x����r������Ă��܂��A�J����@�̘J�����ԋK�������̂܂ܓK�p�����悤�ɂȂ��Ă��܂����̂ł�����B�l���@�����O���ɒu���Ă��������w�Z�̋��t�����₻�̓K�p�Ώۂł͂Ȃ��Ȃ��Ă���ɂ�������炸�A�����I�O�̂��̗����������Ȃ����������Ă���Ƃ�����Ȏ��Ԃɂ��ẮA�s�v�c�Ȃ��ƂɒN���܂Ƃ��Ɏw�E���悤�Ƃ��Ă��܂���B
�@�Ȃ��A���̍����w�Z�ɌW����ʑ[�u�v�j�̒��g�́A�����w�Z�ւ̏��p�������Ăقڂ��̂܂܋����@�Ƃ��Ď�������Ă��܂��̂ŁA�����ł͏ȗ����܂��B
�@
�V�@����R�̐R�c
�@
�@�l���@�̈ӌ��͍����w�Z�ɌW����̂ł����A����𗧖@�����悤�Ƃ���Ɠ��R�ő吨�͂ł�������w�Z�ɂ��K�p���邱�ƂɂȂ�܂��B��������ƁA����1968�N�̋����@�����Ă̎��ɖ��ƂȂ����悤�ɁA�n���������ɂ͘J����@�������K�p�ƂȂ��Ă���̂ŁA����R�̐R�c�����ƂȂ�܂��B�������āA�l���@�ӌ��̏o���ꂽ1971�N2���ɁA�J���ȂƐl���@���璆��R�ɕ��A�@�č쐬�̍l������������܂����B���ژJ����@����������̂ł͂Ȃ��A�J����@�̓K�p�W���߂��n���������@�̉���������Ƃ�����������A�����܂ł������ł����āA����ł͂���܂���B
�@����ɑ��钆��R�̌��c�͈ȉ��̒ʂ�ł��B
�P�@�J����@�����̖@���ɂ���Ĉ��Ղɂ��̓K�p�����O�����悤�Ȃ��Ƃ͓K���łȂ��̂ŁA���̂悤�ȏꍇ�ɂ����ẮA�J����b�́A�{�R�c��̈ӌ��������悤�w�߂�ꂽ���B
�Q�@������b���l���@�Ƌ��c���Ē��ߋΖ��𖽂�����ꍇ���߂�Ƃ��́A��������E���̓��e�y�т��̌��x�ɂ��ĊW�J���҂̈ӌ������f�����悤�K�ȑ[�u���Ƃ���悤�w�߂�ꂽ���B
�@�܂��A����͓����̉����֕����̌���ł����A�����ȂƘJ���Ȃ͂��̎����̂悤�Ȋo�������킵�Ă��܂��B
�o��
�@�@���a46�N2��15��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������142��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���111��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �����ȏ�����������ǒ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�J���ȘJ����ǒ�
�����y�ь����̋`�����珔�w�Z���̋���E���̋��^���Ɋւ�����ʑ[�u�@(��)�ɂ���
�@��65��ɒ�o�����u�����y�ь����̋`�����珔�w�Z���̋���E���̋��^���Ɋւ�����ʑ[�u�@(��)�v�Ɋւ��A�����ȂƘJ���Ȃ͉��L�̒ʂ藹�����A�����Ȃ͂��̎�|�̎����ɓw�߂���̂Ƃ���B
�L
��A�����Ȃ́A����E���̋Ζ����ł��邾���A���K�̋Ζ����ԓ��ɍs����悤�z�����邱�ƁB
��A������b���l���@�Ƌ��c���Ď��ԊO�Ζ��𖽂�����ꍇ���߂�Ƃ��́A��������E���ɂ��ẮA��ނȂ����̂Ɍ��邱�ƁB
�@�Ȃ��A���̏ꍇ�ɂ����ĊW����E���̈ӌ��f���邱�Ɠ��ɂ��Ζ��̎���ɂ��ď[���z�����邱�ƁB
�@
�W�@�@�Ă̍���R�c
�@
�@�������ē�������ɒ�o���ꂽ�u�����y�ь����̋`�����珔�w�Z���̋���E���̋��^���Ɋւ�����ʑ[�u�@�āv�́A��}�̔���������`�œ��N5���ɐ����Ɏ���܂����B
�@�c���^�����Ă����ƁA�����B�v�l���@���ق��A���Ȃ�{�C�Łu�����̎������A�n�����v��_���Ă��邱�Ƃ�������܂��B
�����قǂ̎G���̔r���A����͏������Ⴉ���m��܂���ǂ��A�����������Ƃ���X�傫���l���Ă��邱�Ƃ������Ō��I�\���グ���킯�ł��B������Ƃ��Ύ������Ƒn�����Ƃ����܂��Ă��A���������`�����X���Ȃ���ΐ���傫�����ċ��ԋ@��͂Ȃ��������낤�Ǝ��͎v���܂��B����O���ɂ����鋳���̕��X�̋Ζ����Ԃ͂ǂ��Ȃ��Ă��邩�Ƃ����ƁA������������͎��Ǝ��Ԃ��Ζ����ԂƂ���Ă���悤�Ɏv���܂��B��������̕����Ƃ��ẮA�����͂���ς肻�������ӂ��Ɏ����Ă����ׂ��ł��낤�Ǝv����ł��B���������܂��Ă���������b�������Ă����A���������i�W�̓��������ɊJ����Ƃ����傫�ȋC�����������Ă����͂��̈ӌ��̒�o��\���グ���B���������_�ł͂���͑����̈Ӌ`�������Ă���B�[���������������Ă���Ƃ����ӂ��Ɍ䗹���������������Ǝv���킯�ł��B
�@�������ق́A���t���w�Z���̂��܂��܂ȎG������炳��Ă���ڂ̑O�̓��{�̌����O��ɂ���̂ł͂Ȃ��A���ăW���u�^�Љ�̃v���t�F�b�V���i���ȋ��t�����Ɠ��l�A���Ƃ��������̐��s���ׂ��E���ł���悤�ȁA����䂦���Ǝ��Ԃ������Ζ����Ԃł���悤�ȁA���̂悤�Ȃ���ׂ��Љ���A����Ɍ����Ă̑����Ƃ��Ă��̋����@�����p���悤�ƍl���Ă����̂ł��傤�B���̈Ӑ}�̐^�������̂͋^�����Ƃ͂ł��܂���B����������Ȃ�A���Ƃ��Ό�̍ٗʘJ�����̂悤�ɁA�u���̐��s�̕��@��啝�ɘJ���҂̍ٗʂɈς˂�v�]�X�Ƃ��������~�߂��K�v�������̂ł��傤�B���̈Ӗ��ł́A��}�c���̌����悤�Ɂu�������A�n���������҂���Ȃ�A�Ζ����߂����Ȃ��܂Ȃ��v�͂��ł��B�����āA�����A�����́u�G���v��y���ɒ�����c��Ȋw�Z������k�w���A���������X���������Ă��鋳�t�����ɁA�����@�̖{���̎v�z�Ƃ��Ă��̍������ق̌��t��ǂ܂�����A�����Ȃ銴�z��R�炷�������[���Ƃ��낪����܂��B
�@
�X�@1971�N�����@
�@
�@�������Đ������������@�́A��q�̒ʂ茻�s�����@�Ƃ͈قȂ�A�����w�Z�Ɋւ���K�肪��ŁA����������w�Z�ɏ��p������̂ł����B���Ȃ킿�A��3�������7���܂ł͐�獑���w�Z�̋��t�ɑ���K��ł���A��8���ȉ��͂���������w�Z�ɏ��p���邽�߂̋K�肾�����̂ł��B
�i��|�j
��1���@���̖@���́A�����y�ь����̋`�����珔�w�Z���̋���E���̐E���ƋΖ��ԗl�̓��ꐫ�Ɋ�Â��A���̋��^���̑��̋Ζ������ɂ��ē�����߂���̂Ƃ���B
�i�����̋`�����珔�w�Z���̋���E���̋��E�����z�̎x�����j
��8���@�����̋`�����珔�w�Z���̋���E���ɂ��ẮA��O���������܂łɋK�肷�鍑���̋`�����珔�w�Z���̋���E���̋��^�Ɋւ��鎖������Ƃ��ċ��E�����z�̎x�����̑��̑[�u���u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�i�����̋`�����珔�w�Z���̋���E���Ɋւ���Ǒւ��j
��10���@�����̋`�����珔�w�Z���̋���E���ɂ��ẮA�n���������@�i���a��\�ܔN�@�����S�Z�\�ꍆ�j��\�����O���{�����u�����A���\�l���ꍀ�v�Ƃ���̂́u��O�\�O���O�����u��\�Z���v�Ƃ���̂́u��\�v�ƁA�u�J�������邱�Ƃ��ł���v�Ƃ���̂́u�J�������邱�Ƃ��ł���B���̏ꍇ�ɂ����āA�������̌��N�y�ѕ������Q���Ȃ��悤�ɍl�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ɠǂݑւ��ē����̋K���K�p������̂Ƃ��A���@�����A���\�l���ꍀ�A��O�\�����v�ƁA�u��\�O���ꍀ�v�Ƃ���̂́u��\�O���ꍀ�A��Z�\�����v�ƁA�u�K��́v�Ƃ���̂́u�K��i�D���@�掵�\�O���̋K��Ɋ���߂̋K�蒆���@��Z�\�����ɌW����̂��܂ށB�j�́v�Ɠǂݑւ��ē����̋K���K�p������̂Ƃ���B
�i�����̋`�����珔�w�Z���̋���E���̐��K�̋Ζ����Ԃ�������Ζ����j
��11���@�����̋`�����珔�w�Z���̋���E���i�Ǘ��E�蓖����҂������B�j�𐳋K�̋Ζ����ԁi���^�@��\�l���̋K��ɑ���������̋K��ɂ��Ζ����Ԃ������B�ȉ����̏��ɂ����ē����B�j�������ċΖ�������ꍇ�́A�����̋`�����珔�w�Z���̋���E���ɂ��Ē�߂�ꂽ�����Ƃ��ď��Œ�߂�ꍇ�Ɍ�����̂Ƃ���B���^�@��\�����̋K��ɑ���������̋K��ɂ��x���Ζ��蓖����ʂ̐E���ɑ��Ďx���������ɂ����ē��Y����E���𐳋K�̋Ζ����Ԓ��ɋΖ�������ꍇ���A���l�Ƃ���B
�@�����钴��4���ڂ́A�����w�Z�ɌW���7���Łu������b���l���@�Ƌ��c���Ē�߂�ꍇ�Ɍ�����̂Ƃ���v�Ƃ���Ă���̂��āA���N7���̕����ȌP�߁u����E���ɑ����ԊO�Ζ��𖽂���ꍇ�Ɋւ���K���v�ɂ���Ď��̂悤�ɒ�߂��܂����B
�i���ԊO�Ζ��𖽂���ꍇ�j
��4���@����E���ɑ����ԊO�Ζ��𖽂���ꍇ�́A���Ɍf����Ɩ��ɏ]������ꍇ�ŗՎ����ً͋}�ɂ�ނȂ��K�v������Ƃ��Ɍ�����̂Ƃ���B
��@���k�̎��K�Ɋւ���Ɩ�
��@�w�Z�s���Ɋւ���Ɩ�
�O�@�w���̋�����K�̎w���Ɋւ���Ɩ�
�l�@���E����c�Ɋւ���Ɩ�
�܁@���ЊQ����ނȂ��ꍇ�ɕK�v�ȋƖ�
�@�����A��7���ł͕����Ȏ��g���K���ɒ�߂����ڈȊO�̋Ɩ��������w�Z�̎g�p�ґ����闧��ɂ��镶���Ȃ���点��Ƃ����֔����I�Ȗ��ł����A��������p���Ă����11���ł́A�n�������̂������Ȃ̋K�����u��Ƃ��āv���Œ�߂���̂ł�����A���̔���͊ԐړI�Ȃ��̂ƂȂ�܂��B
�@�Ȃ��A���N7���ɏo���ꂽ�����ʒB�i���a46�N7��9����������377���j�́A���������ɏڂ���������Ă��܂��B
(1)�@���K�Ƃ́A�Z�O�̍H��A�{��(�{�B����܂ށB)�A�D���𗘗p�������K�y�є_�сA�{�Y�Ɋւ���Վ��̎��K���w�����̂ł��邱�ƁB
(2)�@�w�Z�s���Ƃ́A�w�|�I�s���A�̈�I�s���y�яC�w���s�I�s�����w�����̂ł��邱�ƁB���̏ꍇ�ɂ�����w�Z��ʂ��Ƃ̊w�Z�s���Ƃ́A���ꂼ��̊w�K�w���v�̂ɒ�߂��L�w�Z�s���ɑ���������̂ł��邱�Ƃɗ��ӂ��邱�ƁB
(3)�@�w���̋�����K�̎w���Ƃ́A�����w�Z�ɂ�����w���̋�����K�̎w�����w�����̂ł��邱�ƁB
(4)�@���ЊQ����ނȂ��ꍇ�ɕK�v�ȋƖ��Ƃ́A���ЊQ�̏ꍇ�ɕK�v�ȋƖ��̂ق��A�����E���k�̕������a���l���ɂ������ꍇ�ɂ�����K�v�ȋƖ��y�є�s�h�~�Ɋւ��鎙���E���k�̎w���Ɋւ��ً}�̑[�u��K�v�Ƃ���Ɩ����w�����̂ł��邱�ƁB
�@�����Ƃ��A����4���ڂ͓��������Ȃ��l���Ă������̂�肾���ԏk�����Ă���悤�ł��B����Ő������v�������������������Ă����͎̂���9���ڂł���*6�B���݂̕������ɂȂ���N���u�����͓����Ăɂ͓����Ă��Ȃ���A�l���@�Ƃ̋��c�ō폜����Ă������Ƃ�������܂��B
��A�����܂��͐��k�̎��K�Ɋւ���Ɩ�
��A�C�w���s�A�����A�^����A�w�|��A�����Փ��̊w�Z�s���ŁA�w�Z���v����{���鋳�犈���Ɋւ���Ɩ�
�O�A�w���̋�����K�̎w���Ɋւ���Ɩ�
�l�A���E����c�Ɋւ���Ɩ�
�܁A�g�̌����Ɋւ���Ɩ�
�Z�A���w�����Ɋւ���Ɩ�
���A�w�Z���v����{����N���u����
���A�}���َ���
��A���ЊQ�̏ꍇ�ɕK�v�ȋƖ�
�@���̑�10���̓ǂݑւ��K��ł����A�����@���莞�_�œǂݑւ���ꂽ�K��Ԃ���Č����Ă݂܂��傤�B����͘J����@��ǂݑւ��Ă���n���������@������ɓǂݑւ���Ƃ����܂��ƂɋZ�I�I�ȋK��Ȃ̂ŁA�����ق����̂�2�i�K�ɂȂ�܂��B�܂��A��10���œǂݑւ���ꂽ�n���������@��58���3���͂����Ȃ�܂��B
�i���̖@���̓K�p���O���j
��58���@���
3 �J����@��O�\�O���O�����u��\�Z���v�Ƃ���̂́u��\�v�ƁA�u�J�������邱�Ƃ��ł���v�Ƃ���̂́u�J�������邱�Ƃ��ł���B���̏ꍇ�ɂ����āA�������̌��N�y�ѕ������Q���Ȃ��悤�ɍl�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ɠǂݑւ��ē����̋K���K�p������̂Ƃ��A���@�����A���\�l���ꍀ�A��O�\�����A�掵�\��������\�O���܂ŋy�ё�S����̋K����тɑD���@�i���a��\��N�@����S���j��Z�𒆘J����@�����Ɋւ��镔���A��O�\���A��O�\���𒆋Ζ������Ɋւ��镔���A��\�O���ꍀ�A��Z�\�����A�攪�\��������S���܂ŁA��S����y�ё�S���𒆋Ζ������Ɋւ��镔���̋K����тɂ����̋K��Ɋ�Â����߂̋K��i�D���@�掵�\�O���̋K��Ɋ�Â����߂̋K�蒆���@��Z�\�����ɌW����̂��܂ށB�j�́A�E���Ɋւ��ēK�p���Ȃ��B�������A����
�@�����Ă������������������ق������ƂŁA�悤�₭�ǂݑւ���ꂽ�J����@�̋K�肪���̔�߂�ꂽ�p�������܂��B
��33���@���
�B�@�����̂��߂ɗՎ��̕K�v������ꍇ�ɂ����ẮA��ꍀ�̋K��ɂ�����炸�A�攪���\�̎��Ƃɏ]�����銯���A�������̑��̌������ɂ��ẮA�O���Ⴕ���͑�l�\���̘J�����Ԃ��������A���͑�O�\���̋x���ɘJ�������邱�Ƃ��ł���B���̏ꍇ�ɂ����āA�������̌��N�y�ѕ������Q���Ȃ��悤�ɍl�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
��36���@�i�����̂܂ܑ��݁j
��37���@�i�s���݁j
�@����܂ł͘J����@��37���i���������j�̋K��͒n���������@��58���̓ǂݑւ�����K�p����Ă��܂����B����䂦�ɁA��q�̂悤�Ȓ��Αi�ׂ����X�ƋN������A����ψ���͕Ђ��[����s�i���Ă����̂ł��B���̋K�肪�n���������@��58���ɂ��ǂݑւ���͓K�p����Ȃ��Ȃ�܂����B���Αi�ׂ̍�����D���Ƃ��������@�̍ő�̖ڕW�͂������Ď������܂����B
�@����ŁA���ԊO�E�x���J���𖽂��鍪���K��ɂ��ẮA���������s�����ȏƂȂ�܂����B�J����@��͊������Ɍ����Ă����33���3�����w�Z���t�ɂ��g�債�āA�u�����̂��߂ɗՎ��̕K�v�v������Ύ��ԊO�E�x���J���𖽂��邱�Ƃ��ł���悤�ɂ������ŁA��36���͂����ēK�p���O���Ă��Ȃ��̂ł��B�����́A�����ȃT�C�h�͌`���I�ɂ͊O���Ă��Ȃ������ۂɂ͓K�p�̗]�n���Ȃ��Ȃ�Ɖ��߂��Ă��܂����A�{���ɂ����Ȃ�@�����36������37���ƕ��ׂĕs�K�p�Ƃ���悤�ɓǂݑւ��K��������Ηǂ������͂��ŁA�����Ȃ��Ă��Ȃ��Ƃ����̂́A��33���3���ȊO�ɂ����ԊO�E�x���J�������蓾�邾�낤�ƁA���Ȃ��Ƃ������ȈȊO�̐��{�@�ւ��l�������炾�Ǝv���܂��B����c���^������ƁA�������v�J����ǒ��́u36���͂͂����Ă���܂���v�Ɠ��ق��Ă���*7�A�K�p�̗]�n���Ȃ��Ȃ�Ƃ͍l���Ă��Ȃ��������Ƃ��������Ă��܂��B
�@
�P�O�@������w�@�l���ɂ�����
�@
�@�������̋����@�͈ȏ�̂悤�Ȃ��̂ł������A���̍\���{�I�ɗh�邪�����̂��A2003�N7���ɐ������A2004�N�x����{�s���ꂽ������w�@�l�@�ł��B�����w�Z�̋��t�͊��S�ɖ��ԘJ���҂ƂȂ������߁A�����ɐ�������������w�@�l�@���̎{�s�ɔ����W�@���̐������Ɋւ���@���ɂ��A�����@�͖{�̂ł������͂��̍����w�Z���O����Ă��܂����̂ł��B
�@�������Ė@�����́u�����̋`�����珔�w�Z���̋���E���̋��^���Ɋւ�����ʑ[�u�@�v�ƂȂ�A���Ƃ��ƍ����w�Z�Ɋւ���K������p����Ă��������w�Z��������ɔ��F����Ă��܂��܂����B����ɂ��A����܂ł͑�11���Łu�����̋`�����珔�w�Z���̋���E���ɂ��Ē�߂�ꂽ�����Ƃ��ď��Œ�߂�v�Ƃ���Ă��������钴��4���ڂ��A�u���߂Œ�߂��ɏ]�����Œ�߂�v���ƂƂ���A����7���ɕ���đ�2���Ƃ��āu�O���̐��߂��߂�ꍇ�ɂ����ẮA����E���̌��N�ƕ������Q���邱�ƂƂȂ�Ȃ��悤�Ζ��̎���ɂ��ď\���Ȕz��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����ꕶ���lj�����܂����B
�@����ɂ��Ă��A�l���@���B�ꏊ�ǂ��鍑�ƌ��������鍑���w�Z�̋��t�ɂ��āA����قǔM��Ɂu�����̎������A�n�����v���������A�u���ߋΖ��蓖���x�͋����ɂ͂Ȃ��܂Ȃ����̂ƔF�߂���v�ƌ����Ă���Ă����̂ɁA���̍����w�Z�̋��t�͂�������ƘJ����@�S�ʓK�p���O����J����@�t���K�p�̐��E�ɒǂ�����Ă��܂����̂ł�����A�Ȃ�Ƃ�����Ȃ��Ƃł��B��Ɏc���ꂽ�n����������������w�Z�̋��t�́A���X���p�ł������K��̎���̍��ɍ��炳��A�����K�p�̂͂��̘J����@��K�p���O���闝�����������������ł����炦�グ�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B
�@�Ȃ��A����Ɠ����ɒn���Ɨ��s���@�l�@�����肳��A���̋Ɩ��ɂ́u��w�̐ݒu�y�ъǗ����s�����Ɓv���܂܂ꂽ���߁A������w�@�l���ݒu���邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂����B������w�@�l�͖@���シ�ׂĔ�������^�i��ʒn���Ɨ��s���@�l�j�ŁA��w�̐ݒu�Ǘ��ɕ��т���Ɩ��Ƃ��ĕ����w�Z�̐ݒu�Ǘ����\�ł��B���ۂɂ́A����w����L���鍑����w�ƈႢ�A������w�ŕ����w�Z��L������̂͐����Ȃ��ł����A���������݂��܂��B���Ƃ��A������w�@�l���Ɍ�����w�ɂ͕������Z�ƕ������w�Z������܂��B
�@������w�@�l�����w�Z�̋��t�ɂ͋����@�͓K�p�����̂ł��傤���B�w�Z����@��2���2���́A�u�����w�Z�Ƃ́A�n�������c�̂̐ݒu����w�Z�v�ƒ�`���Ă��܂����A�����1���Łu�n�������c�́i�n���Ɨ��s���@�l�@�����Z�\�����ꍀ�ɋK�肷�������w�@�l������܂ށB��������ɂ����ē����B�j�v�Ƃ���̂ŁA������w�����w�Z�����@�ɂ��������w�Z�ł���A�]���āA�����@��2���2���ɂ�蓯�@���K�p�����u�`�����珔�w�Z���v�Ɋ܂܂�܂��B�܂�A�����@�͓K�p����܂��B
�@�Ƃ��낪�b�͂���ŏI���܂���B������w�@�l�͔�������^�ł���A�n���������@�͂��������K�p�̗]�n�͂���܂���B�Ƃ������Ƃ́A�����@���K�p�����Ƃ����Ă�����͋��E�����z�̎x���⒴��4���ڂɌW�镔���ł����āA��10���̒n���������@�̓ǂݑւ��K��́A�ǂݑւ�����ׂ��n���������@��58���3�����K�p����Ă��Ȃ��ȏ��U��ƂȂ炴��܂���B�܂�A������w�@�l�����w�Z�̋��t�͌�����w�����Ɠ��l�ɁA�J����@�̓K�p��̓t���ɖ��ԘJ���҂Ȃ̂ł����āA��33���3���ɂ���Ď��ԊO�E�x���J���𖽂��邱�Ƃ͂ł����A��36���ɂ���ĘJ�g�����������Ȃ���Β���4���ڂɊY�����悤�����܂������͕s�\�ł���A������4���̋��E�����z�������Ă��邩��Ƃ����āA��37���ɂ�銄�������̎x����Ƃ�邱�Ƃ͂ł��܂���B����A��w�����ł͂Ȃ��̂Ő��Ɩ��^�ٗʘJ�����̓K�p���ł��܂���B���s�@�͂��������d�g�݂ɂȂ��Ă���̂ł��B
�@
�P�P�@���������v�̃C���p�N�g
�@
�@���̊ԁA�����w�Z���t�̒����ԘJ���͈����̈�r�����ǂ��Ă����܂����B���̑啔���̓N���X�S�C�╔�����S���ɔ������̂ŁA����4���ڂɊ܂܂�Ȃ��u�����I�Ζ��v�Ƃ���A��������u���ꑱ���Ă��܂����B���ԂƂ��Ă͂���Ȃ��ɂ͊w�Z�^�c�����藧���Ȃ��ɂ�������炸�A���������t�̎����I�����䂦�����ł͂Ȃ��Ƃ������s�s�Ȃ��Ƃ��܂���ʂ��Ă����̂ł��B�������ٔ������A�Ⴆ�Ζk�C�����g�����i�D�y���ٕ���19�N9��27���j�ɂ����āA�����@�̐���o�܂����X�ƕ��ח��Ă�������ɁA�u����E�����v���t�F�b�V�����̈���ł���Ƃ̎��o�̂��ƁC����I�ɐ��K�̋Ζ����Ԃ��ċΖ������ꍇ�ɂ́C���̋Ζ����Ԃ������Ԃɋy�ԂƂ��Ă����ԊO�Ζ����蓖�͎x������Ȃ��v�Ƃ��A���܂����u�Z��������E���ɂЂ����炨�肢���ăN���X�S�C�╔�����̒S���������Ă��炤���Ƃ����饥����C���̂悤�ȏꍇ���C����E�����v���t�F�b�V�����̈���ł���Ƃ̎��o�̂��Ƃɂ�ނ����������̂ƍl���邱�Ƃ��ł��邩��C����������E���̎���I�Ȍ���Ƃ����ׂ��ł���v�ƁA�����e�F���Ă��܂����B
�@�ٔ��������������Ă����̂ň��S���Ă��������Ȋw�Ȃ̐K�ɉ����ɂ́A�ߔN�́u���������v�v�ɂ�钷���ԘJ���K���̓o���҂��Ȃ���Ȃ�܂���ł����B�{���œ��������v�ɂ��čĐ�����K�v�͂Ȃ��ł��傤���A�����@�̓K�p���������w�Z���t�ɑ���C���p�N�g�Ƃ��ďd�v�������̂́A�J����@�ɂ����鎞�ԊO�E�x���J���̏���K�����ꎩ�̂����ނ���A�J�����S�q���@�ɂ�����֘A���K��ł����B�Ƃ����̂��A�n���������@��58���2���́A�u�J�����S�q���@������͂̋K�襥��́A�n�������c�̂̍s���J����@����ʕ\����ꍆ�����\���܂ŋy�ё�\�O�������\�܍��܂łɌf���鎖�Ƃɏ]������E���ȊO�̐E���Ɋւ��ēK�p���Ȃ��v�ƋK�肵�A���͂܂�J���ЊQ�h�~�v��ɌW�鎖���ȊO�͑S�Č����w�Z���t�ɂ��K�p����邩��ł��B�Ƃ������Ƃ́A�ߘJ���h�~��Ƃ��ču�����Ă����66����8�����66����9�܂ł̋K������̂܂ܓK�p����܂��B
�@����ɂ��A���Ǝҁi���w�Z�ݒu�ҁj�́A���̘J�����Ԃ̏��̑��̎������J���҂̌��N�̕ێ����l�����Č����J���ȗ߂Œ�߂�v���i���x�e���Ԃ�����1�T�ԓ�����40���Ԃ��ĘJ���������ꍇ�ɂ����邻�̒��������Ԃ�1��������80���Ԃ��A���A��J�̒~�ς��F�߂���҂ł��邱�Ɓj�Y������J���ҁi�������w�Z���t)�ɑ��A��t�ɂ��ʐڎw�����s��Ȃ���Ȃ�܂��A���Ǝ҂͂��̖ʐڎw���̌��ʂɊ�Â��A���Y�J���҂̌��N��ێ����邽�߂ɕK�v�ȑ[�u�ɂ��Ĉ�t�̈ӌ����A��������Ă��ďA�Əꏊ�̕ύX�A��Ƃ̓]���A�J�����Ԃ̒Z�k�A�[��Ƃ̉̌����Ȃǂ̑[�u���u���Ȃ���Ȃ�܂���B����ɑ�66����8��3�ɂ��A���Ǝҁi���w�Z�ݒu�ҁj�́A�����J���ȗ߂Œ�߂���@�i���^�C���J�[�h�ɂ��L�^�A�p�[�\�i���R���s���[�^���̓d�q�v�Z�@�̎g�p���Ԃ̋L�^���̋q�ϓI�ȕ��@���̑��̓K�ȕ��@�j�ɂ��A�J���҂̘J�����Ԃ̏�c�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂����B
�@�����̋K�肪�d�v�Ȃ̂́A�����@�ɂ��Ւf���ʂ������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�����@�̏��F���̒��ł́A����4���ڂ������@�̔F�߂钴�ߋΖ��ł���A����ȊO�̊����͂��ׂċ��t�������I�ɂ���Ă��邱�Ƃɉ߂��Ȃ��Ƃ������O���ʗp�����Ƃ��Ă��A���ꂪ�J���҂̌��N�m�ۂ̊ϓ_����́u�J�����Ԃ̏v�ɊY�����Ȃ��Ƃ����킯�ɂ͂����܂���B���̌��ʁA�����Ȋw�ȓ��ǂ́A����ŋ����@�̘g�g�݂��ێ����A�����Œ���4���ڈȊO�̋Ɩ��ɏ]�����Ă��鎞�Ԃɂ��Ή�������Ȃ��Ȃ����̂ł��B
�@�Ȃ��A���������v�̖{�ۂł��������ԊO�E�x���J���̏���K���ɂ��ẮA�J����@��36���͌`���I�ɂ͓K�p����Ă�����̂́A�����@�ɂ��u���ۂɂ͓K�p�̗]�n���Ȃ��Ȃ�v�Ɖ�����Ă��邽�߁A���ړI�Ȗ@�I�e���͂���܂���ł����B�������A���̏���K�����J�Еی��ɂ�����ߘJ���F���̐����ł���ȏ�A�ԐړI�ȃC���p�N�g���������̂͂����܂ł�����܂���B
�@
�P�Q�@2019�N�����@����
�@
�@��������2017�N7���A�����Ȋw�Ȃ̒�������R�c��Ɋw�Z�ɂ����铭�������v���ʕ���݂����A2019�N1���Ɂu�V��������̋���Ɍ����������\�Ȋw�Z�w���E�^�c�̐��̍\�z�̂��߂̊w�Z�ɂ����铭�������v�Ɋւ��鑍���I�ȕ���ɂ��āv�\����ƂƂ��ɁA�����Ȋw�Ȃ́u�����w�Z�̋��t�̋Ζ����Ԃ̏���Ɋւ���K�C�h���C���v�����\���A�w�Z�ɂ����铭�������v���i�{�����ݒu����܂����B
�@�����A�Ȃ܂������@�Ŏ��ԊO�E�x���J������36�����37���̈ᔽ�ɂȂ�Ȃ��悤�Ȏd�g�݂ɂ��Ă��܂������߂ɁA������ǂ����邩���Y�܂������ƂȂ�܂��B�f���ɍl����A�u�����@������������ŁA36����̒����⒴��4���ڈȊO�́u�����I�Ζ��v���܂ޘJ�����Ԃ̏���ݒ�A�S�Ă̍Z���Ζ��ɑ��鎞�ԊO�Ζ��蓖�Ȃǂ̎x���v�������Ƃ��ׂ��Ƃ���ł����A���\�͂����܂ł������@�̊�{�I�g�g�݂�O��Ƃ��āA�u�����w�Z�̋��t�̋Ζ����Ԃ̏���Ɋւ���K�C�h���C���v�ł����čݍZ���ԓ��̏k���Ɏ�g�ނƂ����X�^���X�ł��B
�@���́u�K�C�h���C���v�́A����4���ڈȊO�̎����I�Ζ����s�����Ԃ��܂߂āA�ݍZ���ԃv���X�������k�̈������Z�O�Ζ����ԁi�ݍZ���ԓ��j�̏���̖ڈ����������̂ŁA1����45���ԁA1�N360���ԁA����ŔN720���ԁA���̏ꍇ1����100���Ԗ����ȂǁA��{�I��2018�N�����J����@�ɉ����Ă��܂��B�������A�ݍZ���Ԏ��̂��@�I�T�O�ł͂Ȃ��A�K�C�h���C�����@�I�S���͂͂���܂���B����ψ���͂��ꂼ��K�C�h���C�����Q�l�ɂ��ĕ��j�����肵�A�Ɩ��̖������S��K�����A�K�v�Ȋ������Ɏ��g�ނ��ƂƂ���Ă��邾���ł��B
�@�ł͘J�����ԋK���ɂ��Ă͉������Ȃ��̂��Ƃ����ƁA��Ⓜ�˂�1�N�P�ʂ̕ό`�J�����Ԑ��̓������ł��o����Ă��܂��B�w�Z�ɂ͉ċx�݂Ȃǎ������k�̒����x�Ɗ��Ԃ��������A�w�����E�w�N���ɂ͐��я�����w���v�^�L���ŖZ�����A�܂��w�Z�s���╔�����̎����̎����������ԋΖ��ɂȂ肪���Ȃ̂ŁA�N�Ԃ�ʂ����Ɩ��̂�����ɒ��ڂ��Č������悤�Ƃ������̂ł��B�������A���s�n���������@�́i�J�g����ɂ��j1�N�P�ʂ̕ό`����K�p���O���Ă���̂ŁA���\�͒n�������c�̂̏���K�����Ɋ�Â������x���ł���悤�ɂ��ׂ��ƒ�N���Ă��܂��B
�@���̓��\���āA�����Ȋw�Ȃ�2019�N10���A�����@�̉����Ă��o���A���@�Ă͓��N12���ɐ������܂����B����ɂ��A�����@��7���ɑO�q�̃K�C�h���C���̍����K�肪�u����܂����B
�i����E���̋Ɩ��ʂ̓K�ȊǗ����Ɋւ���w�j�̍��蓙�j
��7���@�����Ȋw��b�́A����E���̌��N�y�ѕ����̊m�ۂ�}�邱�Ƃɂ��w�Z����̐����̈ێ�����Ɏ����邽�߁A����E�������K�̋Ζ����ԋy�т���ȊO�̎��Ԃɂ����čs���Ɩ��̗ʂ̓K�ȊǗ����̑�����E���̕������ē��鋳��ψ������E���̌��N�y�ѕ����̊m�ۂ�}�邽�߂ɍu���ׂ��[�u�Ɋւ���w�j�i�����ɂ����ĒP�Ɂu�w�j�v�Ƃ����B�j���߂���̂Ƃ���B
2�@�����Ȋw��b�́A�w�j���߁A���͂����ύX�����Ƃ��́A�x�Ȃ��A��������\���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�����ɂ́u����E�������K�̋Ζ����ԋy�т���ȊO�̎��Ԃɂ����čs���Ɩ��̗ʂ̓K�ȊǗ��v�Ə�����Ă���A�u����ȊO�̎��ԁv�͂����܂Ő��K�̋Ζ����Ԃł͂Ȃ������I�Ζ��ɉ߂��Ȃ��Ƃ������O���ێ�����Ă��܂��B�O�q�̂悤�ɁA�����w�Z���t�ɂ��J����@�͌����K�p����Ă���A���ɂ��̍������Ȃ���32���͂��̂܂ܓK�p����Ă���̂ł�����A�����́u�J�����ԁv�̉��߂͈�ʖ��Ԋ�Ƃɂ�����u�J�����ԁv�̉��߂ƂȂ��ς��͂Ȃ��͂��ł��B��q�̂悤�Ȓ���4���ڈȊO�͎����I�Ζ��ł���J�����Ԃł͂Ȃ��ȂǂƂ������߂��A�������������w�Z���t�ȊO�̘J���҂ɂ�������߂Ɛ����������邩�ǂ����́A�ˑR�Ƃ��ĕs��ɕt����Ă���悤�ł��B
�@�܂����̉����ɂ��A1�N�P�ʂ̕ό`�J�����Ԑ����A�ߔ����g�����͉ߔ�����\�҂Ƃ̋���ł͂Ȃ��A���ɂ���ē������邱�Ƃ��ł��邱�ƂƂȂ�܂����B�}�X�R�~���ł͂��ꂪ�ő�̖��_�ł��邩�̂悤�ɕ����������܂������A��ʖ��Ԋ�Ƃł��J�g����œ����ł��鐧�x�ł���A�J�����Ԃ��ۂ������m�ɂ���Ă������A�ό`�����̂������Ƃ����b�ł͂���܂���B���̍����͋����@�ɂ���A�Ƃ�킯����4���ڈȊO�͎����I�Ζ�������J�����ԂɔƂ����c���߂��ێ��������Ă���_�ɂ�������Ǝv���܂��B
�@
�P�R�@��ʌ������̒n�فE���ٔ���
�@
�@�����������ŁA���߂Ă��̖������g���b�L�[�Ȍ`�Ŗ₢�������̂���ʌ������ł����B�������ܒn�ق̔�����2021�N10��1���A�������ق̍T�i�R������2022�N8��25���ɏo����A���ݍō��قɏ㍐���ł��B
�@��ʌ��̎������w�Z�̋��t�ł����������́A���ԊO�J���ɑ��銄�������̎x�������߂đi�����̂ł����A���̗����̗��ĕ����ЂƂЂ˂肳��Ă����̂ł��B
�i�����̎咣�j
�A�@�����@�́A����E���i���@2��2���B�ȉ��u�����v�Ƃ������Ƃ�����B�j�ɑ��Ď��ԊO�Ζ��蓖���x����Ȃ��|���߁A�J��@37����K�p���Ȃ����̂Ƃ��Ă��邪�A�ȉ��̋����@���̒�߂ɂ��A����E���ɓ������K�p����Ȃ��̂́A����15�N����2���C����j�܂łɌf����ꂽ���ڂɌW��Ɩ��i�ȉ��u����4���ځv�Ƃ����B�j�ɂ��Ă̎��ԊO�Ζ����߂��������ꍇ�Ɍ����A����ȊO�̋Ɩ��ɂ��Ď��ԊO�Ζ����߂�����ɏ]�������ꍇ�ɂ́A�����ǂ���J��@37�����K�p�������̂Ɖ����ׂ��ł���B
�@���Ȃ킿�A�����@6��1���y�ѕ���15�N���߂́A����E���ɑ��Ă͌����Ƃ��Ď��ԊO�Ζ��𖽂��Ȃ����̂Ƃ��A���ԊO�Ζ��𖽂���ꍇ�ɂ́A����4���ڂɏ]������ꍇ�ł����ėՎ����ً͋}�̂�ނȂ��K�v������Ƃ��Ɍ�����̂Ƃ��Ă���B�����O��Ƃ��āA���@3���́A����E���ɑ��Ă͋��E�����z���x�����i1���j�A���ԊO�Ζ��蓖�y�ыx���Ζ��蓖���x�����Ȃ����Ɓi2���j�Ƃ��Ă���A���@5��1���y�ѓ����ɂ��Ǒւ���̒n���@58��2���ɂ��A����E���ɂ͘J��@37����K�p���Ȃ����̂Ƃ��Ă���B�ȏ�̒�߂��炷��ƁA�����@�́A����4���ڂ̎��ԊO�Ζ��ɂ��ẮA���E�����z���x�����邱�Ƃɂ���āA���@32���⓯�@37���̋`���ᔽ�����Ȃ��Ƃ����Ɣ�����^�������̂Ɖ����ׂ��ł���B
�@�����ŁA����4���ڂɊY�����Ȃ��Ɩ��ɂ��Ď��ԊO�Ζ����߂����ꂽ�ꍇ�́A�����@����ɒ�߂��Ȃ����Ƃ��炷��ƁA�����ǂ���J��@���K�p����A���ԊO�Ζ����s�킹�邽�߂ɂ́A���@36��1���̒�߂�葱���K�v�ƂȂ�A���ԊO�Ζ��ɏ]�������ꍇ�ɂ́A���@37���ɂ�莞�ԊO���������̎x�����K�v�ƂȂ�Ƃ����ׂ��ł���B
�@�ȏ�̂��Ƃ��炷��ƁA�����@�́A����4���ڂɂ��āA���ԊO�Ζ����߂����ꂽ�ꍇ�ɂ̂݁A�J��@37���̓K�p��r�˂��Ă���̂ł����āA����ȊO�̋Ɩ��ɂ��Ď��ԊO�Ζ����߂����ꂽ�ꍇ�ɂ́A�����ǂ��蓯�����K�p�����Ƃ����ׂ��ł���B�����@�̐����|�ɋ���E���̒��ߋΖ��h�~���܂܂�Ă���ȏ�A���@���A��{����4�p�[�Z���g�ɂ����Ȃ����E�����z���x�����邱�Ƃ݂̂������āA�{���\�肳��Ă��Ȃ�����4���ڈȊO�̋Ɩ��ɌW�鎞�ԊO�Ζ��ɂ��Ă܂Ŏ��ԊO�Ζ��蓖�̎x����Ə����邱�Ƃ����e���Ă���Ƃ͓���������Ȃ��B
�@�v����ɁA�����@��̒���4���ځA���E�����z�̋K��ƁA�J����@��37���̓K�p���O�Ƃ͖��ڕs���̌��A��������Ƃ����O��ɗ����A����䂦����4���ڈȊO�̎��ԊO�J���ɑ��ẮA�K�p���O���ꂽ�͂��̘J����@��37�����h���ēK�p�����A�Ƃ����킯�ł��B�������Ƃ��Ă͒m�b��U��i���Ē�N���������������̂ł��傤���A�c�O�Ȃ��炻��͐��藧���Ȃ��Ǝv���܂��B���������A�i�����Ȃ̈ӂɔ����āj�J����@��36���͓K�p���O����Ȃ������̂ŁA����4���ڈȊO�̎��ԊO�J���́i���ɐ����Ă��铯���Ɋ�Â��j���ԊO�E�x���J������̒������K�v�ł���A����Ȃ��ɍs��ꂽ���ԊO�E�x���J���͘J����@��32���ᔽ�ɂȂ�Ƃ��������͏\�����藧�������Ǝv���܂����A�n���������@��58���3����ʂ��ĂȂ�̕��я������Ȃ��K�p���O����Ă��܂��Ă����37���͕����̂��悤���Ȃ��̂ł��B
�@���̂��Ƃ́A�����@�̖{�̋K��ƒn���������@��ʂ����J����@�̓ǂݑւ��K��Ƃ����ڕs���ł͂Ȃ����Ⴊ���݂��邱�Ƃ�������炩�ł��B���炭���|�I�ɑ����̐l�X�̖ڂɂ͉f���Ă��Ȃ��Ǝv���܂����A��q�̒ʂ�2003�N�̒n���Ɨ��s���@�l�@�ɂ���������^�̌�����w�@�l���ݒu����A���̕����w�Z�̋��t�́A�����w�Z�̋����Ƃ��ċ����@���K�p�����̂ŁA����4���ڂւ̌���⋳�E�����z�̎x���͋`���Â��������ŁA�������̐g����L���Ȃ����߂ɒn���������@��58���3���͓K�p���ꂸ�A�]���ē�����ʂ����J����@�̓ǂݑւ��K�����U��ƂȂ炴����A����䂦�ɘJ����@��33���3���ɂ�鎞�ԊO�E�x���J�����߂͕s�\�ł���A��36���ɂ�鎞�ԊO�E�x���J�����肪�s���ł���A��37���ɂ�銄�������̎x����Ƃ�邱�Ƃ͂ł��܂���B�����@�̖@�\�����̂��A���҂����ڕs���̌��A����L���Ă��Ȃ����Ƃ������Ă���̂ł��B
�@���ǁA���܂��ܒn���������̐g����L����Ƃ���̌����Ɋւ��邩����A����4���ڈȊO�̎��ԊO�E�x���J�����s�킹�����Ƃ������@�ᔽ�̖��������邱�Ƃ͊i�ʁA�܂��K�p���O����Ă��Ȃ�36���薳�����̖��������邱�Ƃ͂��蓾�Ă��A���Ȃ��Ƃ����S�K�p���O����Ă����37���Ɋ�Â����������̐����͕s�\�ł���ƌ��킴��܂���B
�@�J��Ԃ��܂����A����͌��������܂��ܒn���������̐g����L���Ă��邩��ł����āA����ȊO�̂����Ȃ闝�R�ɂ����̂ł�����܂���B���������������w�Z�̋��t�ł�������A�����w�Z�̋��t�ł�������A������w�@�l�����w�Z�̋��t�ł������肵����A���t�Ƃ��Ă̐E�ӂɂ͑S�����̈Ⴂ���Ȃ��ɂ�������炸�A�����̑i���͔F�߂��Ă����͂��ł��B
�@�������Ȃ���A�������ܒn�ق̍ٔ������������ق̍ٔ������A���̂悤�Ȑ[���˂����l�@�͈�Ȃ��܂܁A���炭����ψ�������o���ꂽ�����������l�����Ɋێʂ��ɂ���悤�Ȕ������������Ă��܂��B
��������̐E���́A�g�p�҂̕�I�w�����߂̉��ŘJ���ɏ]�������ʘJ���҂Ƃ͈قȂ�A�����E���k�ւ̋���I���n����A�����̎����I�Ȕ��f�ɂ�鎩��I�A�����I�ȋƖ��ւ̎�g�݂����҂����Ƃ����E���̓��ꐫ������ق��A�ċx�ݓ��̒����̊w�Z�x�Ɗ��Ԃ�����A���̊Ԃ́A��v�Ɩ��ł�����ƂɂقƂ�Ǐ]�����邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ����Ζ��`�Ԃ̓��ꐫ�����邱�Ƃ���A�����̐E���̓�����A��ʘJ���҂Ɠ����悤�Ȏ��J�����Ԃ���Ƃ��������ȘJ���Ǘ��ɂ͂Ȃ��܂Ȃ����̂ł���B�Ⴆ�A���Ƃ̏����⋳�ތ����A�����y�ѕی�҂ւ̑Ή����ɂ��ẮA�X�̋������A����I���n��w���^�c�̊ϓ_����A�����̋Ɩ����s�����ۂ��A�s�����̂Ƃ����ꍇ�A�ǂ̂悤�ȓ��e�������āA�ǂ̒��x�̏��������āA�ǂ̒��x�̎��Ԃ������Ă����̋Ɩ����s����������I�������I�ɔ��f���Đ��s���邱�Ƃ����߂��Ă���B���̂悤�ȋƖ��́A��i�̎w�����߂Ɋ�Â��čs����Ɩ��Ƃ́A���炩�ɂ��̐������قɂ�����̂ł����āA���K�̋Ζ����ԊO�ɂ��̂悤�ȋƖ��ɏ]�������Ƃ��Ă��A���ꂪ�����ɏ�i�̎w�����߂Ɋ�Â��Ɩ��ɏ]�������Ɣ��f���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̂悤�ɋ����̋Ɩ��́A�����̎���I�Ŏ����I�Ȕ��f�Ɋ�Â��Ɩ��ƍZ���̎w�����߂Ɋ�Â��Ɩ��Ƃ�����I�ɟӑR��̂ƂȂ��čs���Ă��邽�߁A����𐳊m�ɏs�ʂ��邱�Ƃ͍���ł����āA�Ǘ��҂���Z���ɂ����āA���̎w�����߂Ɋ�Â��Ɩ��ɏ]���������Ԃ�������肵�Č����Ɏ��ԊǗ����A����ɉ��������^���x�����邱�Ƃ͌��s���x���ł͎�����s�\�ł���i�����Ȋw�Ȃ̗ߘa2�N1��17���t���u�����w�Z�̋���E���̋Ɩ��ʂ̓K�ȊǗ����̑�����E���̕������ē��鋳��ψ������E���̌��N�y�ѕ����̊m�ۂ�}�邽�߂ɍu���ׂ��[�u�Ɋւ���w�j�v�k�����Ȋw�ȍ�����P���l�ɂ����Ă��A����E���̋Ɩ��ɏ]���������Ԃ�c��������@�Ƃ��āA�u�ݍZ�����ԁv�Ƃ����T�O��p���Ă���A�����ȘJ�����Ԃ̊Ǘ��͋��߂Ă��Ȃ��B�b82�j�B���̂悤�ȋ����̐E���̓��ꐫ�Ɋӂ݂�A�����ɂ́A��ʘJ���҂Ɠ��l�̒�ʓI�Ȏ��ԊǗ���O��Ƃ��������������x�͂Ȃ��܂Ȃ��Ƃ��킴��Ȃ��B
�@����画���ɂ��A�J����@��37���̓K�p���O�́u�����̎����I�Ȕ��f�ɂ�鎩��I�A�����I�ȋƖ��ւ̎�g�݂����҂����Ƃ����E���̓��ꐫ�v�ɂ����̂ł���A����䂦�u�����ɂ́A��ʘJ���҂Ɠ��l�̒�ʓI�Ȏ��ԊǗ���O��Ƃ��������������x�͂Ȃ��܂Ȃ��v�̂������ł��B�������������̐E���̓��ꐫ�́A�����܂ł��Ȃ������w�Z�⍑���w�Z�̋����ɂ�����͂��ł����A����画�����������ٔ����̖ڂɂ͔ނ�̑��݂��f���Ă��Ȃ������̂ł��傤���B�ߘa2�N�x�̊w�Z��{�����ɂ��A�����@�̑Ώۂɑ������鍂�Z�܂ł̋������́A�����w�Z��158,758�l�A�����w�Z��4,618�l�ł��B�����w�Z��834�C191�l�ɔ�ׂ�Ύ���Ȃ��Ƃ͂����A�������Ă������ł͂���܂���B
�@�������A���R�̂��ƂȂ���J����@���t���ɓK�p����Ă���ނ�ɂ��ẮA�J����ē@�ւ��@�ᔽ��e�͂Ȃ��E�����ɗ��܂��B2022�N8���Ɍ����J���ȘJ����NJēۂ����\�����u�ēw���ɂ������s���c�Ƃ̐������ʁi�ߘa3�N�x�j�v�ɂ́A�����s���c�Ƃ̉����̂��߂̎�g����Ƃ��Ď����w�Z�̃P�[�X���ڂ��Ă��܂��B
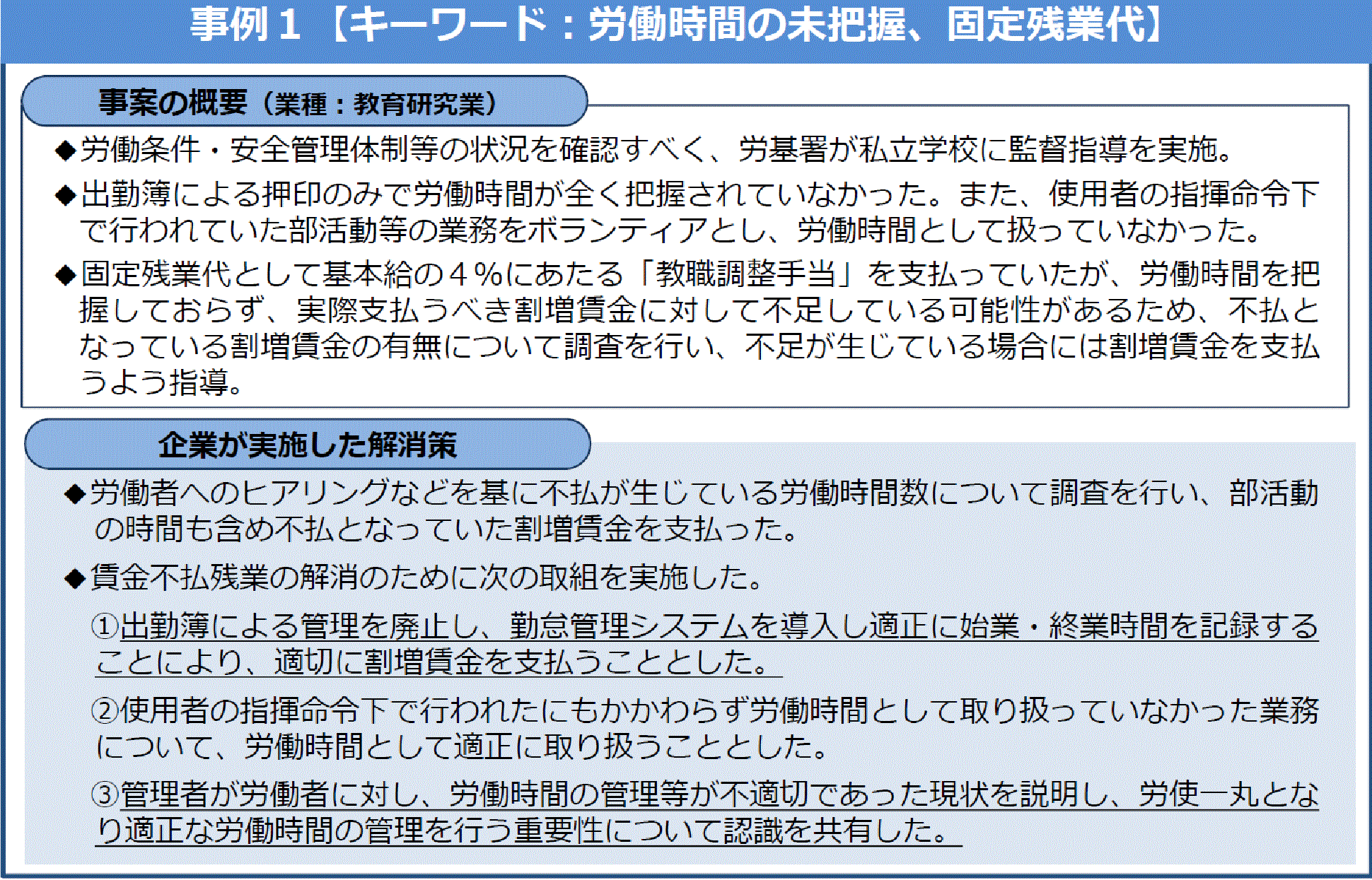
�@�����w�Z�ɂł��Ȃ��������4���̋��E�����z���A���ԊO����������Ȃ����������w�Z���A�������̎��Ԃ��܂߂ĕs�����c�Ƒ�킳��Ă��܂��B���s�@�㓖�R�̂��Ƃł͂���܂����A�������̎����w�Z�̌o�c�҂���L�������ܒn�قⓌ�����ق̔�������ǂ�ǂ��v���ł��傤���B�䂪�Z�̋��t�������A�u�����̎����I�Ȕ��f�ɂ�鎩��I�A�����I�ȋƖ��ւ̎�g�݂����҂����Ƃ����E���̓��ꐫ�v�͂Ȃ��ς�邱�Ƃ͂Ȃ��A�u�����ɂ́A��ʘJ���҂Ɠ��l�̒�ʓI�Ȏ��ԊǗ���O��Ƃ��������������x�͂Ȃ��܂Ȃ��v�̂ł͂Ȃ��̂��B�J����ē��̊ēw���͕s�����I�Ǝv���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����āA�����v���������w�Z���A��L�������������Ƃ��āA�E��Ƃ��Ă̋����ɂ͂Ȃ��܂Ȃ������������x���A�@���ɏ����Ă��邩��Ƃ����ĉ������Ă���͈̂�@���ƌ����đi�����N���Ă�����A����画�����������ٔ��������͈�̂ǂ�������������������Ȃ̂ł��傤���B���炭�A����Ȃ��Ƃ͂�������]���ɕ����Ȃ������̂ł��傤
*8�B
�@
�P�S�@���E�Ƃ��Ă̋��t�ɂӂ��킵���J���@���̉\��
�@
�@���āA�������A��ł����Ǝ��������悤�ɁA�����@���莞�̐l���@�̈ӌ��̔w�i�ɂ́A���ăW���u�^�Љ�̃v���t�F�b�V���i���ȋ��t�����Ɠ��l�A���Ƃ��������̐��s���ׂ��E���ł���悤�ȁA����䂦���Ǝ��Ԃ������Ζ����Ԃł���悤�ȁA���̂悤�Ȃ���ׂ��Љ�̎p���������Ă��܂����B��������Ɛ����C�f�I���M�[�I�ȋ��t���E�_�ƕ���킵���ڂŌ����邱�Ƃ��������Ƃ͂����A���̎v�z���ꎩ�̂͐^���Ȍ����ɒl���܂��B
�@�����āA�����@���蓖���͐��E�Ƃ��Ă̑�w�����ɂӂ��킵���J�����Ԑ��x�ȂǑ��݂����A������̍ٗʘJ�������C����Ă����ɉ߂��Ȃ������̂ɑ��A���̌�J����@��ɐ��Ɩ��^�ٗʘJ�������K�肳��A�u�`���̎��Ƃ̎��Ԃ�1�T�Ԃ̏���J�����Ԃ̔����ȉ��̑�w�����͐��Ɩ��^�ٗʘJ�������K�p�����悤�ɂȂ��Ă��܂��B�w�ȒS�C����ȖڒS�C���̒��w�Z�⍂�Z�ł́A���̐��x��K�p����]�n�̂��鋳�t�͑��݂�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������A�����ɖc��Ȋw�Z������k�w���A���������X���������Ă��鋳�t�����ɂ��̂܂ܓK�p���邱�Ƃ͂��蓾�܂��A�����̂���ׂ��w�Z�̎p�A���t�̎p�Ƃ��āA�����������E�Ƃ��Ă̋��t�ɂӂ��킵���J���@���̉\����T���Ă������Ƃ��A�l�����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�����܂ł��Ȃ��A���̍ۂɂ́A�������ł��邩�Ȃ����ȂǂƂ����E��̐����ɂ͂Ȃ�̊W���Ȃ��G���ɔς킳��邱�ƂȂ��A���t�̐��m�ȈӖ��ɂ����āu�܂��߁v�Ɍ�������Ȃ���Ȃ�܂���B
*1�n�ӏ͕ҏW��\�w���{���@�����S�W�J����@�x(2)�M�R��p749�`
*2�ȉ��e�߂ɂ킽��A����~�w���E���̋��^���x�ڐ��x�鍑�n���s���w��(1957�N)�A�����O�����Y�w���E���̋��^�x�w�z���[(1966�N)�A�����P�O�w���t�̌����Ƌ`���x���@�K(1966�N)�A�{�n�ΊďC�E�����ȏ�����������Ǔ��������^������Ғ��w����E���̋��^���ʑ[�u�@����x���@�K(1971�N)���Q�ƁB
*3���́u�E�������x�v�����̖��ɒl���Ȃ����̂ł��������Ƃ́A�_���j��Y�u�E�K���|�W���u�^���������x�̒���ƍ��܁v�i�w�G���J���@�x2020�N�t���i268���j�j�Q�ƁB
*4���{���E���g���ҁw�����g�O�\�N�j�x�J������Z���^�[(1977�N)p425�`�B
*5�s�쏺�߁u�����@�̖��_�v�w�W�����X�g�x485��(1971�N8��)�B
*6�Q�c�@�����ψ���1971�N5��20���B
*7�Q�c�@�����ψ���A1971�N5��21���B
*8���͋����@���蓖�����A�����w�Z�̋��t�̂��Ƃ�N���c�_���Ȃ������킯�ł͂���܂���B1971�N4��23���O�c�@�����ψ���Ŏ����}�̉��菁�c���́A�u�������̐搶�ɂ͂������������Ύ蓖���x�������z���x�ɉ��߂���B�Ƃ��낪�A�����̐搶�����ɂ͈ˑR�Ƃ��ĘJ����@�̓K�p�������āA�ǂ����Ă����Ζ��߂��o����25���̒��Ύ蓖���܂�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����͂ǂ������ӂ��ɍl�����邩�v�Ɩ₤�Ă��܂��B
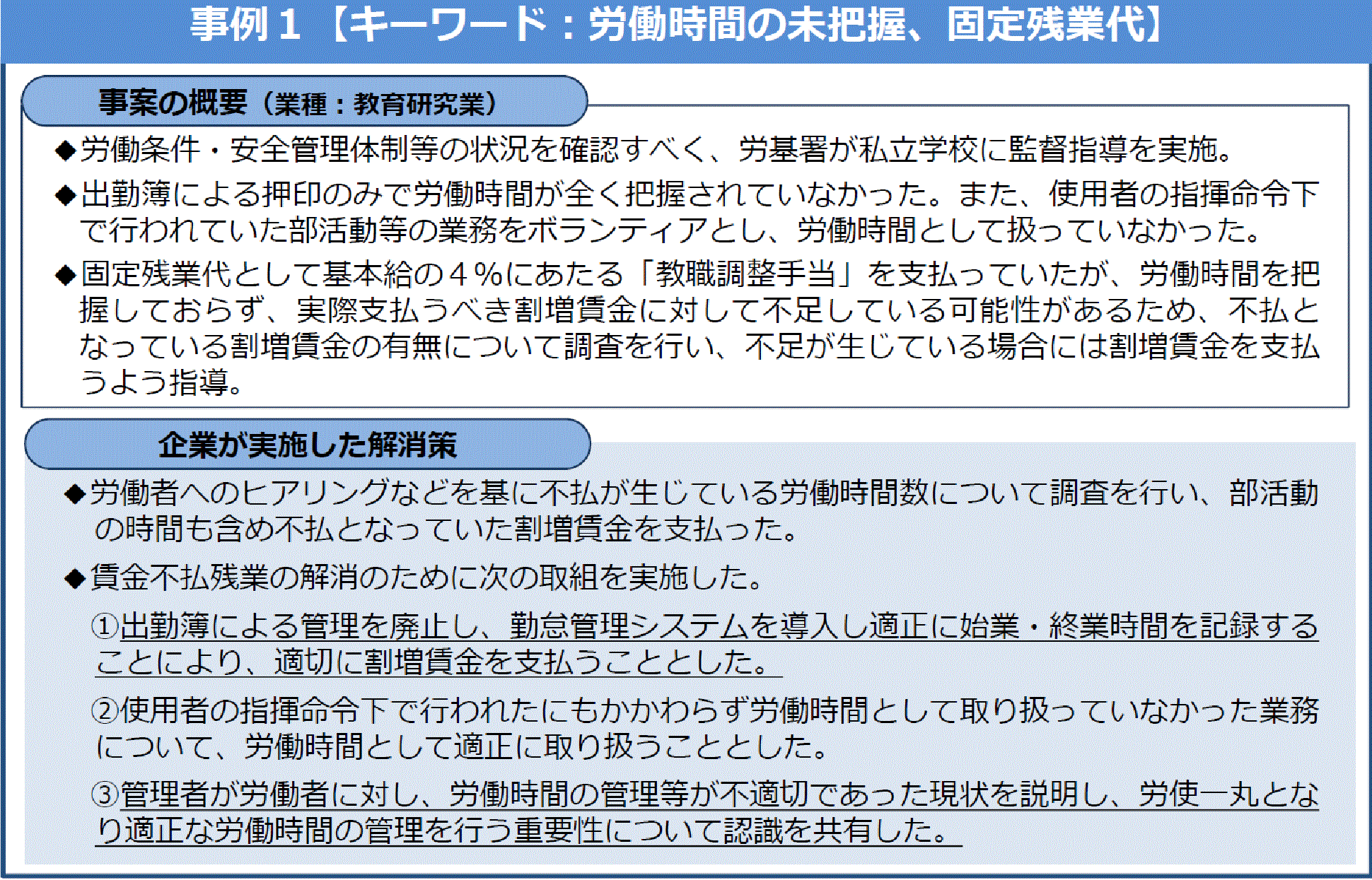 �@�����w�Z�ɂł��Ȃ��������4���̋��E�����z���A���ԊO����������Ȃ����������w�Z���A�������̎��Ԃ��܂߂ĕs�����c�Ƒ�킳��Ă��܂��B���s�@�㓖�R�̂��Ƃł͂���܂����A�������̎����w�Z�̌o�c�҂���L�������ܒn�قⓌ�����ق̔�������ǂ�ǂ��v���ł��傤���B�䂪�Z�̋��t�������A�u�����̎����I�Ȕ��f�ɂ�鎩��I�A�����I�ȋƖ��ւ̎�g�݂����҂����Ƃ����E���̓��ꐫ�v�͂Ȃ��ς�邱�Ƃ͂Ȃ��A�u�����ɂ́A��ʘJ���҂Ɠ��l�̒�ʓI�Ȏ��ԊǗ���O��Ƃ��������������x�͂Ȃ��܂Ȃ��v�̂ł͂Ȃ��̂��B�J����ē��̊ēw���͕s�����I�Ǝv���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����āA�����v���������w�Z���A��L�������������Ƃ��āA�E��Ƃ��Ă̋����ɂ͂Ȃ��܂Ȃ������������x���A�@���ɏ����Ă��邩��Ƃ����ĉ������Ă���͈̂�@���ƌ����đi�����N���Ă�����A����画�����������ٔ��������͈�̂ǂ�������������������Ȃ̂ł��傤���B���炭�A����Ȃ��Ƃ͂�������]���ɕ����Ȃ������̂ł��傤*8�B
�@�����w�Z�ɂł��Ȃ��������4���̋��E�����z���A���ԊO����������Ȃ����������w�Z���A�������̎��Ԃ��܂߂ĕs�����c�Ƒ�킳��Ă��܂��B���s�@�㓖�R�̂��Ƃł͂���܂����A�������̎����w�Z�̌o�c�҂���L�������ܒn�قⓌ�����ق̔�������ǂ�ǂ��v���ł��傤���B�䂪�Z�̋��t�������A�u�����̎����I�Ȕ��f�ɂ�鎩��I�A�����I�ȋƖ��ւ̎�g�݂����҂����Ƃ����E���̓��ꐫ�v�͂Ȃ��ς�邱�Ƃ͂Ȃ��A�u�����ɂ́A��ʘJ���҂Ɠ��l�̒�ʓI�Ȏ��ԊǗ���O��Ƃ��������������x�͂Ȃ��܂Ȃ��v�̂ł͂Ȃ��̂��B�J����ē��̊ēw���͕s�����I�Ǝv���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����āA�����v���������w�Z���A��L�������������Ƃ��āA�E��Ƃ��Ă̋����ɂ͂Ȃ��܂Ȃ������������x���A�@���ɏ����Ă��邩��Ƃ����ĉ������Ă���͈̂�@���ƌ����đi�����N���Ă�����A����画�����������ٔ��������͈�̂ǂ�������������������Ȃ̂ł��傤���B���炭�A����Ȃ��Ƃ͂�������]���ɕ����Ȃ������̂ł��傤*8�B