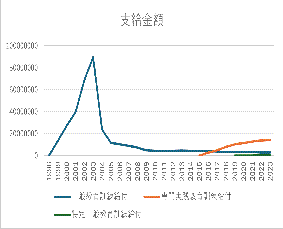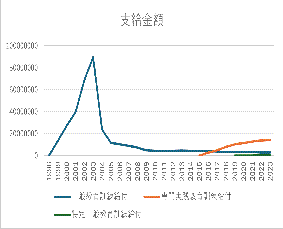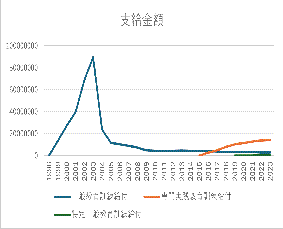『労務事情』2025年2月1日号
連載「数字から読む日本の雇用」第32回
「専門実践教育訓練給付受給者数98,786人」
昨年の雇用保険法改正は、メインの週10時間以上労働者への適用拡大のほかにもいくつか改正点がありますが、その中の教育訓練給付の改正は、専門実践教育訓練を受けて資格取得し、賃金が5%以上上がった場合の給付率の最高限度を80%にするもので、近年政府が音頭をとっているリスキリング政策の目玉ですが、この80%という給付率は、今から四半世紀前に教育訓練給付が創設されたときの給付率に戻ったという面もあります。
もともと、自己啓発支援という触れ込みで1998年に創設された教育訓練給付は、かかった費用の80%を雇用保険財政から支援する大盤振る舞いの制度でしたが、対象講座が余りにも広範に指定され、初歩的な英会話教室やパソコン教室のような、就職時に求められる職業能力という観点からみてどうかと思われるようなものまで含まれていたために批判を受け、雇用保険財政の急激な悪化もあって、2003年改正で40%に、2007年改正で20%にまで引下げられました。
ところが第2次安倍内閣で「学び直し」が掲げられると、2014年改正により「専門実践教育訓練給付」が設けられ、文部科学省所管の専修学校や専門職大学院、経済産業省所管の情報通信技術講座など特定の課程については、給付率を原則40%、資格取得して就職すれば60%にまで引上げられました。その後、給付率が70%、80%と引上げられていくとともに、専門実践教育訓練と一般の教育訓練の間に「特定一般教育訓練給付」も設けられ、40%の給付率となっています。また今回の改正では教育訓練休暇給付金も創設されています。
このように複雑化してきた教育訓練給付の推移を、受給者数と支給金額で見ると次のグラフのようになります。2003年度には受給者数約47万人、支給金額約900億円にまで膨れ上がっていた一般教育訓練給付はその後徐々に減少していったのに対し、新興の専門実践教育訓練給付は受給者数も支給金額も急速に増大し、2023年度には受給者数98,786人に達し、支給金額も144億円に近づいています。ただ、文科省や経産省の教育訓練に雇用保険がお金を出すというこの仕組みが、どれだけ日本の労働者のリスキリングに貢献しているのか、EBPMが謳われているわりに、明確なデータはないようです。