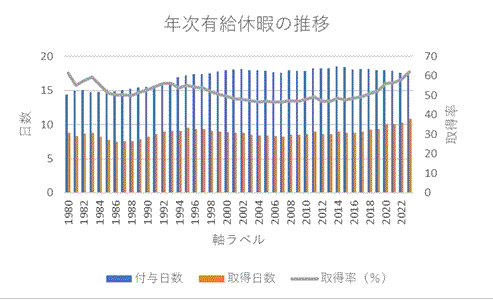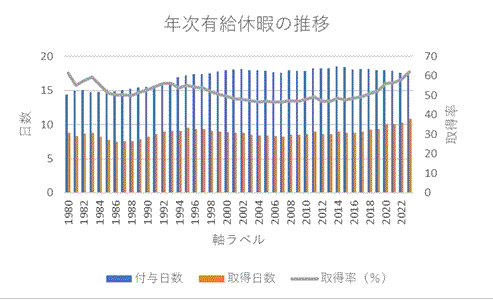『労務事情』2025年4月1日号
連載「数字から読む日本の雇用」第34回
「年次有給休暇取得率65.3%」
2024年12月に発表された令和6年就労条件総合調査によると、企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)をみると、労働者 1 人平均は 16.9 日で、このうち労働者が取得した日数は 11.0 日であり、取得率は 65.3%となっています。この年次有給休暇取得率は、統計を取り始めた1980年以来最高の数字です。
年次有給休暇取得率は長らく50%台で低迷していましたが、21世紀に入る頃から50%すら割り込むようになり、2017年まで40%台を推移していましたが、2018年からようやく50%台に復帰し、2023年には62.1%、2024年には65.3%とかなりの増勢を見せています。
そもそも日本の年次有給休暇制度は、法律上は労働者の時季指定権という形で規定されていますが、これは裏を返すと労働者が自ら積極的に年休を取ると言い出さない限り、使用者側が黙っていて取らないままになってしまっても、年休付与義務違反にはならないということを意味していました。そのため、長らく取得率は50%台を低迷していたのです。こてをなんとかしようと、1987年改正で労使協定による計画的付与制度が導入され、2008年改正では時間単位取得制度が導入されましたが、取得率の推移のグラフを見る限り、その効果はほとんどなかったようです。むしろ21世紀には40%台を低迷していました。
取得率が再び50%台になった2018年は、働き方改革によって使用者による年次有給休暇の時季指定義務が盛り込まれた年です。これは、1954年の省令改正で削除された使用者による時季聴取義務が形を変えて復活した面があり、ようやく本来の年次有給休暇制度に近い姿に、部分的にではありますが戻ったと言えます。その後の取得率の急上昇はその成果が現れているのかも知れません。