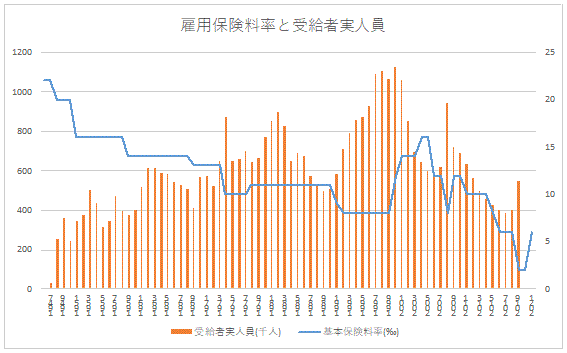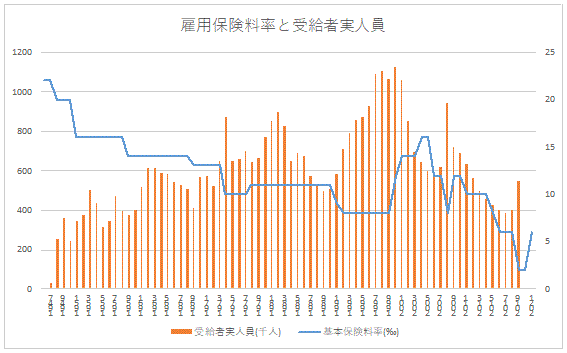東京都社会保険労務士会『社労士TOKYO』2022年6月号
「雇用保険の歴史」
現在の雇用保険法が失業保険法という名前で制定されてから75年が経ちました。広範かつ膨大なその歴史を数ページでまとめることはほぼ不可能ですが、今年の改正の中心が保険料率であったことから、そこを糸口としつつ給付のあり方を概観していきたいと思います。まず、法制定以来の保険料率(雇用保険法以後は失業等給付の保険料率)と受給者実人員の推移をみましょう。びっくりするのは、制定当時の2.2%(これを労使折半、以下同じ)が、2020年度には前年の0.6%からたった0.2%にまで下がっていたことです。もっとも、これは育児休業給付が独立して0.4%の保険料率となったからですが、コロナ禍がまさに襲いかかろうとしていたその時に、極限まで保険料率を下げようとしていたというのは、この上ない皮肉です。
・失業給付のセーフティネットとモラルハザード
さて、雇用保険の歴史は、そのセーフティネット機能とモラルハザードの抑制とのせめぎ合いの歴史でした。これはその保険事故である「失業」という概念に特殊性があるからです。失業には労働の意思と能力という主観的要件が含まれ(これがなければ「無業」であって、失業ではない。)、とりわけ労働の意思は外部から客観的に判断することが困難です。それゆえ、失業保険制度は本質的にモラルハザードの危険性が高く、これを防止するための制度設計上の工夫が必要となるのです。
1947年11月に制定された当時の失業保険は極めて簡素な作りで、受給要件は6か月以上の被保険者期間、給付日数は一律に180日でした。ということは、半年働けば半年受給できるということです。そのため、失業保険はデカンショ保険(「デカンショ、デカンショで半年暮らす、後の半年は寝て暮らす♪」)と呼ばれて批判の的となり、1955年8月に給付日数を被保険者期間に応じて段階化する改正が行われました。
継続雇用期間
(被保険者期間) |
1年未満 |
1年以上
5年未満
|
5年以上
10年未満
|
10年以上
|
9月以下 |
10月以上 |
給付日数
|
90日
|
180日
|
180日
|
210日
|
270日
|
ところが1974年12月の雇用保険法への改正により、被保険者期間に応じた仕組みは私保険的だからと止めてしまい、代わりに就職の難易度に応じて定めるべきだとして年齢階層別になりました。
|
|
離職日の年齢
|
30歳未満
|
30歳以上
45歳未満 |
45歳以上
55歳未満 |
55歳以上
|
給付日数
|
90日
|
180日
|
240日
|
300日
|
|
ところが10年後の1984年7月の改正でまた被保険者期間が復活しました。年齢と被保険者期間の2軸によるマトリックスです。また、自己都合離職者には3か月の給付制限期間を設け、さらに所定給付日数を半分以上残して再就職した者には再就職手当を出すことにしました。こういうことになるのは、失業保険のモラルハザードが、あちらをなくそうとするとこちらで増えるという困難な性質があるからです。被保険者期間で差を付ければ就職の容易な長期勤続者にモラルハザードが発生し、年齢で差を付ければ短期勤続の高齢者にモラルハザードが発生します。早期就職者に褒美を付ければ就職の容易な者にモラルハザードが発生し、付けなければ満額受給するまで居座るという形でモラルハザードが発生します。全てに対応しようとすれば制度は限りなく複雑化してゆくことになります。
給付日数がもっとも複雑化したのは2000年5月の改正です。2003年改正で消えた短時間労働被保険者の軸を省略して3軸の表を示すと次の通りです。
離職理由
|
年齢
被保険者期間 |
30歳未満
|
30歳以上45歳未満 |
45歳以上60歳未満 |
60歳以上65歳未満 |
倒産・解雇等による離職者
|
1年未満 |
90日 |
1年以上5年未満 |
90日 |
90日 |
180日 |
150日 |
5年以上10年未満 |
120日 |
180日 |
240日 |
180日 |
10年以上20年未満 |
180日 |
210日 |
270日 |
210日 |
20年以上 |
- |
240日 |
330日 |
240日 |
自己都合等による離職者
|
1年未満/1年以上5年未満 |
90日 |
5年以上10年未満 |
120日 |
10年以上20年未満 |
150日 |
20年以上
|
180日
|
2000年改正の主な原因は、1990年代後半の金融危機等による失業者の急増でした。5兆円近くに達していた積立金が急減し、2001年度にはマイナスになると見込まれたため、真に必要な者に給付を重点化するという触れ込みで、自己都合離職者の給付日数に切り込んだのです。しかし、後述のように「自己都合」という概念にも問題が溢れていました。
この2000年改正は、それまで0.8%という低水準であった保険料率を1.2%に引き上げ、2003年改正はさらに1.6%に引き上げました。ところが2000年代半ばにいざなみ景気といわれる好況になり、2007年改正時には1.2%に下げ、さらに2008年には0.8%に下げるという動きになりました。2008年というのは御承知の通り、リーマンショックにより世界中が不況に陥っていった年です。年末の年越し派遣村をご記憶の方も多いでしょう。そんな時期になぜ引下げの話が持ち上がったのでしょうか。新聞報道等によれば、これは雇用保険への国庫負担をやめたい財務省が、積立金が余っているならばまずは保険料を引き下げるのが筋で、国庫負担だけをやめるわけにはいかないことから、麻生太郎首相に景気対策の一環として雇用保険料の引下げを進言したことによるということです。ところが、折からの雇用情勢の悪化により国庫負担の廃止は実現には至らず、結局保険料の一時的引下げだけが残さてしまいました。雇用情勢がこれから悪化しようというときに、その対策の原資となるべき雇用保険料を引き下げるという、顛倒した雇用政策となってしまったわけです。労政審雇用保険部会では労使双方から保険料率の引下げに対する疑念が示されましたが、事務局側としても内心不満を持ちながらでしょうが、政府の追加経済対策ですでに決まったことへの理解を求めています政策決定過程の愚劣さを示す好事例といえましょう。
保険料率が0.8%となった2009年度には受給者実人員も100万人近くに達しましたが、その後再び景気は回復して2017年度からは30万人台で推移し、積立金残高も6兆円を超え、保険料率も0.6%にまで下がっていたのが、コロナ禍勃発直前の2019年の状況です。未来を予測することは誰にもできないとはいえ、武漢で新たな感染症が発生しているらしいという情報が漏れてきた2019年12月に建議が出され、日本でも感染者が出始めた2020年2月に法案を国会に提出し、緊急事態宣言発出直前の3月に成立した法改正の中身が、失業等給付に係る保険料率を0.2%(労使が0.1%ずつ負担)に引き下げるというものであったというのは、皮肉としか言いようがありません。
・雇用調整助成金
1974年の雇用保険法への改正の最大の意義は、雇用保険3事業(現在は2事業)という形で雇用政策手段のための財源を確立したことです。0.3ないし0.35%の事業主負担を原資に、雇用安定、雇用改善、能力開発等のさまざまな助成金が設けられてきました。その中でも断トツに重要なのが雇用調整助成金(創設時は雇用調整給付金)です。石油ショック、リーマンショック、今回のコロナ禍と、休業を余儀なくされた企業の賃金負担をカバーしてきました。今回は支給要件を緩和するとともに、大幅に助成率を引き上げ(解雇を行わない中小企業は10/10)、受給額の上限を1万5千円に引き上げるという大盤振る舞いとなりました。もちろん、2020年前半の緊急時にはそれが必要だったのでしょうが、2022年の今日でもなおその特例措置が続けられ、支給件数も支給額も高止まりしています。似た雇用維持制度を有するドイツやフランスでは、受給者数が減少傾向にあるのと対照的です。
こうして、緊急雇用安定助成金と併せると2021年度末までで5兆5千億円が支給され、2019年度には1.5兆円あった雇用安定資金残高は2020年度から0となり、失業等給付の積立残高から3兆円以上の借り入れでしのぐ状況となりました。その失業等給付の積立残高も2019年度の4.5兆円から急速に目減りし、2020年6月の雇用保険臨時特例法により一般会計から1.7兆円繰り入れてしのぐ状況に追い込まれました。
そこで、ようやく2021年9月から労政審雇用保険部会で改正に向けた審議が始まり、翌2022年1月に報告がされ、3月に法改正に至りました。これにより、失業等給付に係る保険料率が弾力条項に基づき原則の0.8%から0.2%にまで引き下げられていたのを原則の0.8%に戻すのですが、ただし激変緩和措置として2022年9月までは0.2%、2023年3月までは0.6%とされています。これは2022年夏の参議院選挙をにらんだ政治的判断ということです。また雇用保険2事業の保険料率も原則の0.3%から0.35%に戻すこととしました。
・非正規労働者の適用問題
非正規労働者が雇用保険制度から排除されているという問題意識が噴出したのは、リーマンショックによる派遣切りが社会問題となった2008年でした。パートタイマーと派遣労働者は1年以上の雇用見込みがなければ雇用保険を適用しないという取扱いがなされていたからです。ところが、その時点では法令上にはそのような規定は存在しませんでした。通達(業務取扱要領)で「労働者」の解釈としてやっていただけで、臨時工や社外工と呼ばれるフルタイム直接有期雇用の非正規労働者は一貫して雇用保険の適用対象だったのです。
私は当時、この奇妙な取扱いの起源を探して、1950年1月の通達「臨時内職的に雇用される者に対する失業保険法の適用に関する件」(職発49号)に到達しました。ここでは「臨時内職的に雇用される者、例へば家庭の婦女子、アルバイト学生等であつて」「その者の受ける賃金を以て家計費或は学資の主たる部分を賄わない者、即ち家計補助的、又は学資の一部を賄うに過ぎないもの」「反復継続して就労しない者であつて、臨時内職的に就労するに過ぎないもの」は、「労働者と認めがたく、又失業者となるおそれがな」いので、「失業保険の被保険者としないこと」と指示していました。この発想がその後の通達や業務取扱要領に流れ込み、パートと派遣には1年以上の雇用見込みが要求されるようになっていたのです。
民主党政権下の2010年3月の改正により、それまで業務取扱要領で定めていた適用基準がようやく法律に明記されるようになり、①1週間の所定労働時間が20時間未満である者、②同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者、③季節的に雇用される者のうち、短期雇用特例被保険者に該当しない者、④学校の学生・生徒(定時制等を除く)を除き、適用されることとなりました。この時、昼間学生・生徒アルバイトが適用対象に入らなかったのは、主婦パートやフリーターと異なりなお家計補助的とみなされていたからでしょう。しかし、今回のコロナ禍では学生アルバイトの苦境が注目され、雇用調整助成金の対象に含められるとともに、文部科学省サイドでは学生支援緊急給付金を創設しました。セーフティネットをどこまで広げるべきであり、どこまで広げるべきではないのかが、社会の変化によって変わってくることを物語っています。
・自己都合離職の問題
最後に、1984年改正で3か月の給付制限がかかり、2000年改正で給付日数が大幅に削られた自己都合離職の問題に触れておきましょう。形式上は自己都合離職であっても、実際には低劣な労働条件やいじめ、嫌がらせなどさまざまな理由によってやむなく退職を強いられた、というケースが少なからずあります。もちろん、法令上はそれらに対してもきちんと手当がされています。雇用保険法施行規則36条には、倒産・解雇による離職に準じて特定受給資格者となるものとして、「明示された労働条件が著しく相違した」とか、「賃金が2カ月以上不払い」だとか、「賃金が85%未満に低下した」とか、「月100時間以上の残業があった」とか、直接間接に「退職勧奨を受けた」とか、かなり事細かに規定されています。
ところが最大の問題は、離職票を書くのは使用者側だということです。形の上では自己都合離職だけれども、その原因は使用者側にあるような場合、使用者側がちゃんとそう書いてくれるとは限りません。むしろ、ハローワークの窓口では、離職票を持ってきたら自己都合離職だから3カ月待たされて、しかも給付日数は3カ月だけだと知らされてトラブルになる例が少なくないのです。