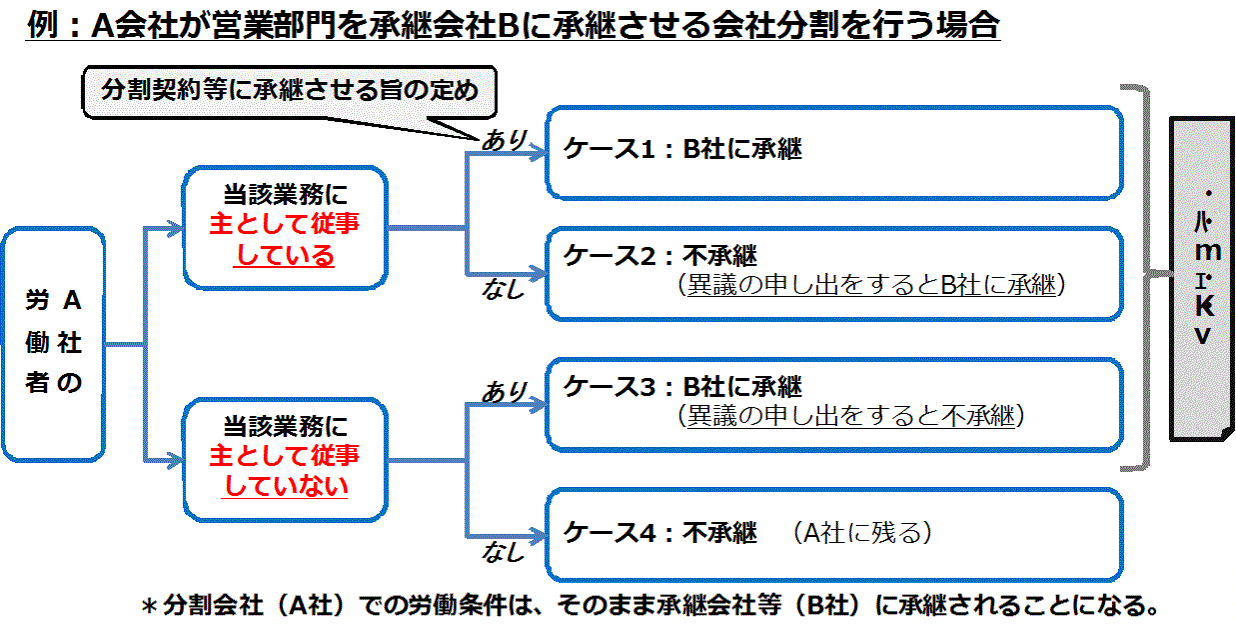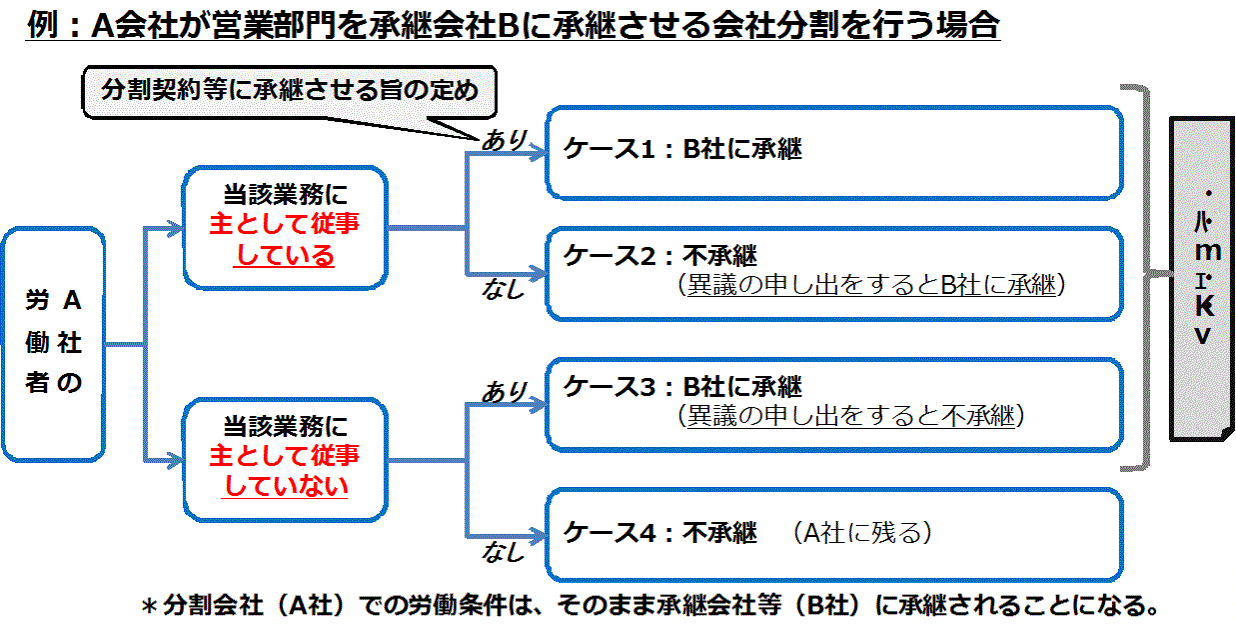第67回 組織変動と労働契約承継法
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
厚生労働省が昨年12月から開催していた「組織の変動に伴う労働関係に関する研究会」が、去る11月20日に報告書を取りまとめました。
※厚生労働省「組織の変動に伴う労働関係に関する研究会」報告書⇒資料(PDF)はこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000104902.pdf
この研究会は、当初医療法人や農協など会社以外の法人に分割法制が導入されるということで、急遽急きょ検討を行い、今年3月に中間とりまとめを行って、その結果が既に農協法や医療法の改正に盛り込まれていますが、その後は2005年の会社法制定や裁判例の蓄積を踏まえて、労働契約承継法の在り方についての検討を行ってきました。ここではもっぱら後者について解説します。
さて、労働契約承継法は2000年の商法改正に伴って作られた法律です。同改正は、それまで営業譲渡というやり方でしか行えなかった事業の移転を、会社分割というやり方でできるようにしたものです。営業譲渡は個別承継なので、他ほかの債権債務と同様に労働契約も個別労働者の同意が必要ですが、会社分割は部分的包括承継なので、分割計画書に基づいて権利義務がまとまって承継されます。労働契約も同様です。しかしそれでは、承継を望まない者が承継され、承継を望む者が紹介されないことが起こり得えますし、これまで従事してきた職務から切り離されてしまう可能性もあります。そこで、労働契約の承継に一定のルールを定めたのが労働契約承継法なのです。
その基本的な発想は、EUの企業譲渡指令と同様、労働者は職務と一緒に動くのが一番いい、というところにあります。ヨーロッパでは、労働契約は職務を限定して結ぶのが普通ですから、ある会社で自分がやっている仕事が分割されてほかの会社に行ってしまうのに、自分がそれから切り離されて元の会社に残されてしまうのが最大の悲劇になります。労働者にやらせるべき仕事がなくなったからといって、あっさり解雇されてしまいかねません。ですから、職務と一緒に労働者も移転するというのが大原則です。これは、会社分割にとどまらず、企業譲渡一般についても適用されます。それでこそ、労働者の雇用も安定します。移転が嫌だといって元の会社に残っても、雇用は保障されません。ジョブ型社会とはそういうものです。
日本では、労働契約で職務が限定されていないことが普通で、ある時点をとれば「主として従事している職務はこれだ」ということはできますが、それでも業務分担自体も結構曖昧なため、「主としてはこの職務に従事しているけれども、従としては別の職務に従事している」といったことも結構あります。また主として従事している業務といえども、それは会社から命じられたから従事しているだけであって、人事異動が発令されたら全然違う部署の仕事に回される――といったことも普通です。そういうメンバーシップ型社会に、ジョブ型社会で発達した労働契約承継のルールをなんとか持ち込もうとしたことから、労働契約承継法のルールはいささか複雑なものになりました。
概略は下図の通りですが、分割計画書の記載を基本としつつ、主に従事する職務を優先させる方向への修正を認める仕組みになっています。就職よりも就社が一般的な日本の雇用慣行を踏まえつつも、労働者からの異議申出権を職務優先の場合にのみ認めるという形で整理を図っているわけです。当時対案として出された野党法案は、行くも残るも労働者の意思次第という仕組みでした。ジョブ型とメンバーシップ型の両方の希望を全て満たそうとするとそうなるわけですが、それでは労使のバランスがとれません。どこかで線引きをするとなると、EU指令をベースにするしかなかったのでしょう。
もっともEU指令は上述の通り、一般の企業譲渡の場合でも職務と一緒に労働者も移転するというルールを厳格に適用しています。しかし日本では、従来から営業譲渡は個別承継だからという理屈で、原則は的に労働者は移転せず、個別に合意した場合だけ移転するという扱いです。日本でもタクシーや医療のように極めてジョブ型の世界もありますが、営業譲渡の原則がこうなので、逆にいろいろと問題が生じるもと元になっています。営業譲渡については、承継法成立後の2001年から2002年にかけて「企業組織再編に伴う労働関係上の諸問題に関する研究会」で議論されましたが、結局「現時点で立法措置は不要」という結論でした。日本では会社に所属するという意識が強いからという理由も挙げられていますが、それをいうなら会社分割でも同様のはずです。この問題も今回の研究会で引き続き取り上げられています。
※厚生労働省「企業組織再編に伴う労働関係上の諸問題に関する研究会報告取りまとめ」⇒資料はこちら
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0822-1.html
一方、メンバーシップ型社会にEU型の労働契約承継法を持ち込んだことによるトラブルとして、日本IBMアイ・ビー・エム事件(最高裁二小 平22.7.12判決)があります。日本IBMでハードディスク事業部門に従事していた労働者たちが、同部門が新設分割により設立された会社に承継された事案ですが、上の図の「ケース1」なので、承継拒否権はありません。問題になったのは商法改正法附則5条で求められている個別協議が果たされたかどうかで、本件では果たされたと判断しましたが、5条協議を全く行わなかったような場合には承継の効力に影響があると述べた部分が注目されました。法解釈学的にはそこがポイントでしょうが、法社会学的にはむしろ、EUであれば当たり前の主従事労働者が承継されたことに異議を唱(とな)えていることにこそ注目すべきでしょう。実際、労働契約承継法制定直前に筆者が連合に呼ばれてEU指令の解説をした時とき、そこに張り出されたタイトルは「気がつけば別の会社に」でした。事業が移転されたのに気がつけば元の会社に残されてしまうことこそ問題だと考えるヨーロッパの労働者とは、発想のベクトルが全く逆向きであることが分かります。
さて、労働契約承継法制定後の2005年、商法の中から会社関係部分が独立して「会社法」という法律ができるとともに、中身も大きく変わりました。会社分割についても、それまでは分割の対象が有機的一体性のある営業(事業)だったのが、「事業に関して有する権利義務の全部又は一部」となり、またそれまでは債務の履行の見込みがあることが前提だったのが、債務の履行の見込みがなくても分割できるようになりました。いわゆる「泥船分割」です。しかし、そのときには労働契約承継法は改正されず、指針で最小限の対応がされただけでした。今回の研究会の検討は、この会社法による新たな事態に対応すべきかどうかというのが最大の論点です。
今回の報告書によると、まず事業に当たらない権利義務の会社分割の場合について、①従来通り事業に主従事かどうかで判断し、事業たり得ない権利義務に従事していても非主従事と整理、②承継される権利義務に主従事か否かで判断、――の二つの立場を示し、雇用や職場の確保の観点から①が望ましいとしています。しかしこの場合、どの範囲が「事業」に当たるのかが問題になりますから、その判断基準を明確にすべきだとも述べています。その上で、今までは5条協議の対象は承継される事業に主従事及び従従事の労働者だけでしたが、通知の対象となる不従事労働者についても対象とすることが望ましいとしています。
次にいわゆる泥船分割の場合について、不採算事業に承継される労働者に何らかの保護が必要かを論じ、債務超過の状況についても7条措置(過半数組合/過半数代表者への協議等)の対象となることを明確に周知すること、5条協議の対象に含めることとする一方、不採算事業に承継される主従事労働者や不採算事業に残留する非主従事労働者にも異議申出権を付与すべきではないかという議論に対しては、承継法の趣旨から否定的な考えを示しています。ジョブ型社会を前提とすれば、泥船であろうがなかろうが労働契約にその職務が書き込まれているのですから当たり前の理屈です。しかし、日本のようなメンバーシップ型社会では、たまたま会社から人事命令で不採算部門への配置転換を命じられたために、その部門と運命をともにしなければならないというのは、不平不満をもたらす可能性があります。
本法関係でもう一つ問題となった裁判例が阪神バス事件(神戸地裁尼崎支部 平26.4.22判決)で、分割会社が主従事労働者に承継法に基づく通知等を行わず、転籍合意方式によって労働条件の不利益変更を行った事案です。報告書では、承継会社で労働条件を統一する必要があることなどから、転籍合意を一律に排除する必要はないとし、その上で転籍合意の場合でも5条協議や通知は省略できず、法律上労働条件を維持したまま承継できることを等を説明すべきと述べています。
因縁のある事業譲渡の問題ですが、今回の報告書では「将来の雇用の確保にもつながるような有用な組織再編への影響や全体としての雇用の維持の観点からも慎重な検討を要する」として、「事業譲渡に労働契約の承継ルールを設けることについては、未だいまだ慎重に考えるべき」としています。ここは理屈がもやもやとするところですが、おそらく21世紀に導入された会社分割に比べても、事業譲渡の場合には、日本的なメンバーシップ感覚からすると事業と一緒に労働者も動くということに対する抵抗感が強く、現実に問題が多発しているタクシーや医療などジョブ型の職域はまだまだ少数派であることが最大の原因ではないかと思われます。報告書案は、手続き面でのルールを整備することは考えられるとし、まずは例えば指針を定めて取り組みを促していくことを提案しています。
以上のように、報告書は法改正に至るような提案はなく、指針の一部改正を提起しているにとどまりますが、ここで論じられた問題は結構奥が深いものが多く、さらに突っ込んで検討していくことが望まれます。