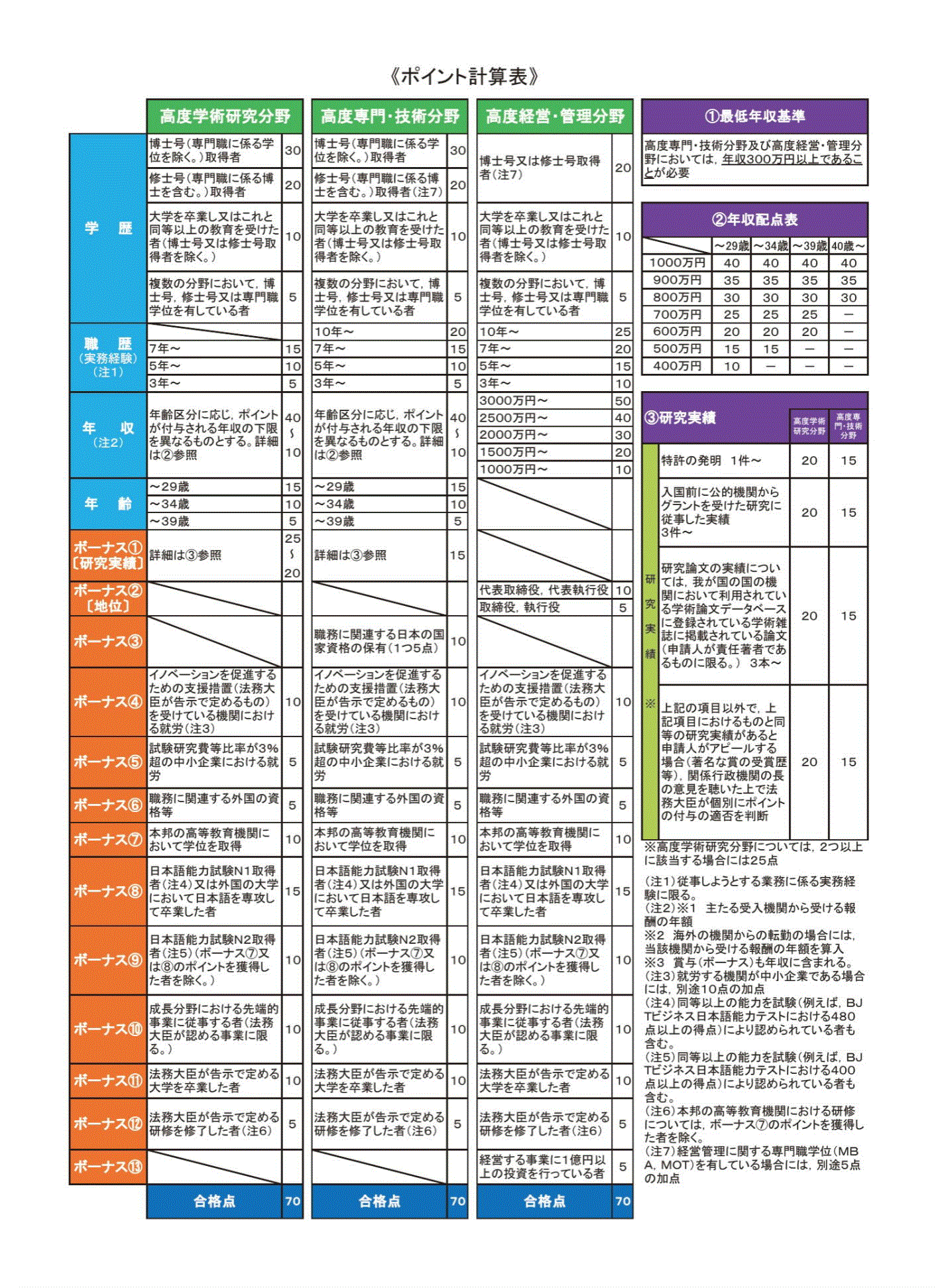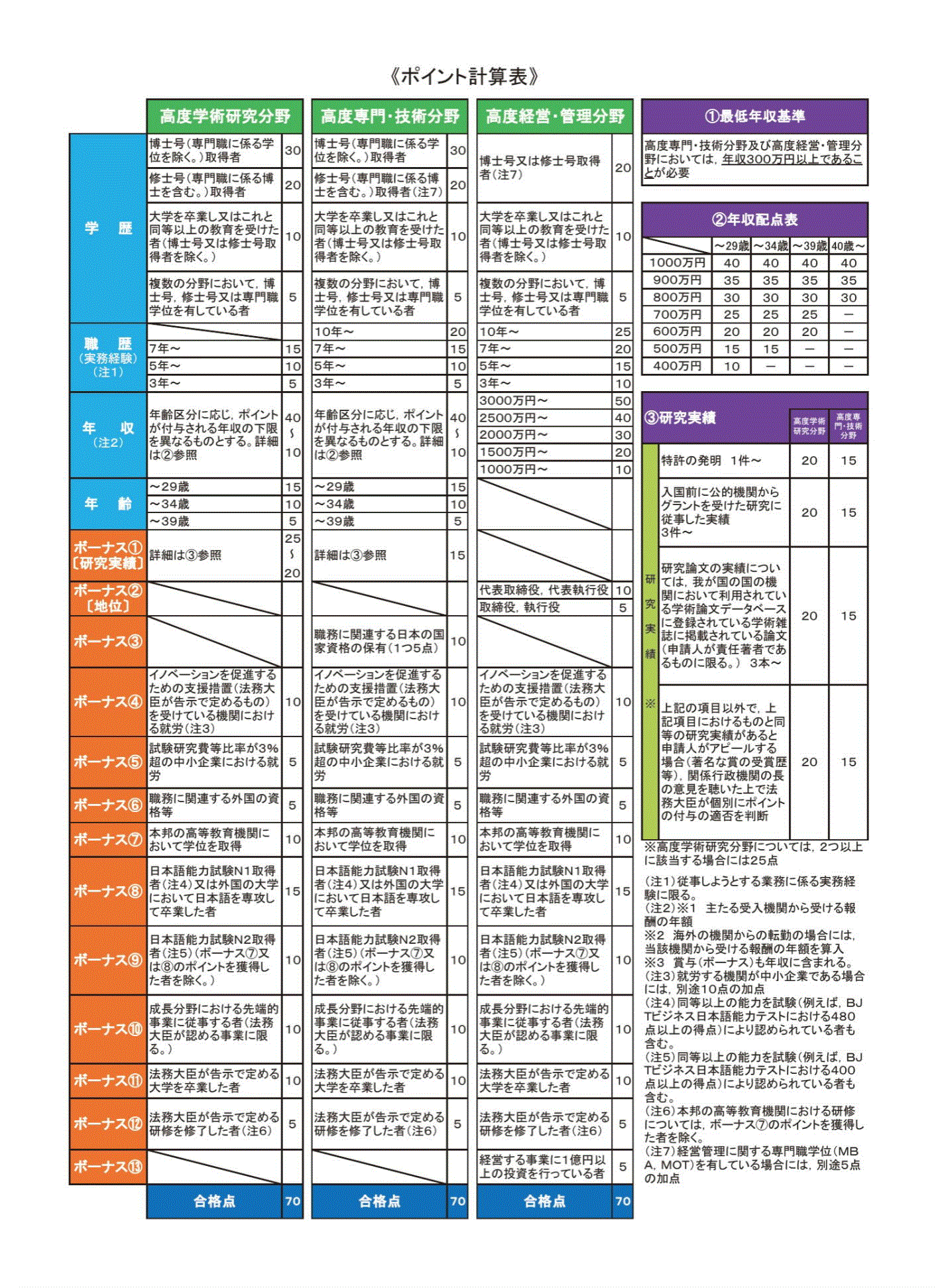第140回 外国人高度人材の虚実
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
労働政策研究所長
日本の外国人労働者政策は、過去30年にわたってフロントドアをほとんど閉ざしたまま、日系人2世・3世や研修生・技能実習生といったいわゆるサイドドアを広げることで対応してきたと指摘されています。そして、ようやく2018年入管法改正で導入された「特定技能」という在留資格によって、高度専門職でない一定の技能労働者の正面からの導入が始まったことは周知のとおりです。
では、これまでも積極的に受け入れるという方針であった専門的・技術的分野の外国人労働者受け入れ政策はどこまでしっかりとしたものなのでしょうか。今回はその経緯を概観しておきましょう。
まず、以前から専門的・技術的分野の外国人は積極的に受け入れるという方針がありましたが、2007年6月の雇用対策法改正により「高度の専門的な知識又は技術を有する外国人(中略)の我が国における就業を促進する」ことが国の施策として明記されたことが重要です(第4条第1項第10号)。その後の2008年7月、内閣府に高度人材受入推進会議が設置され、実務作業部会で議論した上で、2009年5月「外国高度人材受入政策の本格的展開を」と題する報告書をまとめました。同報告書はアメリカのグリーンカード制等を参考に、ポイント制導入による高度人材優遇制度の創設を求めています。これは2010年6月の新成長戦略に盛り込まれました。
これに対し、厚生労働省は2011年6月から外国人高度人材に関するポイント制導入の際の基準等に関する検討会を開催して同年8月に報告書をまとめ、「対象者の範囲や優遇措置の内容によっては、国内労働市場や社会保障制度など厚生労働分野に大きな影響が及ぶ懸念」を指摘しました。その後、同年12月に閣議決定された「日本再生の基本戦略」には告示による早期実現が盛り込まれ、翌2012年3月に法務省告示(高度人材告示)を公表し、同年5月から実施しました。本来は法改正が必要な事項のはずですが、急遽法務省告示で実施し、在留資格は既存の「特定活動」という間に合わせで対応するというドタバタぶりです。
その内容は、①学術研究活動、②専門・技術活動、③経営・管理活動の3分野について、学歴、職歴、年齢、年収、研究実績などの項目ごとにポイントを設定し、合計70ポイント以上獲得したものを高度人材と認定し、①複合的な在留活動の許容、②5年の在留資格の付与、③高度人材の配偶者の就労許可要件の緩和、④一定の条件の下での高度人材の親の帯同の許容、⑤一定の条件の下での高度人材に雇用される外国人家事使用人の帯同の許容などの優遇措置が付与されます。しかし、目論見に反して高度人材の数は増えませんでした。
そこで法務省は2013年12月に要件を緩和し、日本語能力や日本の高等教育機関での学位取得のポイント配分を引き上げるとともに、最低年収基準を学術研究については撤廃し、専門・技術と経営・管理については全年齢一律に300万円に引き下げました。これは「大学等教育機関や中小企業で就労する者については、一般に大企業で就労する者より年収が低いことに配慮」したためです。
その後、告示で対応していた高度人材ポイント制が、2014年6月の入管法改正によりようやく「高度専門職」という在留資格になりました。入管法別表第一の高度専門職の欄には、「我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれる」第1号活動と、「我が国の利益に資する」第2号活動に区分されます。1号の在留期間は5年、2号は上限がありません。
さらに2016年6月の「日本再興戦略2016」では、高度外国人材をさらに呼び込むため、高度外国人材の永住許可申請に要する在留期間を5年から大幅に短縮する世界最速級の「日本版高度外国人材グリーンカード」を創設すると打ち上げました。これを受けて2017年4月から、70点以上の者は3年、80点以上の者は1年に短縮されました。これは事実上、初めから「永住者」としての在留資格を認めるのに等しく、一種の選別移民制度の導入といってよいでしょう。
ここまで基準が緩和された高度専門職は、一体どこまで本当に「高度専門」の名に値するものになっているのでしょうか。現時点のポイント計算表を下に示しておきます[図表1]。
図表1 高度専門職のポイント計算表
これを見ると、日本の大学を卒業して(日本の大学にもピンからキリまであるはずですが)、日本語能力がそれなりにあり、一定の中小企業に5年勤続している29歳の外国人は、年収300万円というレベルであっても「高度人材」として扱ってもらえそうです。しかし、この要件を満たす日本人労働者のことを、周りの日本人たちは高度人材とは呼ばないでしょう。外国人受け入れ政策という枠組の中で、どうも「高度人材」の水増しが行われているような気配があります。
労働関係者の関心はどうしてもかつて「単純労働」と呼ばれた技能労働者の受け入れ政策の法に向かいがちですが、こちらにも注意を払っていくことが必要なのでしょう。