『WEB労政時報』2022年10月11日
「公立学校教師の労働時間をめぐる判決の矛盾」
公立学校の教師の労働時間問題に関しては、もう3年近く前になりますが、2019年12月24日付けの本欄で取り上げたことがあります。
そこでその経緯を若干詳しく解説した「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(=給特法)をめぐって、昨年から今年にかけて世間の注目を集めた判決が出ました。埼玉県の私立小学校の教師であった原告は、時間外労働に対する割増賃金の支払を求めて訴えた埼玉県事件でした。さいたま地裁の判決が2021年10月1日、東京高裁の控訴審判決が2022年8月25日に出され、現在最高裁に上告中です。
この事件では、原告側の理屈の立て方がひとひねりされていました。
(原告の主張)
ア 給特法は、教育職員(同法2条2項。以下「教員」ということがある。)に対して時間外勤務手当を支払わない旨を定め、労基法37条を適用しないものとしているが、以下の給特法等の定めによれば、教育職員に同条が適用されないのは、平成15年政令2号イからニまでに掲げられた項目に係る業務(以下「超勤4項目」という。)についての時間外勤務命令があった場合に限られ、それ以外の業務について時間外勤務命令を受けこれに従事した場合には、原則どおり労基法37条が適用されるものと解すべきである。
すなわち、給特法6条1項及び平成15年政令は、教育職員に対しては原則として時間外勤務を命じないものとし、時間外勤務を命ずる場合には、超勤4項目に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとしている。これを前提として、同法3条は、教育職員に対しては教職調整額を支給し(1項)、時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給しないこと(2項)としており、同法5条1項及び同項による読替え後の地公法58条2項により、教育職員には労基法37条を適用しないものとしている。以上の定めからすると、給特法は、超勤4項目の時間外勤務については、教職調整額を支給することによって、同法32条や同法37条の義務違反を問われないという免罰効を与えたものと解すべきである。
他方で、超勤4項目に該当しない業務について時間外勤務命令がされた場合は、給特法上特に定めがないことからすると、原則どおり労基法が適用され、時間外勤務を行わせるためには、同法36条1項の定める手続が必要となり、時間外勤務に従事した場合には、同法37条により時間外割増賃金の支払が必要となるというべきである。
以上のことからすると、給特法は、超勤4項目について、時間外勤務命令がされた場合にのみ、労基法37条の適用を排斥しているのであって、それ以外の業務について時間外勤務命令がされた場合には、原則どおり同条が適用されるというべきである。給特法の制定趣旨に教育職員の超過勤務防止が含まれている以上、同法が、基本給の4パーセントにすぎない教職調整額を支給することのみをもって、本来予定されていない超勤4項目以外の業務に係る時間外勤務についてまで時間外勤務手当の支払を免除することを許容しているとは到底解し得ない。
要するに、給特法上の超勤4項目、教職調整額の規定と、労働基準法第37条の適用除外とは密接不可分の牽連性があるという前提に立ち、それゆえ超勤4項目以外の時間外労働に対しては、適用除外されたはずの労働基準法第37条が蘇って適用される、というわけです。原告側としては知恵を振り絞って提起した理屈だったのでしょうが、残念ながらそれは成り立たないと思われます。実を言えば、(文部省の意に反して)労働基準法第36条は適用除外されなかったので、超勤4項目以外の時間外労働は(現に生きている同条に基づき)時間外・休日労働協定の締結が必要であり、それなしに行われた時間外・休日労働は労働基準法第32条違反になるという理屈は十分成り立ちえたと思われますが、地方公務員法第58条第3項を通じてなんの附帯条件もなく適用除外されてしまっている第37条は復活のしようがないのです。
そのことを証明するために、若干回り道が必要です。実は、給特法が1971年に成立したときには、今と違って「国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」という法律名でした。まずは労働基準法の全く適用されない国家公務員たる国立学校の教師について規定を定めた上で、それを労働基準法が原則的に適用される地方公務員たる公立学校の教師に準用するという形だったのです。ところが、その構造を抜本的に揺るがしたのが、2003年7月に成立し、2004年度から施行された国立大学法人法です。国立学校の教師は完全に民間労働者となったため、同時に成立した国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により、給特法は本体であったはずの国立学校が外されてしまったのです。
こうして法律名は「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」となり、もともと国立学校に関する規定を準用されていた公立学校が一躍主役に抜擢されてしまいました。肝心の国立学校の教師はあっさりと労働基準法全面適用除外から労働基準法フル適用の世界に追いやられてしまい、後に残された地方公務員たる公立学校の教師は、元々準用であった規定の主役の座に座らされ、原則適用のはずの労働基準法を適用除外する理屈を自分たちだけでこしらえ上げなくてはならなくなってしまいました。
これと同時に地方独立行政法人法も制定され、その業務には「大学の設置及び管理を行うこと」も含まれたため、公立大学法人も設置することが可能となりました。公立大学法人は法律上すべて非公務員型(一般地方独立行政法人)で、大学の設置管理に附帯する業務として附属学校の設置管理も可能です。実際には、教育学部を有する国立大学と違い、公立大学で附属学校を有するものは数少ないですが、いくつか存在します。たとえば、公立大学法人兵庫県立大学には附属高校と附属中学校があります。
公立大学法人附属学校の教師には給特法は適用されるのでしょうか。学校教育法第2条第2項は、「公立学校とは、地方公共団体の設置する学校」と定義していますが、同条第1項で「地方公共団体(地方独立行政法人法・・・第六十八条第一項に規定する公立大学法人・・・を含む。次項・・・において同じ。)」とあるので、公立大学附属学校も同法にいう公立学校であり、従って、給特法第2条第2項により同法が適用される「義務教育諸学校等」に含まれます。つまり、給特法は適用されます。
ところが話はそれで終わりません。公立大学法人は非公務員型であり、地方公務員法はそもそも適用の余地はありません。ということは、給特法が適用されるといってもそれは教職調整額の支給や超勤4項目に係る部分であって、第5条の地方公務員法の読み替え規定は、読み替えられるべき地方公務員法第58条第3項が適用されていない以上空振りとならざるを得ません。つまり、公立大学法人附属学校の教師は公立大学教授と同様に、労働基準法の適用上はフルに民間労働者なのであって、第33条第3項によって時間外・休日労働を命ずることはできず、第36条によって労使協定を締結しなければ超勤4項目に該当しようがしまいが超勤は不可能であり、そして4%の教職調整額が払われているからといって、第37条による割増賃金の支払を免れることはできません。
こうして、埼玉県事件の原告の主張に反して、給特法の本体規定と地方公務員法を通じた労働基準法の読み替え規定とが密接不可分ではないことが明らかになりました。非公務員型の公立大学法人の附属学校の教師は、公立学校の教員として給特法が適用されるので、超勤4項目への限定や教職調整額の支給は義務づけられる一方で、公務員の身分を有さないために地方公務員法第58条第3項は適用されず、従って同項を通じた労働基準法の読み替え規定も空振りとならざるを得ず、それゆえに労働基準法第33条第3項による時間外・休日労働命令は不可能であり、第36条による時間外・休日労働協定が不可欠であり、第37条による割増賃金の支払を免れることはできません。給特法の法構造自体が、両者が密接不可分の牽連性を有していないことを示しているのです。
結局、たまたま地方公務員の身分を有するところの原告に関するかぎり、超勤4項目以外の時間外・休日労働を行わせたことが給特法違反の問題を生じさせることは格別、また適用除外されていない36協定無締結の問題を生じさせることはあり得ても、少なくとも完全適用除外されている第37条に基づく割増賃金の請求は不可能であると言わざるを得ません。これは原告がたまたま地方公務員の身分を有しているからであって、それ以外のいかなる理由によるものでもありません。もし原告が私立学校の教師であったり、国立学校の教師であったり、公立大学法人附属学校の教師であったりしたら、教師としての職責には全く何の違いもないにもかかわらず、原告の訴えは認められていたはずです。
しかしながら、さいたま地裁の裁判官も東京高裁の裁判官も、そのような深く突っ込んだ考察は一切ないまま、恐らく教育委員会側から提出された資料を何も考えずに丸写しにするような判決文を書いています。
・・・教員の職務は、使用者の包括的指揮命令の下で労働に従事する一般労働者とは異なり、児童・生徒への教育的見地から、教員の自律的な判断による自主的、自発的な業務への取組みが期待されるという職務の特殊性があるほか、夏休み等の長期の学校休業期間があり、その間は、主要業務である授業にほとんど従事することがないという勤務形態の特殊性があることから、これらの職務の特質上、一般労働者と同じような実労働時間を基準とした厳密な労働管理にはなじまないものである。例えば、授業の準備や教材研究、児童及び保護者への対応等については、個々の教員が、教育的見地や学級運営の観点から、これらの業務を行うか否か、行うものとした場合、どのような内容をもって、どの程度の準備をして、どの程度の時間をかけてこれらの業務を行うかを自主的かつ自律的に判断して遂行することが求められている。このような業務は、上司の指揮命令に基づいて行われる業務とは、明らかにその性質を異にするものであって、正規の勤務時間外にこのような業務に従事したとしても、それが直ちに上司の指揮命令に基づく業務に従事したと判断することができない。このように教員の業務は、教員の自主的で自律的な判断に基づく業務と校長の指揮命令に基づく業務とが日常的に渾然一体となって行われているため、これを正確に峻別することは困難であって、管理者たる校長において、その指揮命令に基づく業務に従事した時間だけを特定して厳密に時間管理し、それに応じた給与を支給することは現行制度下では事実上不可能である(文部科学省の令和2年1月17日付け「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」〔文部科学省告示第1号〕においても、教育職員の業務に従事した時間を把握する方法として、「在校等時間」という概念を用いており、厳密な労働時間の管理は求めていない。甲82)。このような教員の職務の特殊性に鑑みれば、教員には、一般労働者と同様の定量的な時間管理を前提とした割増賃金制度はなじまないといわざるを得ない。
これら判決によれば、労働基準法第37条の適用除外は「教員の自律的な判断による自主的、自発的な業務への取組みが期待されるという職務の特殊性」によるものであり、それゆえ「教員には、一般労働者と同様の定量的な時間管理を前提とした割増賃金制度はなじまない」のだそうです。そうした教員の職務の特殊性は、いうまでもなく私立学校や国立学校の教員にもあるはずですが、これら判決を書いた裁判官の目には彼らの存在が映っていなかったのでしょうか。令和3年度の学校基本調査によれば、給特法の対象に相当する高校までの教員数は、私立学校は158,821人、国立学校は4,611人です。公立学校の832,649人に比べれば若干少ないとはいえ、無視していい数ではありません。
しかも、当然のことながら労働基準法がフルに適用されている彼らについては、労働基準監督機関が法違反を容赦なく摘発しに来ます。2022年8月に厚生労働省労働基準局監督課が発表した「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)」には、賃金不払残業の解消のための取組事例として私立学校のケースが載っています。
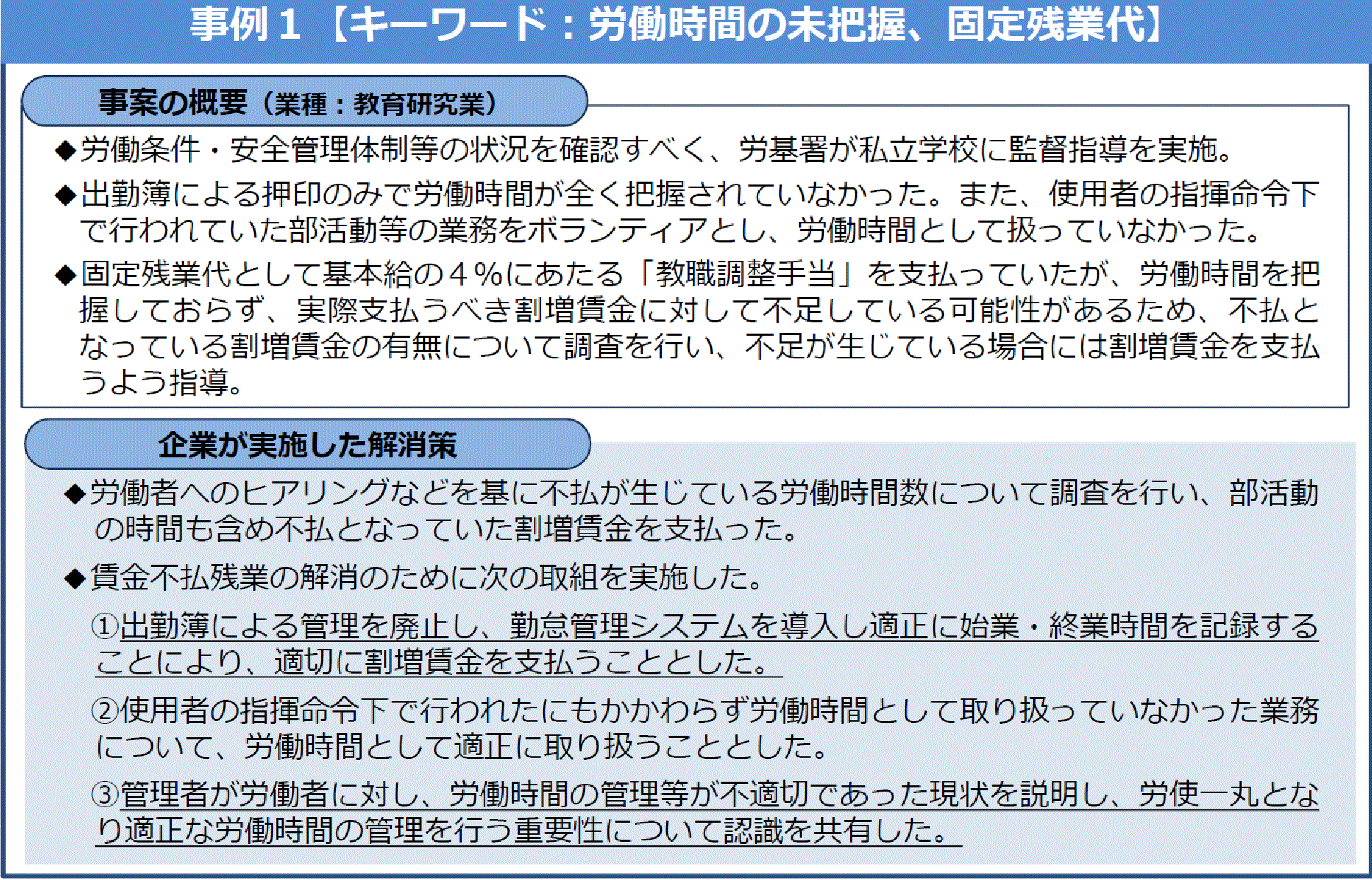
公立学校にでもなったつもりで4%の教職調整額を払い、時間外割増賃金を払わなかった私立学校が、部活動の時間も含めて不払い残業代を払わされています。現行法上当然のことではありますが、もしこの私立学校の経営者が上記さいたま地裁や東京高裁の判決文を読んだらどう思うでしょうか。我が校の教師たちも、「教員の自律的な判断による自主的、自発的な業務への取組みが期待されるという職務の特殊性」はなんら変わることはなく、「教員には、一般労働者と同様の定量的な時間管理を前提とした割増賃金制度はなじまない」のではないのか。労働基準監督署の監督指導は不当だ!と思うのではないでしょうか。そして、そう思った私立学校が、上記判決文を根拠として、職種としての教員にはなじまない割増賃金制度を、法律に書いてあるからといって押しつけてくるのは違法だと言って訴えを提起してきたら、これら判決を書いた裁判官たちは一体どういう判決を下すつもりなのでしょうか。恐らく、そんなことはかけらも脳裡に浮かばなかったのでしょう。
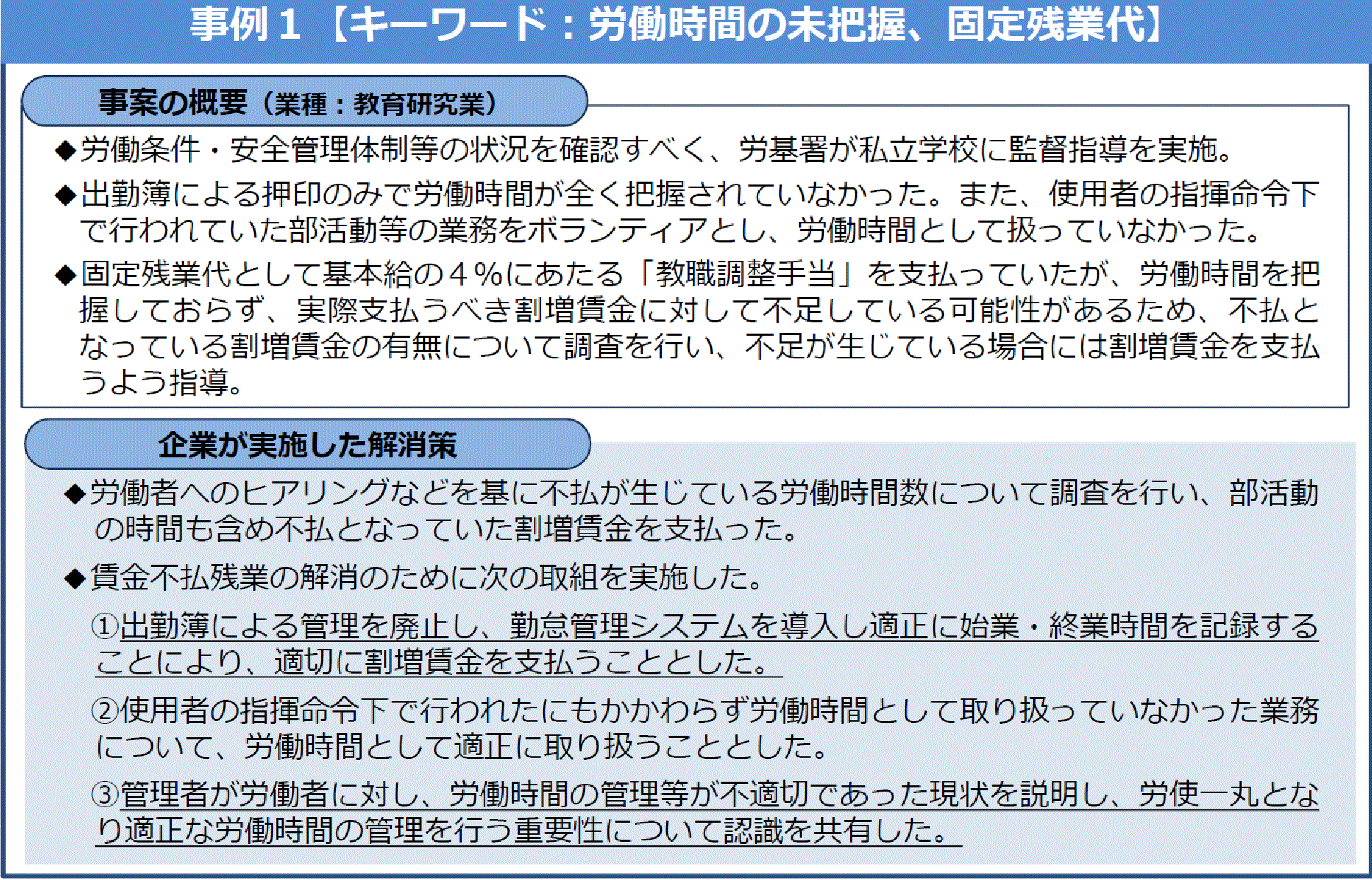 公立学校にでもなったつもりで4%の教職調整額を払い、時間外割増賃金を払わなかった私立学校が、部活動の時間も含めて不払い残業代を払わされています。現行法上当然のことではありますが、もしこの私立学校の経営者が上記さいたま地裁や東京高裁の判決文を読んだらどう思うでしょうか。我が校の教師たちも、「教員の自律的な判断による自主的、自発的な業務への取組みが期待されるという職務の特殊性」はなんら変わることはなく、「教員には、一般労働者と同様の定量的な時間管理を前提とした割増賃金制度はなじまない」のではないのか。労働基準監督署の監督指導は不当だ!と思うのではないでしょうか。そして、そう思った私立学校が、上記判決文を根拠として、職種としての教員にはなじまない割増賃金制度を、法律に書いてあるからといって押しつけてくるのは違法だと言って訴えを提起してきたら、これら判決を書いた裁判官たちは一体どういう判決を下すつもりなのでしょうか。恐らく、そんなことはかけらも脳裡に浮かばなかったのでしょう。
公立学校にでもなったつもりで4%の教職調整額を払い、時間外割増賃金を払わなかった私立学校が、部活動の時間も含めて不払い残業代を払わされています。現行法上当然のことではありますが、もしこの私立学校の経営者が上記さいたま地裁や東京高裁の判決文を読んだらどう思うでしょうか。我が校の教師たちも、「教員の自律的な判断による自主的、自発的な業務への取組みが期待されるという職務の特殊性」はなんら変わることはなく、「教員には、一般労働者と同様の定量的な時間管理を前提とした割増賃金制度はなじまない」のではないのか。労働基準監督署の監督指導は不当だ!と思うのではないでしょうか。そして、そう思った私立学校が、上記判決文を根拠として、職種としての教員にはなじまない割増賃金制度を、法律に書いてあるからといって押しつけてくるのは違法だと言って訴えを提起してきたら、これら判決を書いた裁判官たちは一体どういう判決を下すつもりなのでしょうか。恐らく、そんなことはかけらも脳裡に浮かばなかったのでしょう。