『日本人の働き方100年-定点観測者としての通信社-』図録解説
この写真展を第1部から見始めた人はみんなこういう感想を持つに違いない。
「昔の日本人って、こんなに労働争議ばっかりやっていたのか!?」
まず劈頭を飾るのが今からほぼ1世紀前の1920年、大日本労働総同盟友愛会が主催した日本最初のメーデーの写真だが、その後は横浜市電の総罷業、日本ゼネラルモータースの越年争議、鐘紡争議で募金活動する女性たち、東京市電の罷業本部で炊き出しする女性車掌たち、女工哀史で有名な東洋モスリン亀戸工場の争議、住友製鋼所の争議への差し入れ風景、事務所に立てこもって気勢を上げる山岡発動機工作所争議団、等々と、どれもこれも闘う労働者の姿ばかりが映っている。いや雇用されている労働者だけではない。相撲の力士たちが待遇改善を求めて中華料理店に籠城しているかと思えば、浅草松竹座のレビューガールたちも待遇改善を求めて気勢を上げているのだ。
労働争議などという言葉がほとんど死語と化しつつある現代日本人からすると、およそ4世代前の先輩たちの姿は想像を絶するものかもしれない。なにしろ、2019年8月に東北道の佐野サービスエリアでフードコートの従業員たちが経営者に不満を募らせて令和最初のストライキに打って出たとき、マスコミは客が困惑しているとか、経営の仕方がまずかったとか論評するだけで、まともに労働争議として論ずることはほとんどなかったのである。
ここで、戦前から今日に至るまでの労働争議件数のグラフを見ておこう。1922年から2019年まで約100年間の労働争議の増減がよくわかる。青い線は労働争議の総件数、橙色の線はそのうちストライキなどの争議行為を伴う争議件数である。
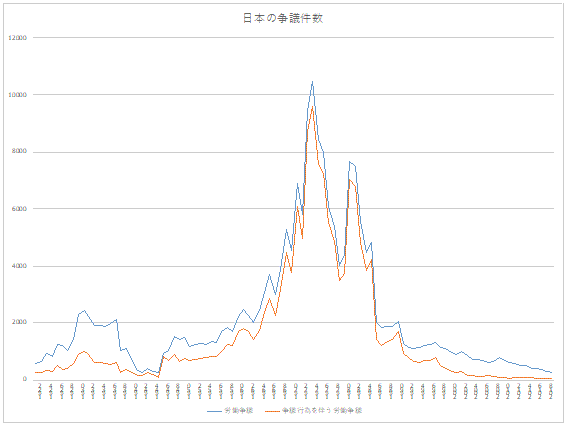
争議行為を伴わない労働争議というのは、実力行使をしない口先だけの争議ということだが、一番最近の2019年には総争議件数268件中、争議行為を伴う争議はわずか49件、残りの219件は口先争議に過ぎない。しかも争議行為を伴うといっても、49件のうち半日以上のストライキはたった27件である。最盛期の1974年には、総争議件数10,462件、そのうち争議行為を伴う争議が9,581件、そのうち半日以上のストライキは5,197件もあったのだが、戦前だって決して見劣りはしない。1931年には総争議件数2,456件、そのうち争議行為を伴う争議は998件もあった。平成、令和のすっかり争議を忘れてしまった日本人に比べれば、戦前の日本人の方がはるかに闘争心をむき出しにしていたのだ。
忘れてはならないのは、戦前の日本には団結権や団体行動権を保障した憲法もなければ、労働組合を守る労働組合法もなかったということだ。1925年と1931年に政府は労働組合法案を議会に提出したが、いずれも経営側の猛反発で審議未了、廃案となっている。団体交渉や争議の煽動に刑罰を科す治安警察法の規定は1926年に削除されたとはいえ、警察権力の敵意の中で争議を貫く労働者の姿が各分野にみられた。
第1部の写真はやがて戦時中の軍需工場や自給農園に移っていくが、実はその時期にも労働争議は続いていた。太平洋戦争真っ盛りの1943年ですら、総争議件数417件、そのうち争議行為を伴う争議件数279件と、今どきの日本人よりもたくさん争議をしていたのである。敗戦後も日本人は労働争議に明け暮れた。東宝争議の写真に写っているのは鎮圧にやってきた米軍の戦車である。「来なかったのは軍艦だけ」といわれたこの争議では、組合側で黒澤明監督や三船敏郎らが活躍したことでも知られている。デパートでも「三越にはストもございます」と48時間ストライキに突入した。
日本の労働争議史上に燦然と輝く成果を収めたのは、既に第2部に入っているが、1954年の近江絹糸争議である。人絹と人権を引っかけて、人権争議とも呼ばれたこの争議は、若い女子工員たちが宗教、外出、通信の自由を求めてストライキを決行し、封建的な経営方針を打ち破った、まさに戦後民主主義の象徴ともいうべき争議であった。しかし民間部門では、1960年の三井三池炭鉱争議以後は大企業分野では争議は影を潜めた。なお争議が盛んに行われたのは、法律で争議が禁止されていた公共部門であった。しかし、郵便、国鉄といった公共サービスのストライキは、民間労働者の共感を呼びどころか反発を招き、やがてこれら公共部門の民営化の遠因ともなっていくことになる。
労働者が集団で権利を訴える労働争議が影を潜めるのと軌を一にして、個別労働紛争と呼ばれる労働者個人の紛争類型が増えていく。この十数年来、都道府県労働局への労働相談は100万件を超えて推移している。解雇、雇い止め、内定取消、退職勧奨、労働条件引下げ、いじめ・嫌がらせといったものだが、労働争議と違ってこれらは絵になりにくい。第3部には年越し派遣村で炊き出しに並ぶ人々、失職してハローワークを訪れた非正規労働者たち、採用試験に臨む就職氷河期世代といった、間接的に個別労働紛争を暗示する写真もあるが、総じて紛争は見えにくくなっている。そして、その中のごく一部だけが裁判闘争という形で可視化される。
第3部には解雇をめぐる裁判闘争が勝利に終わった写真が1枚だけあるが、それは2013年、大相撲の八百長問題をめぐる蒼国来のものである。雇用される労働者の姿は一つもないのだ。これと軌を一にして、第3部に登場する唯一のストライキの写真は、2004年のプロ野球選手会によるものである。大相撲とプロ野球。労働をめぐる紛争は、いまや華やかなプロスポーツの世界でしか表舞台に現れなくなってしまったかの如きである。普通の労働者の普通の争議は、この写真展で取り上げてもらえるだけのものではなくなってしまったのだ。
その代わりにデモの写真がいっぱいあるではないか、と思うかもしれない。たしかにそうだ。しかし、デモは所詮デモに過ぎない。少なくとも労働問題に関する限り、ストライキが会社と斬り合う真剣勝負であるとすれば、デモは広く世間一般に訴えかけているだけだ。それは市民運動の一種であって、団結した労働者にしかできない闘い方ではない。そして、戦前や戦後のデモの写真が、メーデーにおける労働者の団結を誇示するデモンストレーションであったのに対し、第3部に登場するデモの写真は、労働時間規制や派遣切りといった労働政策テーマに対するマイノリティグループのアドボカシー活動以上のものではない。そのプラカードに「原発反対」とか「海外派兵反対」とかあってもなんの違和感もないだろう。それがたまたま労働運動を名乗っていたとしても、いかなる意味でも労働争議と呼ぶことはできない。
もう一度第1部からみていくと、戦前から今日まで一貫して登場するテーマが、仕事に就くことの難しさであることがわかる。戦前、簡易宿泊所で仕事にあぶれた自由労働者にパンを配給する官僚や政治家の姿から、戦後仕事を求めて飯田橋職安に殺到する失業者たち、職寄こせと池袋職安に押しかけた自由労働者たち、帝国ホテル近くで服に「求職」の張り紙をして立っている青年の姿は、21世紀に日比谷公園の年越し派遣村の炊き出しに並ぶ人々、ハローワークで仕事を探す人々の姿に至るまで、労働者にとって最大の災厄が失業であったことを物語っている。
写真展劈頭の第一回メーデーが行われた1920年は、日本政府が初めて失業対策として、職業紹介所の設置や土木工事の施工に踏み出した年であり、メーデーを主催した大日本労働総同盟友愛会が失業保険法制定を要求した年でもあった。だが、日本では退職手当を支給する慣行があるから失業保険など不要だという経営側の反対で、終戦直後に至るまで失業保険制度はできなかった。
その代わりに、1923年の関東大震災後、そして1929年の世界大恐慌の下で、失業者救済のための公営土木事業を行った。これは戦後、焼け野が原になった国土復興のための土木事業に、戦争に敗れて帰国した復員兵たちを含む膨大な失業者を吸収する緊急失業対策事業という形で復活した。この事業は、少なくとも戦後復興期の間は有効に機能したと言える。しかし、ここに吸収されたニコヨンと呼ばれる労働者たちは、やがて社会が安定し、経済成長が始まってからも失業対策事業にしがみついた。失業対策事業の打切りに反対して労働省の裏庭に集まった高齢の失対労働者たちの姿は悲しい。皮肉なことに、1995年に緊急失業対策法が廃止された後になって、再びこうした事業が行われるようになった。東日本大震災で仕事を失った人々を復旧・復興事業に吸収しようという運動が、キャッシュ・フォー・ワークという新たな名で登場したのである。
大日本労働総同盟友愛会のリーダーの一人であり、1921年に川崎・三菱造船所の争議を主導した賀川豊彦は、戦後失業保険法の制定にも関わった。これにより、一定期間働いてきた失業者はすぐに生活に困窮するということはなくなった。ほどなく日雇労働者失業保険もできた。山谷や釜ヶ崎といったいわゆる寄せ場には日雇労働者の宿泊する簡易宿泊所(ドヤ)が建ち並び、早朝には手配師が彼らをトラックの荷台に積んで建設現場に連れて行く。連れて行ってもらえなかった、つまり「アブレ」た日雇労働者は、寄せ場の職安に白手帳を提示して、その日のアブレ手当をもらう。そうした寄せ場の日常が時に大きく炎上する。1961年の早朝の釜ヶ崎風景は、第1次釜ヶ崎暴動のその後だ。釜ヶ崎はその後も二十数回にわたって暴動を繰り返したが、日雇労働者たちも高齢化していき、今や生活保護を受給する老人と外国人バックパッカーの街となっている。
日雇労働者はいなくなったのか?いやそうではない。ただ、山谷や釜ヶ崎といった寄せ場に可視化されなくなったということである。2000年代には、携帯電話で仕事をあっせんする日雇派遣が急増した。日雇労働者は寄せ場のドヤに集まることなく、電波の届く限りアパートの小部屋やネットカフェなどに散在するようになった。それゆえ、この写真展にも、日雇派遣を取り上げた一枚の写真もない。労働の不可視化の一つの現れであろうか。ただ、上述の「デモ」の写真の一環として、フリーター全般労組が新宿を行進する姿と派遣切りに抗議するデモ参加者の姿が写っているばかりである。だが、なぜ派遣切りがそれほど問題になったのか。
失業保険によって、一定期間働いてきた失業者はすぐに生活に困窮することはなくなった、と先に述べた。だが実はそこからこぼれ落ちる人々がいた。最初は悪意ではなかった。1950年の通達が、臨時内職的に雇用される「家庭の婦女子、アルバイト学生」を対象から外したのは、解雇されても(夫や親に扶養されるから)失業するおそれがないと考えたからだ。ところがこの扱いがパートタイマーや派遣労働者などにも広がる一方、就職氷河期に直面して正社員として就職することができなかった若者たちが「フリーター」という名で非正規労働力に投げ込まれた。低賃金不安定雇用で自らの生計を支える彼らは、扶養されていることが前提のパート・派遣の一種として、雇用保険という労働市場のセーフティネットからも排除されてしまった。その矛盾が一気に露呈したのが、2008年のリーマンショックであり、派遣切りであった。一番セーフティネットが必要な人々が、一番そこから排除されているという実態が明らかになったのである。日比谷公園の年越し派遣村の炊き出しに並ぶ人々がその象徴となった。
その後、法改正で日雇派遣は原則禁止となったが、ほとんど同じビジネスモデルが日雇紹介という名で継続しただけであった。そして、2016年には雇用ではなく請負という契約形式で使用者責任を負わないウーバーイーツというビジネスモデルが日本でも始まり、2020年にはコロナ禍で急激に拡大した。いまや日雇労働はデジタルな請負の世界に主力を移しつつあるようである。第3部の一番最後の写真がウーバーイーツの配達員であるのは、日本の労働の未来図を暗示しているのかもしれない。
仕事に就くためにはスキルを身につけなければならない。戦前の不況下で手に職をつけようとする女子美術学校手芸科の女性たちの姿から、戦後東京商工会議所の英文タイプ技能検定試験に集まったタイピストたち、就職氷河期に日比谷公園の就職出陣式で肩を組む専門学校生、氷河期世代向けの宝塚市採用試験に臨む受験者たちに至るまで、スキルアップに励む日本人の姿もこの100年間変わることはない。ただやはり、どうしても写真展に出てくるのは「絵になる」姿ばかりである。
犬が人にかみついてもニュースにならないが、人が犬にかみつくとニュースになる。保健婦(士)国家試験の合格発表会場に訪れた男性保健士の写真は載るが、女性保健婦は載らない。だが、労働の世界を支えているのは、そうした写真の載らない多くの人々であるのも確かである。職業訓練校で日々黙々と訓練に励む訓練生の姿は通常は不可視化されている。それが可視化されたのは、1998年に封切られた山田洋次監督の映画『学校Ⅲ』で、リストラされた中高年齢者たちが必死に職業訓練に励む姿を描いたことによってであった。
その一方で、建前としてはスキルを身につけるための仕組みだという名の下に、安価な外国人労働力を導入しようとして拡大されてきたのが研修・技能実習制度であった。外国人労働者の姿は第2部の終わりあたりから次第に増えていく。1980年代のフィリピン人ホステス(じゃぱゆきさん)や中国人留学生から始まって、天皇・皇后(現上皇・上皇后)両陛下が日系ブラジル人労働者と交流する姿を経て、被災地の水産工場で働く中国人技能実習生、日が暮れるまで農作業に励むインドネシア人技能実習生、ベトナムの実習生送り出し機関の中庭に集まった候補生たちと、日本の産業が次第に外国人労働力によって支えられていく姿が活写されている。この写真展の最後近くに、在日ベトナム人(その多くは技能実習生であろう)を支援するためにコメを配布する姿が登場するのは、もはや後戻りできないその構造を象徴しているのかもしれない。
男性保健士だけは逆方向のジェンダー職域拡大であるが、この写真展の一つの基調低音が女性活躍であるのは間違いないだろう。日本初の女性○○というのは、常にマスコミのペットテーマであった。1946年の婦人警官誕生から始まって、同年の婦人参政権による女性議員39人当選、1948年の皇宮婦人護衛官、1951年のエアガール勢揃い、1952年の保安隊婦人部隊員、1960年の女性閣僚、そして2018年の女性戦闘機パイロットと、活躍の場は広がってきた。ただ。そういう上澄みばかりを追いかけることで、その背後に広がる膨大な普通の働く女性たちの姿がかすんでしまわないように気をつけなければならない。
女性活躍などというかけ声はなく、むしろ民法を始めとする国家制度自体が働く女性に対して制約的であった戦前の写真の中にこそ、ごく普通の女性労働者たちがごく自然に団結し、ごく自然に自分たちの権利を主張している姿が映し出されている。1930年の鐘紡争議で、街頭に出て募金活動する女性たちや、ストライキに突入して幡ヶ谷の罷業本部で炊き出しをする女性車掌たち、開演中の浅草松竹座で気勢を上げるレビューガールたちの姿には、今日みることの少なくなった「闘う笑顔」が詰め込まれている。戦後もある時期まではそうした「闘う笑顔」がみられるが、やがて姿を消していく。そこには、1985年の男女雇用機会均等法以後、女性も男性と同様、団結よりは競争の世界で生きていくこととなったことが示されているのであろう。
普通の労働者の普通に働く姿は、普通の時代にはわざわざマスコミの写真として残されることはない。それが残されるのは普通ではない時代である。1938年の製糸工場で働く女工たちの姿、1943年の空襲下で防毒マスクをつくる少女たちの姿、1945年の沖縄の軍需工場で働く少年戦士の姿、そして戦闘帽や防空頭巾姿で職場に向かう出勤風景など、異常な時代の異常な労働だからこそ、それを黙々とこなす普通の労働者たちの姿が目に焼き付く。
労働とは日々の営みである。お祭りではない。日本人の働き方100年を本当にありのままに映し出せば、その99%までは普通の労働者の普通に働く姿になるであろう。しかし、本写真展の大部分を占める写真は決して普通ではない。普通ではないからこそ写真が撮られ、記事と共に報道されてきたのだ。当たり前といえば当たり前だが、そのことを改めて頭に置いた上で、再度初めからこの写真展をみていきたい。101年前の第一回メーデーから、昨年コロナ禍の下で自転車を漕ぐウーバーイーツ配達員までの、この激動の時代を生きた労働者の姿を。
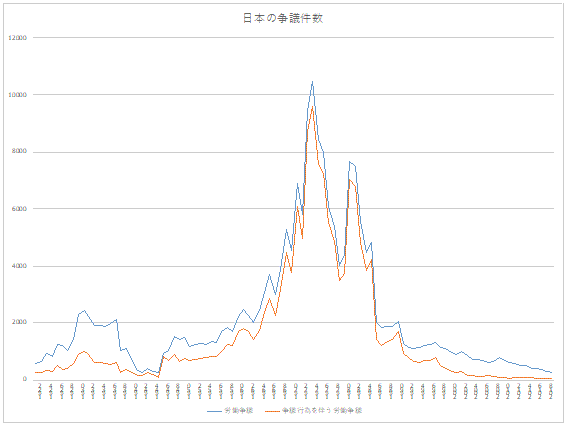 争議行為を伴わない労働争議というのは、実力行使をしない口先だけの争議ということだが、一番最近の2019年には総争議件数268件中、争議行為を伴う争議はわずか49件、残りの219件は口先争議に過ぎない。しかも争議行為を伴うといっても、49件のうち半日以上のストライキはたった27件である。最盛期の1974年には、総争議件数10,462件、そのうち争議行為を伴う争議が9,581件、そのうち半日以上のストライキは5,197件もあったのだが、戦前だって決して見劣りはしない。1931年には総争議件数2,456件、そのうち争議行為を伴う争議は998件もあった。平成、令和のすっかり争議を忘れてしまった日本人に比べれば、戦前の日本人の方がはるかに闘争心をむき出しにしていたのだ。
争議行為を伴わない労働争議というのは、実力行使をしない口先だけの争議ということだが、一番最近の2019年には総争議件数268件中、争議行為を伴う争議はわずか49件、残りの219件は口先争議に過ぎない。しかも争議行為を伴うといっても、49件のうち半日以上のストライキはたった27件である。最盛期の1974年には、総争議件数10,462件、そのうち争議行為を伴う争議が9,581件、そのうち半日以上のストライキは5,197件もあったのだが、戦前だって決して見劣りはしない。1931年には総争議件数2,456件、そのうち争議行為を伴う争議は998件もあった。平成、令和のすっかり争議を忘れてしまった日本人に比べれば、戦前の日本人の方がはるかに闘争心をむき出しにしていたのだ。