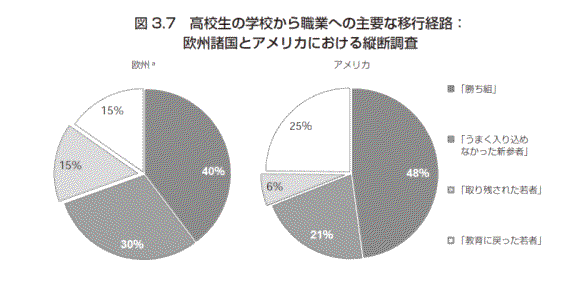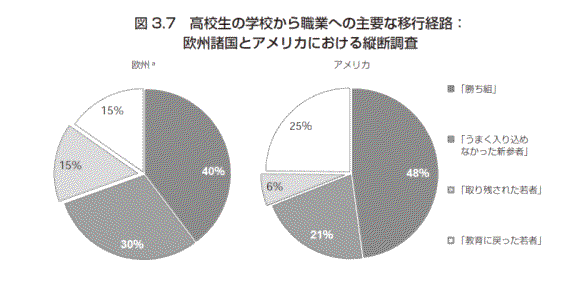『I・B(Information Bank)』2016新春特別号
「雇用システムと若者雇用」
私は今から十数年前、若者雇用に関する本を翻訳し、自著を刊行したことがある。すなわち2010年にはOECDの報告書である『日本の若者と雇用』、2011年には『世界の若者と雇用』を翻訳した。また2013年には一般向けの『若者と労働』(中公新書ラクレ)を刊行し、これは今まで10刷を重ねている。同書で私が強調したのは、欧米と日本では雇用システムが全く異なり、そのために若者雇用の姿が全く異なって現われてくるということであった。
欧米(及びアジア)のジョブ型雇用社会では、企業とは様々な職務(ジョブ)の束であり、それぞれの職務にそれを最も的確に遂行しうる人材を採用して嵌め込むことが「採用」ということの唯一の意味になる。つまり採用とは全て(新たなポストを創設する場合も含め)欠員補充なのであり、「その仕事をできる人」を採用するのが当然である。この「当然」というのは、企業経営上その方が合理的だというだけではない。あるポストに応募してきた複数人の中から、その仕事をできる人を差し置いて、その仕事をできない人を採用したとするならば、それは明白な採用差別となる。とりわけ、できる人が女性でできない人が男性であったり、できる人が黒人でできない人が白人だったりすると、訴えられて勝つ見込みはほとんどない。圧倒的に多くの日本人にはこの肝心要のところがほとんど理解されていない。差別というのは何か感情的な話だと思い込んでいる。それは、ジョブ型雇用社会のイロハのイが全く理解されていないからである。
こういうジョブ型雇用社会においては、若者というのは不利な立場に立たされる。とりわけ学校を卒業したばかりの新卒者は、仕事をしたことがないのだから「その仕事ができます」と応募することは難しい。経験を積んだ中高年齢者と競争すれば、企業側は(差別と言われないように自己防衛するためにも)未経験の若者ではなく経験のある中高年齢者を採用することになる。つまり、ジョブ型社会では、若者は若者であるが故に労働市場で不利な立場に立たされることになるのである。この点も、新卒一括採用システムに慣れ親しんで、それ以外の採用を「中途採用」などとあたかも例外であるかのようにみなしている日本人にはなかなか理解しがたい点であろう。
もっとも、「その仕事ができる」証明は職歴に限らない。学歴もそうである。というと、日本も学歴社会だから同じじゃないか、と思われるかもしれないが、根本的に異なるのは、学歴すなわち教育機関の卒業証書(ディプロマ)が「その仕事ができる」証明であるという点である。それゆえ、ビジネススクールの卒業証書は、企業の管理職ポストへの最強のパスポートになる。しかしながら、すべての学校の卒業証書がその卒業生の職業スキルを証明してくれるわけではない。そうすると、自分の職業スキルを証明してくれる材料を持たない低学歴の若者は、つらく苦しい「学校から仕事への移行」の時期を過ごさなければならなくなる。欧米社会というのは、若者が就職しにくい社会なのだ。だから、過去数十年にわたって、欧米諸国の雇用対策というのは、中高年などはほったらかしにして、ほとんどもっぱら若者の就職対策に集中してきたのである。
先に挙げたOECDの報告書『世界の若者と雇用』に、大変印象的なグラフが載っている。学校から職業への移行がうまくいったかどうかで、若者を「勝ち組」「うまく入り込めなかった新参者」「取り残された若者」「教育に戻った若者」の4つに分けている。さて、ここでいう「勝ち組」(high performer)の定義は何だとお考えになるだろうか?
OECDのいう「勝ち組」とは、教育を離れた後の5年以上の期間、その期間の大部分(70%以上)において雇用に就いており、学校を離れてから初職を見つけるのにかかった期間が6か月未満の若者のことである。え?それでどこが「勝ち組」なのか?と多くの日本人は思うだろう。いや、それで「勝ち組」なのだ。それが、若者は就職できないのが当たり前の欧米社会の常識なのである。就職氷河期のような特殊な時期を除けば、誰でもがほぼ間違いなく自分の就職先を見つけ出すことができた日本から見れば、つまり若者雇用問題が存在しなかったかつての日本からすれば、とても「勝ち組」に見えないような若者が「勝ち組」であるのが、欧米のジョブ型雇用社会なのである。
そして、欧米諸国の若者雇用対策はほぼ揃いも揃って、スキリング、つまり教育訓練を施して何らかの職務のスキルを身につけさせることに焦点を当ててきた。なぜ若者は就職できないのか?それはスキルがないからだ。ならばスキルを与えよう。さすれば就職できるであろう。実のところ、欧米諸国の若者雇用対策はほぼこの一言に尽きるのである。
そのために膨大な予算が組まれ、様々な若者雇用対策が講じられてきたが、にもかかわらず若者はなかなか就職できない。卒業即無業というのがデフォルトルールで、そこから必死に這い上がって何とか就職にたどり着くという在り方自体に変わりはないからだ。そこで、卒業する以前から、在学中から、就職させてしまえばよいのではないかという発想が出てくる。これは別に新しい考え方ではなく、ドイツやその周辺諸国では昔から行われてきているデュアルシステムというものだ。
これは、中世のギルド制度に起源を有するとも言われる仕組みだが、一言でいえば学校教育の枠組みの中で、学校における座学と企業現場における実習とを組み合わせた仕組みである。かつては主として後期中等教育つまり高等学校レベルで行われてきたが、最近は高等教育つまり大学レベルでも盛んに行われるようになっている。学校の座学と企業現場の実習を組み合わせるといっても、その組み合わせ方は半端なものではない。両者が同じくらいの分量で組み合わされているのある。
例えば、高校の3年間、毎週の週日のうち3日間は学校に通って基礎科目や職業科目について勉強をし、残りの2日間は企業現場に通って職場の管理者や先輩労働者に教わりながら実際に作業をやって、職業スキルを身につけていくというパートタイム型もあれば、数か月間は学校に通って勉強をし、次の数か月間はずっと企業現場で作業をするというブロック型のやり方もある。
デュアルシステムの下では、学校の生徒や学生が同時に企業で働く見習労働者でもある。スキルのない若者が企業現場で実習を通じてスキルを身につけるという点では、日本のやり方と似ているといってもよいが、一番重要な点は、デュアルシステムで実習している生徒や学生は、卒業したらその実習している企業に就職するとは限らないということである。デュアルシステムは政府が援助しているが、その主体は地域の業界団体であり、その会員の企業が業界全体の技能労働者養成という目的のための活動として若者を見習労働者として受け入れているのである。決して自分の会社のために、自社の将来の人材を養成するという狭い目的のためにやっているわけではない。これはやはり、ギルド的な業界のつながり、強い絆があって初めて行えることであろう。
なお、これまでデュアルシステムは主として高校レベルで行われてきたが、近年の大学進学率の上昇に対応して、同じようにデュアルシステムで勉強しながら職業スキルを身につける専門大学という教育機関が急速に拡大してきている。今では高等教育機関の6割以上はアカデミックな大学ではなく、専門大学なのである。このお陰で、ドイツやその周辺諸国はEUの中では例外的に若年失業率が低く、ほぼ日本並みである。
これに対して、フランスをはじめとする多くのEU諸国で広がっている教育から職業への移行の装置はトレーニーシップ(研修制度)である。スキルがないゆえに卒業後就職できない若者を、労働者としてではなく研修生として採用し、実際に企業の中の仕事を経験させて、その仕事の実際上のスキルを身につけさせることによって、卒業証書という社会的通用力ある職業資格はなくても企業に労働者として採用してもらえるようにしていく、という説明を聞くと、大変立派な仕組みのように聞こえるが、実態は必ずしもそういう美談めいた話ばかりではない。むしろ、研修生という名目で仕事をさせながら、労働者ではないからといってまともな賃金を払わずに済ませるための抜け道として使われているのではないかという批判が、繰り返しされてきている。
とはいえ、ジョブ雇用型社会のヨーロッパでは、研修生であろうが企業の中で仕事をやらせているんだから労働者として扱えという議論が素直に通らない理由がある。労働者として採用するということはそのジョブを遂行するスキルがあると判断したからなのであって、そのスキルがないと分かっている者を採用するというのは、そのスキルがある応募者からすればとんでもない不正義になるからである。スキルがない者を採用していいのは、スキルを要さない単純労働だけである。そして、単純労働に採用されるということは、ほっとくといつまで経ってもそこから抜け出せないということを意味する。ジョブ型雇用社会というのは、本当に硬直的で面倒くさい社会なのだ。
スキルがない者であるにもかかわらず、スキルを要するジョブの作業をやらせることができるのは、それが教育目的であるからである。労働者ではなく研修生であるという仮面をかぶることで、スキルのない(=職業資格を持たない)者がスキルを要するジョブのポストに就くことができるのである以上、この欺瞞に満ちた研修制度という仕組みをやめることは難しい。
とはいえ、さすがにそれはひどいではないかと声が高まり、EUでは2014年に「研修制度の上質枠組みに関する理事会勧告」という法的拘束力のない規範が制定されている。そこでは研修制度の始期に研修生と研修提供者との間で締結された書面による研修協定が締結されること、研修生の権利と労働条件の確保、手当や報酬が支払われるか否か、支払われるとしたらその金額を明示すること、期間が原則として6カ月を超えないこと等が求められている。とはいえこれは法的拘束力のない勧告なので、実際には数年間にわたり研修生だといってごくわずかな手当を払うだけで便利に使い続ける企業が跡を絶たない。
欧州委員会は2024年3月に研修生(偽装研修対策)指令案を提案し、去る2025年6月に閣僚理事会で一般的アプローチに合意され、同年10月欧州議会でも意見がまとまり、両機関の間で交渉が始まっている。原案では研修を偽装した正規雇用関係を判断する5要件が示され、また均等待遇や期間の上限などが盛り込まれているが、最終的にどのような規定に落ち着くかはわからない。いずれにしても、これがジョブ型雇用社会における若者雇用の実態なのである。
これと比べると、職業資格や職業経験のまったくないど素人を好んで採用し、採用してから適当な職場に配置して、上司や先輩がその若者に作業をさせながら鍛え上げていくというのが、日本的なメンバーシップ型社会の最もメインストリームのやり方である。
OECDの『世界の若者と雇用』では、先進諸国の若者雇用を4つに類型化しているが、日本はそこにうまくはまらない。同報告書では、第1グループは北欧やオランダなどの「働きながら年長まで勉強」モデル、第2グループはアングロサクソン諸国などの「働きながら勉強」モデル、第3グループは多くの欧州諸国が含まれる「まず勉強、それから仕事」モデル、そして第4グループはドイツ、スイス、オーストリアの「実習制度」モデルであり、このうち第3グループは若者の就業率が低く、ニート率が高いなど問題山積なので、学習と労働を組み合わせる方向の政策をとるべきだと力説する。ところが、奇妙なことに、第3の「まず勉強、それから仕事」モデルの最も典型的な国が日本であるにもかかわらず、その若者雇用のパフォーマンスはドイツよりもいいくらいなのだ。その理由は、日本独特の「入社」の仕組みにある。私が「教育と職業の密接な無関係」と呼ぶ「スキルがなくても、いやむしろ下手にスキルのない若者の方を選好する」日本企業の行動様式が、この欧米人には理解不能な事態をもたらしているのである。
最後に、本誌の特集との関係で、AIが若者雇用にどのような影響を与えるかを考えておこう。実のところ、AIが今後どこまで進化していくか、私も分からないし、誰も分からないだろう。ホワイトカラーが従事している多くの知的な仕事の大部分が代替されるという議論もあるし、そこまではいかないという議論もある。ただ現時点で起っているのは、比較的低スキルの、エントリージョブといわれるジョブがAIによって代替され、その結果普通の大卒クラスの若者が(就くべきジョブがなくなったので)就職できないという事態である。この点に関する限り、日本ではそもそもジョブに就くのではなく、会社の社員として全人格的に「入社」するのであるから、同じことは起らないだろう。「入社」後にあてがわれ、上司や先輩に鍛えられながら身につけていくべきスキルが初めからより要求水準の高いものになるだけである。それもしんどいが、しかしそれで済むかどうかは分からない。AIが代替するのがエントリーレベルに留まる保証などないのだから。ホワイトカラーが総体として今までのような規模では不要になっていくのだとしたら、若者であろうか中高年であろうが雇用が危なくなる可能性は否定できない。そうなれば、AIの苦手な繊細な手作業を行うブルーカラーの方が安泰になるのかもしれない。いずれにしても、現段階では鬼が笑う話である。